
文字サイズ
3月23日に北海道百年記念塔の解体についての質問をさせていただきました。
この記事を投稿している3月24日、第一回定例会閉会日には、議場にて解体関連予算が「賛成多数」で議決されてしまいます。
しかし、解体中止に向けて活動は継続させて頂きますし、長期戦になる見込みの本活動については、それぞれに活動されている国民・道民の皆さんの熱量を束にしていく必要がある段階へと入っていくことになります。
今の私たちが北海道と共にあることをご先祖の皆さんに感謝・慰霊し、その感謝を未来の子孫たちに期待と共に繋いでいく「象徴」としての北海道百年記念塔に対して、責任を果たして参りたいと思います。
解体については、下記の質問にあるように北海道と北海道教育委員会が提訴されたところですし、聞き及ぶところによれば、この動きは後を追うように続くものと承知しております。
引き続きご支持頂けますようにお願い申し上げます。
————————————————————————
北海道百年記念塔について
(一)説明会の議事録について
北海道百年記念広場の整備等に関する説明会の議事録について、道は、説明会開催時点で、一週間程度で全ての質問に対して公開することを明言されておりました。
第一回目が2月9日に開催されて、議事録の公開が2月22日、第二回目が2月10日に開催されて議事録は3月16日、第三回目は2月14日に開催されて議事録はまだ未公開となっています。開催日には未回答であった分も含めた議事録の公開を約束している道にとって、本日現在でも公開されていない状態は「丁寧な対応」とは言い難いと断言できます。
第三回目の公開スケジュールをお示しください。
<答弁>
(文化振興課長)
質疑への対応についてでございますが、道では、これまで、記念塔解体の判断に至った考え方や解体後の広場整備の方向性をお示しした「交流空間構想」につきまして、様々な機会を通じて説明し、広くご意見を伺ってきたところでございますが、改めて、2月9日から3回に渡り、オンラインによる説明会を開催し、合計109名の方々に、ご参加いただいたところでございます。
参加された皆様からは、記念塔に関しまして、これまでの道の維持管理や道民の皆様への周知のあり方、新たなモニュメントに係る費用や今後の進め方など多岐にわたり、ご質問、ご意見をいただいたところでございます。
時間の関係上、その場でお答えできなかったご質問に対しましては、後日回答を作成し、参加された方々にメールでお知らせした上で、ホームページに掲載することとしておりまして、これまで第2回目までの72件を公開し、現時点で回答をお示しできていない第3回目の質疑応答314件につきましては、3月29日を目途にお示しできるよう鋭意作業に取り組んでいるところでございます。
(指摘)
議事録の公開にあたっては、説明会参加者はもとより、報道や一部の道民が高い関心を持って待ち望んでおります。それは議事録公開という事実だけに留まらず、道として答えにくいであろう質問に対して、どのような回答を寄せてくるのかについて、ただならぬ関心をお持ちであるからと承知しております。
まずは、回答漏れのないように、そして1日も早い回答をお願いしておきます。故意に回答を避けることは、不作為として残りますので、ご留意をいただきたいと思います。

(二)説明会の開催について
前回の質問でもお聞きしましたが、2月に開催された説明会がWEB開催であったことや、その説明会の告知が十分でなかったことから、仕切り直した説明会の開催を多くの道民から要望されております。これは、道もWEB開催での説明会時に触れている点でもあります。リアルでの説明会開催の日程や規模感などについて、見通しの見解を伺います。
(文化振興課長)
道民の皆様などへの説明についてでございますが、先月開催した説明会につきましては、当初、会場にお集まりいただく方式での開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルスの感染状況に鑑みまして、オンラインでの開催としたところでございます。
道といたしましては、まずは、説明会の資料や会議録、質疑に対する回答につきまして、道のホームページで公開するなど、道の考え方をご理解いただくよう努めるとともに、今回、参加できなかった方々をはじめとする道民の皆様から寄せられる問い合わせの状況や新型コロナウイルスの感染状況などを踏まえ、必要に応じて対応を検討してまいる考えでございます。
(指摘)
リアル開催での説明会については、開催の検討に留まることなく、開催する前提で準備に入っていただきたいと強く要望しておきます。今月21日には、新型コロナウイルス感染症によるまん延防止重点措置も解除されております。一日も早い開催告知を始めていただくよう、そして、今度こそ広く多くの道民が開催を知ることができる方法で、告知していただけるよう、併せて要請しておきます。
さらに、その説明会では、道の考え方を理解していただく説明会なのではなく、参加者から寄せられた質問に向き合う説明会であることを要求しておきます。
また、これも前回の質問で要請していた点ですが、記念塔の視察は必ず実現させますので、準備のほど、くれぐれもよろしくお願い申し上げます。
(三)「近代化遺産である百年記念塔の偉功遺産としての地位保全の確認宣言請求」について
私の手元に3月11日に届いた訴状によると、3月9日付けで、「近代化遺産である百年記念塔の偉功遺産としての地位保全の確認宣言請求」が札幌地方裁判所で受理されております。
まずは、この事実についての見解を伺います。
(文化振興課長)
訴えの提起についてでございますが、ただ今ご質問のあった事項につきましては、本日現在、道では、裁判所からの訴状は受け取っておらず、受理の状況やその内容などについて、承知していないところでございます。

(四)北海道百年記念塔の登記について
次に、北海道百年記念塔の登記について伺います。先ほどお伺いした訴状の中で、百年記念塔の底地は道の所有地でありますが、記念塔そのものは未登記であることが記載されております。これは事実でしょうか。見解を伺います。
(文化振興課長)
記念塔の登記についてでございますが、先ほどもお答え申し上げたとおり、裁判所からの訴状は受け取っていないことから、その内容は承知しておりませんが、記念塔は、「工作物」に該当することから、不動産登記は行っていないところでございます。
(再質問)
改めて伺います。今となってはそれが道の弱点にさえなっていると見ているところですが、当時は登記する必要がなかったと判断してのことなのでしょうか。それとも登記をし忘れたことが発覚してしまったので、先ほどの答弁に至ると受け止めてよろしいのでしょうか。当時登記を済ませる必要があったと考えているのか、見解を伺います。
(文化局長)
記念塔の登記についてでございますが、記念塔は、「工作物」に該当いたしますことから、建設当時の不動産登記法に基づきまして、適切に取り扱ったものと考えております。
(五)北海道百年記念塔の所有者について
いま未登記であることが答弁されたところでもありますが、道は、記念塔の所有者たり得ないと理解することもできると思います。1970年に竣工した時点で、建設期成会が広く寄付を募り、道の事業から切り離して竣工されたものであることから、所有権不詳とされ、収去明渡しの債務名義でもなければ、道単独で撤去することは非合法であると、その訴状の中では明記されているところであります。この点について道の見解を伺います。
(文化振興課長)
記念塔の所有権についてでございますが、記念塔は、当時、建設主体となりました「北海道百年記念塔建設期成会」から道の規則で定められた手続きに則りまして、寄附の申し込みを受けて、受納し、公有財産台帳に記載した上で、維持管理してきたものでございまして、道が所有権を保有しているものと認識しております。
(指摘)
先ほどの訴状の中では、この他にも様々に史実と並んで、道の瑕疵と不作為が指摘されているところとなっていて、明日にでも議決されようとしている解体予算案に、数多くの疑義が突きつけられていると捉えることができると思います。これらの事実の真偽は、公正な裁判で明らかになっていくものと承知しておりますが、実は前述の説明会で数多くの質問が寄せられた質問の中には、同様の趣旨のものが存在していることを、私達は知らなければならないと思います。この点については、今後の委員会質問の中で明らかにしていく考えでありますので、ご承知おきください。
ちなみに私は、所有者が道とは言い切れないと捉えているところであります。今答弁にあった公有財産台帳に記載されていたとはいえ、未登記であったことも事実だと思います。私は、公有財産台帳が登記に取って代わることを聞いたことがありません。言うなれば、自分の財産目録に書いてさえあれば、所有権を主張できることがまかり通るならば、権利関係をいかようにでも操れることになってしまいます。だからこそ、公的に認められた不動産登記という方法が存在している訳であります。これらの点がまさに争点となって裁判が行われると承知しております。成り行きを見守りたいと思います。
また、この訴状では、被告として北海道教育委員会も記名されているところです。同様に、今回の質問の中であげれば項目にキリがありません。この点については、後の議会議論の中で取り扱っていきたいと考えているところであります。

(六)北海道百年記念塔の新聞報道について
3月12日付の新聞報道によると、北海道百年記念塔の解体着手について某団体の会長が「当然の判断。塔建設の背景に何があるのかよく考えて欲しい」と発言されていることが明記してあります。
道は、この「背景に何がある」と理解しているのか、見解を伺います。
(文化振興課長)
記念塔に関する報道についてでございますが、ご指摘の新聞報道につきましては承知しておりますが、発言の趣旨については把握していないところでございます。
(指摘)
先述の訴状では、多様な北海道開拓先人のご尽力に対し慰霊のまことを捧げるは、末裔として当然の義務ですらあり、何も一部種族だけがメモリアル化される縁は史実上には全く無いのであると記載されております。
この北海道百年記念塔が、「開拓の先人に対し感謝と慰霊のまことを捧げ、将来に向かってたくましい北海道の建設を誓う道民の総意を込めた記念塔」として存してきた以上は、北海道独自の文化財として、維持管理されて当然のことなのであることを申し上げておきます。
またこの期に及んで知らぬふりを決め込む道は褒められたものではありません。偏向した政策に肩入れする様は、他の政策と比べても不自然であることは明らかであります。分かっていてあえて、僕も僕でありますが、答弁を避ける道も道であると思うのであります。そんなタブーを作り出してしまったというのは健全な北海道の元気に繋がりません。お互いに戒めていかなければいけないと考えるわけであります。
(七)北海道百年記念塔の解体予算について
明日の第一回定例会で、北海道百年記念塔の6億4千万円超の解体予算が議決されようとしています。情勢を鑑みると賛成多数で議決されるものと推察しています。これは、ただただ私の力の至らなさを悔いるばかりであります。
しかし、本日の質問で展開したように、今後の道民活動や開催される説明会、そして訴訟などを通じ、北海道百年記念塔の在り方については、議論が継続されるものと考えております。
道は、この状況をどのように捉えているのか、最後に見解を伺いいたします。
(文化局長)
記念塔に関しまして、今後の対応についてでありますが、道では、塔のあり方について、平成28年度以降、様々な分野の専門家や有識者の方々のご意見を伺うとともに、道民ワークショップや出前講座、アンケート調査などを通じまして、道民の皆様から寄せられた様々な意見を踏まえながら、時間をかけ、慎重な検討を進めてきたところでございます。
また、解体の判断に至った考え方や解体後の跡地を含む今後の広場整備の方向性をお示しした「交流空間構想」につきましても、先月開催しました説明会を含め、様々な機会を通じて説明し、広くご意見を伺ってきたところでございます。
道といたしましては、記念塔に対する皆様の思いやご意見を真摯に受け止めながら、今後とも道の考え方について、ご理解いただけるよう努めてまいります。

(指摘)
またここでも、道の考え方について理解いただけるよう努めてまいるが出てまいりました。この点は違うということをはっきり断言しておきます。
道は、道民の考え方を理解しなければならない立場にあるのです。答弁が強すぎます。私はこれまでたくさんの課題を明示し、瑕疵や不作為を明らかにしていくことで、道がとってきた手続きの脆弱を示していく考えであります。
私にも、大きな流れの変化がすぐそこまで迫ってきていることを聞かされているところであります。道のみなさんも真の意味で慎重に誠実に事に当たっていただきたいと要望します。
もう一つ指摘を加えます。
前回質問時にも申し添えた点でありますが、本件を担当されてる道の職員の皆さんにおかれては、本当にご苦労ご心労を掛けてしまっているとお見舞い申し上げるところでもあります。
私は、北海道百年記念塔の取り扱いについては、過去の行政プロセスの中で手続きが進み、今日を迎えていることを十分に承知をしているところでもあります。
しかし、本日ここに「北海道開拓先人に対する感謝と慰霊のまことを捧げ、将来に向かってたくましい北海道の建設を誓う道民の総意を込めた記念塔」の未来を想う時に、胸が焼かれる思いであり、今を生きる者として、先人のみならず子孫に対して、すべきことの使命を思い知らされるところなのであります。
これまで質問の中で判明していることは、「交流空間構想」等の中で道から説明されてきた北海道百年記念塔の解体の経緯については齟齬があり、意図的に時系列を違わせることによって解体推進に都合良く書き換えさせられてしまっていたのではないかという疑義なのであります。
明日、解体予算は成立してしまうこととなるでしょう。しかし、今後明らかにされる史実と事実を基にして、各委員のみなさまをはじめ、それぞれの地区を代表する各派議員として、本件に向き合い、先人と子孫に対して恥ずかしくないご判断を賜るよう願って止まないところであります。
3月11日に行われた一般質問で、鈴木直道知事に質問させて頂いた<内容>と<答弁>です。
世界から多くの観光客にお越しいただくことが、即ち北海道の元気に直結することは、この二年の間の新型コロナウィルス感染症との闘いを通して、皆さんも肌身で感じたのではないかと捉えています。
地域が元気になる手段の一つとして、この機会を上手に活用していただけるように設えたいと思い、質問に至りました。
——————————————————————————
C,アドベンチャートラベル・ワールドサミットについて
アドベンチャートラベルワールドサミットについて伺います。
2020年12月に北海道での開催が正式決定し、その後準備されてきたATWSは、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、2021年5月にはバーチャルでの開催が発表となりました。その後の2021年9月には、改めて2023年に北海道での開催が内定し、関係者の期待がつながったものと承知しています。
これらは、「農業」「エネルギー」に加えて「観光」を三本柱として掲げる私たちの北海道にとって、今後の戦略に適った取り組みであり、官民挙げて取り組むべき政策・施策なのだと確信しています。そこで、知事に幾つか伺うと共に提案しておきたいと思います。

①アドベンチャートラベル・ワールドサミット2021について
最初に、ATWS2021について確認しておきます。
先に述べたように9月のATWS2021はバーチャル開催となってしまいましたが、開催された結果等はこれまでの質問で明らかにさ れていることと承知していますが、その総括は行われているのでしょうか。またその公開についての予定を教えてください。
<答弁>
アドベンチャートラベル・ワールドサミット2021の総括についてでありますが、昨年バーチャル開催されたサミットにおいては、欧米豪を中心に多くの国から、旅行会社やメディア関係者、観光関係団体など617名が参加し、北海道のアドベンチャートラベルのコース等をバーチャルで体験していただくとともに、各種講演や分科会のほか、旅行会社同士のオ ンライン商談会や、参加者とメディアのオンライン交流会などが実施されたところでございます。 サミット開催時に発信した映像については、主催 者や参加者から高い評価を得たところであり、2023年サミットのリアル開催につながったところであります。これらの実施結果につきましては、本年春に予定している実行委員会の総会で報告するとともに、 ホームページでも公表することとしております。
②アドベンチャートラベル・ワールドサミット2023について
ATWS2023について伺います。
開催結果や総括等を受けて、私たちのATWS2023への期待はより高まるものと容易に推測できます。
開催までの一年半で、ATWS2021の準備工程を繰り返すのでは二度開催する意味がありません。順調な開催を期待しているのではありません。私たちは、より効果の高い開催を期待しているのです。知事の見解を伺います。

<答弁>
アドベンチャートラベル・ワールドサミット2023に向けた準備についてでありますが、道では、来年のサミットまでの時間を有効に活用し、本道のアドベンチャートラベルをリアルに体感し、感動いただけるよう、一年を通じたコンテンツの磨き上げや北海道全域での魅力あるツアーコースの造成のほか、アドベンチャートラベルに対応した新たなガイド制度の検討を進めているところであります。私としては、2023年に再び北海道でサミットが開催されるというチャンスを最大限活かし、全道域で機運の醸成を図るとともに、サミットの主催団体と緊密な連携を図りながら、アドベンチャートラベルが本道の観光の主要な柱の一つとなるよう加速的に準備を進めてまいります。
③道内エクスカーションについて
次に、ATWS2023の参加者に提供される道内エクスカーションについて伺います。
事前に伺ったところによると、ATWS2021の参加者に提供される予定だった道内エクスカーションは、サミット開催前に行われるプレサミットアドベンチャー(PSA)15コースと、サミットの初日に開催されるデイオブアドベンチャー(DOA)29コースであると伺っています。
いずれもアドベンチャートラベル・トレードアソシエーション(ATTA)の審査を経て提供されるものと承知しています。
ATWS2023の参加者に提供されるPSAとDOAは、ATWS2021のメニューの継続となるのかを伺います。その44コースについての概要と道内での選定経緯、また誰が企画したコースであるかを含めて教えてください。
<答弁>
道内エクスカーションについてでありますが、ATWS2021においては、サミットの前に希望者を対象に4泊から5泊のツアーとして開催されるプレサミットアドベンチャーを15コース、サミット参加者が全員、初日に体験する、デイオブアドベンチャーを29コース造成したところでございます。これらのコースは、旅行会社が道内各地域を回り、ガイドの皆様などとも相談しながら造成した旅行商品の中から、実行委員会で審査・選定の上、サミットの主催団体であるアドベンチャートラベル・トレードアソシエーションの審査を経て決定したものでございます。 ATWS2023の開催に当たりましては、ATWS2021で造成されたコースを基本としながら、改めて、主催団体の意向も踏まえ、商品の追加や既に造成されている商品 画したコースであるのかを含めて教えてください。 の変更などして対応してまいる方向でございます。

④地域発のエクスカーションについて
道内エクスカーションの在り方について伺います。
ATWS2023の参加者に提供されるエクスカーションは基より、多くの参加者に情報提供されるメニューの創出と共有が必要だと思うのです。道内津々浦々や四季折々に満喫できるアドベンチャートラベルの情報を提供することが必要です。
そこで、道が自治体や地域の観光協会に呼び掛けて、その地域に存するアドベンチャートラベルのコンテンツを、ATTA基準で磨き上げる取組みを主導し展開することを提案します。旅行商品の開発という意味でもあり、その地域の住民に改めて受け入れる覚悟を求めるものでもあると捉えています。
北海道では、余りに当たり前で、時に畏怖の念を抱かざるを得ない「自然」そのものが、私たちに活力を与え元気にすることを再認識することが出来ます。
道の見解を伺うと共に、知事の決意をお聞かせいただきたいと思います。
<答弁>
地域発のエクスカーションについてでありますが、本道は雄大で豊かな自然はもとより、縄文遺跡群やアイヌ文化などの地域資源、さらには、多様なアクティビティを楽しむ環境が整っており、道内各地を訪れなければ体験することができない魅力あるコンテンツを有しているアドベンチャートラベルの適地であると認識をしております。このため、道では、アドベンチャートラベルとして求められる高い顧客ニーズに応えることができるコンテンツの発掘や磨き上げを道内自治体の皆様などとも連携して取り組んでいくとともに、一年を通じた全道各地の魅力ある商品造成を支援し、本道の魅力を世界に売り込む絶好の機会であるATWS2023の場において、世界各国のバイヤーやメディアに向けた道内各地の魅 力を余すことなく紹介する動画を発信するなどして積極的にプロモーションをしてまいります。
3月11日に行われた一般質問で、鈴木直道知事に質問させて頂いた<内容>と<答弁>です。
札幌丘珠空港の利活用については、北海道の活力源としての効果が明確になっているにも関わらず、北海道も札幌市も行政手続きのペースが遅く、いや遅すぎて参ってしまう状態です。
これまで以上に、議員活動を通しながら『北海道の元気』のために働いて参ります。
————————————————————————————–
B,札幌丘珠空港について
札幌丘珠空港について伺います。
札幌丘珠空港については、これまでに会派を問わず多くの質問が重ねられてきたことと承知しています。それらは、いずれにしろ道が果たす役割や滑走路の延長であったり、道内に限らず東日本における防災拠点としての活用であったり、北海道の活力の喚起に向けた方向性の質問であったと捉えています。
私は、これらを「まちづくり」の視点で捉えて質問してきたところでありますが、北海道の人口が驚くほどに減っていくことが明確になっている現時点において、更に新型コロナウィルス感染症の流行が収まりきらぬ現時点において、札幌丘珠空港の活用についての議論が停滞していることを危惧している者の一人として、以下、本定例会の予特と関連させて質問させていただきます。
①国との議論について
最初に、国との調整について伺います。
現時点における札幌丘珠空港の整備計画については、国との間においてどのような内容で進められているのか伺います。そして、その到達度合いはどの程度と見込んでいるのでしょうか。
特に、2030年に札幌オリパラの開催を目指す私たちにとっては、残されている時間には限りがあるのです。
道の責任において行われなければならない国との調整の範囲、言い換えれば札幌市との役割分担を、道はどのように自覚しているのかについて伺っておきます。

<答弁>
丘珠空港の利活用についてでありますが、現在、札幌市では、丘珠空港の利活用のあり方を示す「丘珠空港の将来像(案)」の来年度中の公表に向けまして、国との協議や航空会社など関係者へのヒアリングを進めているものと承知しております。道では、北海道における航空ネットワークや空港の目指す姿を明らかにした「北海道航空ネットワークビジョン」において、丘珠空港の役割を「道内各地の経済・医療・防災を支える航空ネットワークを実現するもの」としており、その利活用等について、これまでも札幌市と連携し、様々な取組を進めてきたところであります。 今後、札幌市における「丘珠空港の将来像」の内容を踏まえ、道としても、全道的な視点から、丘珠空港の一層の利活用と機能強化に向けて、引き続き、 札幌市と緊密に連携を図りながら、着実に取り組んでまいります。
②道が目指す札幌丘珠空港の姿について
私が過去の質問で繰り返し主張してきたことは、札幌丘珠空港は、人口減少を主因とする将来の北海道の活力の減少を埋め合わすだけの主な源となり得るものであります。
私は、道として期待は寄せるものの、その主管が札幌市に存する為に、出過ぎた考えが避けられてきたことに地団駄を踏んでいます。
札幌丘珠空港がどうあれば、北海道の視点で北海道の活力に繋げることが出来るのかを札幌市と共有出来ているのでしょうか。
道として期待する札幌丘珠空港の「仕掛け」を札幌市に示すことが必要です。知事の見解を伺います。

<答弁>
次に、丘珠空港の目指す姿についてでありますが、丘珠空港は、札幌都心に僅か6kmという地理的優位性から、「北海道航空ネットワークビジョン」において、経済・医療・防災など、道民の皆様の生活を支える役割を果たしていくこととしており、今後、空港機能の強化等を推し進めることで、様々な航空路線やビジネスジェットの就航などが期待され、幅広い階層による交流人口の拡大に資する空港となる潜在力を有していると考えております。
道としては、今後、札幌市が地域住民の皆様等との意見交換を行いながら取りまとめる予定の「丘珠空港の将来像」を踏まえた上で、丘珠空港が、国際拠点空港である新千歳空港を補完し、北海道経済を牽引する空港となるよう、引き続き、市と連携を図りながら、必要な取組を着実に進めてまいります。
<指摘>
丘珠空港の質問について指摘を加えます。 私は、丘珠空港の活用によって北海道の活力を創出していくことを目論むにあたり、国と道と札幌の役割は自ずと異なるものと考えております。その中でも、道には航空ネットワークビジョンを用いて、具体的な夢を示していただかなくてはなりません。その航空ネットワークビジョンで示す内容で、国に理解を求め、札幌市にはそれらを可能とする丘珠空港を作り上げていただかなくてはならないのであります。あくまでも、大志を語り上げる北海道でなくてはならないと思うのであります。その大志を語ることができるのは、未来を語る知事だけなのであります。しかし、その航空ネットワークビジョンの中の丘珠空港の取り扱いはほんの一部でしかなく、全く満足できるものとなっていないのが現実です。活力ある北海道の未来を示した目指す姿とはなっていないのであります。どうして国や札幌市に理解を求めることができるのでしょうか。 私には、道に何がそうさせているのか理解することができません。腰が引けているのは札幌市ばかりだと思っていましたけれども、実は道もそうなのかもしれないのでありま す。特に、2030札幌オリパラを目指す私たちは、このナショナルイベントをきっかけとして丘珠空港 の整備を実現させていかなければなりません。残すところ8年となっています。待ったなしです。私に言わせれば、これまでの行政プロセスが遅すぎて苦 虫噛みつぶす思いであります。そのような意味で今回の質問に対する道の姿勢は残念でありません。私は航空ネットワークビジョンが「仕掛け」とするならばその改訂を今後、議会議論の中で強く求めていくこととなりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
3月11日に行われた一般質問で、鈴木直道知事に質問させて頂いた<内容>と<答弁>です。
この質問は、北の元気玉が7年前に当選させていただいた当初より取り組んできている課題です。
エネルギー問題は、私たちの暮らしと切っても切れない関係にあり、昨今の国際情勢の不安定さからも注目される課題となっています。
地域の課題を「燃料」にして、地域内で創り出された「新エネルギー」を、地域内で消費する。
余剰する程に新エネルギーを創出して、地域外に売り出すことで、地域内に「富(活力)」を呼び込む。
これが、北の元気玉が皆さんにお約束した「北海道を元気にする」提案です。引き続き取り組んでまいります。
————————————————————————————
A,企業局の行財政改革について
最初に、企業局の行財政改革について伺いたいと思います。
振り返れば、私は、平成30年の第四回定例会において、企業局に対して「新エネルギー導入の加速化について」質問を行いました。簡単にまとめるならば、より積極的に事業展開を図るべきと提案し、「稼ぐ企業局」となり得るための挑戦的な取り組みについての質問でありました。その答弁の内容では、強く同意して頂けたものと承知しております。
それから3年経過した今、その進捗を確認させて頂くと共に、改めてより具体的な質問を提案含めて行いたいと思います。
①進捗に進捗について
最初に、前回の質問に対しての進捗を確認させて頂きます。
その答弁の中で、「稼ぐ企業局」となり得るために、情報収集や調査研究に取り組むことや、また公営企業管理者からは、新たな事業に取り組むことについても言及して頂いたところです。まずは、それらの進捗状況について伺います。
<答弁>
(公営企業管理者)
新たな事業展開に向けた企業局の取組についてでございますが、企業局では、持続可能な経営基盤の確保と財政マネジメントの強化を図るため、令和2年度に中長期的な経営指針となる経営戦略を策定し、その方策の一つとして、新たな再生可能エネルギーの導入に向けて積極的に取り組むこととしているところであります。
これまで、企業局の強みである発電分野では、全道各地にある新たな水力発電の候補地の調査をはじめ、道内における事例を踏まえて、木材や家畜排泄物を活用したバイオマス発電などについて検討し、経済性の評価や課題の抽出を行ってきたところであります。
引き続き、大学や道総研等と連携し、太陽光など様々な電源開発について調査研究を進め、知見を蓄積しながら、こうした取組がゼロカーボン北海道の実現につながるよう、新たな事業の可能性を見極め、対応していく所存でございます。

②「稼ぐ企業局」について
次に、「稼ぐ企業局」について伺います。
「稼ぐ企業局」になる為にも、自らの強みと弱みは冷静に分析しておくことが必須です。
企業局は、公共性と公益性を求められながらも経済性を発揮しなけれけばならないと考えています。それは、単純に利益の最大化を目指すことが目的ではないと承知しています。
しかし、私は、さまざまな危機に対応しながらも道財政への負担から脱却し、逆に寄与出来る程のチャンスが正にいま到来しているのだと考えています。
企業局は、自身の強みと弱みをどのように分析しているのでしょうか。
自らの強みを伸ばしていくことは、民間企業にとって避けることの出来ない、絶え間ない努力なのであります。時に弱みを切り離していくことさえ避けられないことがありますが、公共性と公益性を求められる企業局にとってはタブーであることとなります。
よって、弱みを凌駕する強みを持つこと、強みを如何に自覚して伸ばしていかなければならないかは、とても重要な選択であることは間違いありません。
企業局は、自らの強みと弱みをどのように自覚し分析しているのかを公営企業管理者に伺います。
<答弁>
(公営企業管理者)
企業局経営の考え方についてでありますが、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギー導入といった社会的要請のもと、シューパロ発電所等での固定価格買取制度、いわゆるFITの適用により、企業局における電気事業は、収益の面で安定した経営が保たれていると認識をしております。
こうした状況のもと、ゼロカーボン北海道に向けた新エネルギーの導入を加速するうえでの企業局の役割を果たすため、改修計画や経営リスクを見据えながら、電気事業で得られた収益の一部を道の一般会計へ繰り出し、道内の再生可能エネルギーのさらなる導入拡大などに充てており、今後も、道の施策を積極的に後押しすることとしてまいります。
企業局としましては、「経済性の発揮」や「公共の福祉の増進」という公営企業の基本原則を堅持しつつ、新たな事業への挑戦なども含め、経営の安定化に向け不断に取り組むことが重要な視点だと考えております。
③企業局の長期借入金等について
次に、企業局の長期借入金等について伺います。
頂いた資料によると、工水部門の未処理欠損金は、平成18年度の資産処分に伴う特別損失処理等の影響が大きかったものの、昨年度までに繰越欠損金が5億程度にまで減少しているそうです。言い換えれば、身軽になった工水部門として平成23年度には黒字化を達成していると示して頂きました。しかし、その名の通り資産を失っていることに他なりません。
確かに会計上の処理としては健全化を実現しつつあるところではありますが、工水部門と電気部門にこれから到来する施設の老朽化や設備更新に伴う膨大な費用を捻出していく為には、一難去ってまた一難といった状況なのではないかと推察しています。
更に、工水部門の長期借入金に至っては、令和2年度決算時で48億円程の未返済額が残り、そのうち近年では電気事業会計からの借り入れを繰り返す状況となっていることは深刻であり、放置できるものではありません。
企業局として、長期借入金の返済についてどのような見通しとなっているのか伺います。
<答弁>
(公営企業管理者)
工業用水道事業の長期借入れについてでありますが、産業構造や社会経済情勢の変化による工水需要の減少に伴い、工水事業は一般会計や電気事業会計からの借入を余儀なくされており、厳しい経営状況となっているところでございます。
一般会計からの借入れについては、工水3地域のうち、今後数年間で苫小牧工水の債務返済が完了するほか、石狩工水についても、新規契約による収益の増加により、借入金の返済が令和7年度から開始できるものと見込んでいるところでございまして、また、電気事業会計からの借入についても、3工水全てにおいて、計画的に返済しております。
企業局としましては、今後とも、立地が進むエネルギーや食品関連分野などへの需要開拓を精力的に進めまして、経営基盤を強化することとともに、施設の計画的な老朽更新などに努めながら、地域経済を支える重要なインフラとして、その役割を果たしてまいります。

④企業局が作り出す新エネルギーについて
次に、企業局が電気事業で作り出している新エネルギーについて伺います。
頂いた資料によると、電気事業で作り出している販売電力量は、平成30年度には3億5761万9千kwhに上るそうです。そのうち非FIT適用となっている分は59%の2億1223万8千kwhです。令和2年度は2億9919万2千kwhに上るそうです。そのうち非FIT適用となっている分は65%の1億9527万1千kwhです。
水力発電である以上、その年の降雪量や降雨量に大きく影響されることは避けられませんが、概ね3億kwhの新エネルギーを販売していると判断することが出来ます。
企業局は、このうち4割を国のFIT制度を活用して有利に売電していると承知しています。しかし、これは期間に限りがある制度です。
ここで提案したいのは、非FIT分にあたる6割程度の発電量についてです。
企業局は、非FIT分については、電力の小売り全面自由化に伴い、一般競争入札によって売電してきました。その売電単価は、令和4年3月までは10.65円/kwhで、令和4年4月から2年間は13.46円/kwhで販売することが決まっています。
企業局の水力発電の発電原価が9円/kwh程度とお聞きしていますから、一見すると採算は合っているように見受けられます。
しかし、「稼ぐ企業局」を目指すのであれば、利益の最大化を目論むことが必要です。
私が、総務部に問い合わせして、知事部局や教育庁、警察本部が使う電力量を調べて頂いたところによると、知事部局551施設の直近3年間の総計平均で7190万kwhを16億1448万円掛けて消費していて、教育庁269施設では総計平均が4530万kwhを10億966万円掛けて消費していて、警察本部799施設では総計平均が2735万kwhを5億7630万円掛けて消費しているのです。金額については、施設毎の入札等により単価は相違しますが、3年間の平均合計で、1619施設が1億4455万kwhを32億44万円掛けて消費することになっています。
先ほど申し上げた通り、企業局の販売電力量のうち非FIT適用となっている分が2億kwh程度となっているので、全てを十分に賄えるだけの電力を生み出していることになります。
更に、電力システム改革における小売りの全面自由化に沿った形で、企業局の販売価格がその時々の入札価格以上であることを見込み、道として買取る価格が入札価格以下であることが担保できれば、双方の経済的有利性を確保することが可能になります。残りの分もダムが所在する自治体を中心に販売することが出来れば、無駄なく消費することが可能です。
但し、託送料等の費用が発生することを考慮しながら検討することを含めた企業局による経営戦略の見直しが必要となります。
因みに、本庁と赤レンガ、議会庁舎の電気調達契約は、令和2年度がkwhあたり18.2円、令和3年度が16.41円となっていることからも、十分に検討するに値する環境は整っていることが判ります。
北海道庁関係の全ての施設を、新エネルギーによって運営させることが出来るのは、ゼロカーボン北海道を掲げる私たちにとってはあるべき姿となるのではないでしょうか。
この取組みは、企業局の経営戦略上は基より、道の施策方針にも合致したものと言えるでしょう。知事と公営企業管理者の見解を伺います。
<答弁>
(知事)
再エネ由来電力の調達についてでありますが、道では、事務・事業に伴い生じる温室効果ガス排出量を2030年度までに2013年度比50%削減する目標を設定しており、その達成に向けて、現在、再エネ由来電力の調達手法や再エネ設備の導入などについて検討を進めているところであります。
企業局が発電する再エネ電力を道有施設で活用することは、更なるCO2排出削減と、電気料金の削減にもつながる可能性がある一方、庁舎などでの電力需要と企業局からの発電供給を同量にするための需給調整が必要となるなど、様々な課題があると考えております。
今後、企業局と一体となって道有施設での活用検討を進め、北海道にとって貴重な企業局の再エネ電力が削減目標の達成につながることを期待しているところであります。
(公営企業管理者)
道有施設への電力供給についてでありますが、FITが適用されていない発電所の電力については、国の電力システム改革による小売全面自由化に伴い、令和2年度から一般競争入札により、小売電気事業者に対し売電しており、最大収益の確保に努めているところでございます。
この電力を道有施設に売電することは、ゼロカーボン北海道のモデルとなり得る取組であるとともに、道有施設の電気料金を軽減する手立てとなるその一方で、企業局の発電量と道内全域に及ぶ約1,600の施設において複雑で高度な受給量の調整が小売電気事業者に求められるなど、様々な課題もあることと承知をしております。
今後におきましては、小売電気事業者とのヒアリングとあわせ、関係機関からご意見を伺う場を設置し、道有施設への売電も含め、実効性ある様々な有効活用の方法について検討してまいります。
⑤経営戦略について
次に、経営戦略について伺います。
以前の質問でも触れていますが、道財政の逼迫が続く現下にあっては、企業局の負債は勿論のこと前向きな投資についても、企業局自身が稼ぎ出して積極的に返済や投資をしていくことが必要なのです。勢い余って道財政の改善そのものに寄与することでさえ可能だと考えています。私たちは、どれだけ稼ぎ出すことが必要なのかを知る必要があります。
世界では、私たちが想像するより遥かに進んだ技術が次々に生み出されています。
ゼロカーボン北海道を目指す私たちにとって、全国に自然エネルギー源の宝庫であることを宣言する私たちにとっても、この分野における優位的立場を保ち北海道の活力を創出していくことは絶対命題でもあると考えています。
現行の経営戦略を決して批判するものではありませんが、より野心的で重層的な戦略を展開していくことが必要です。
先に触れた長期借入金の返済や設備更新等の膨大な資金調達等を可能にする為には、返済バランスの調整と稼ぎ出す必要額の明確化させた上で、その差が前向き投資に充てられるものと承知しています。
現経営戦略は、令和2年度からの10年間を示したものと承知していますが、時に見直しは付き物であることから、これらの要素を含んだものに直ちに改定していくことが必要です。公営企業管理者の見解を伺います。
<答弁>
(公営企業管理者)
経営戦略の見直しについてでありますが、現在、道におきましては、「ゼロカーボン北海道」の実現に向けて、「地球温暖化防止条例」の改正や「省エネルギー・新エネルギー促進行動計画」の見直しなどに全庁を挙げて取り組む中にあって、本道の豊かな水資源を活用したクリーンなエネルギーを供給する企業局の役割は、これまで以上に大きくなるものと認識をしております。
企業局としましては、今後とも、令和2年度からスタートした経営戦略のもと、持続可能な経営基盤の強化を図るとともに、新たな電源開発の可能性を探る取組やコロナ禍における本道経済の動向など社会情勢の変化を踏まえ、脱炭素化といった時流をとらえた先導的役割を果たすよう、経営戦略のブラッシュアップについて検討してまいります。

⑥経営戦略室の新設について
次に、経営戦略室の新設について提案します。
これまで伺ってきた点や提案させていただいたように、野心的に「稼ぐ企業局」となる為には、現時点での強みである電気事業の拡大が必須です。
しかし、やみくもに事業拡大を急いでも、公営企業としての役割を果たすことは出来ません。単純に利益を生み出せば良いだけではない責務がそこには在るものと考えています。
それは電気事業に留まることなく、道総研や民間企業と共に世界から先進的な技術の取り込みを模索し、道内外に導入される事業のコンサルタント的役割を果たすことで権利金を獲得することも十分に可能となります。
更に、世界の先進的な情報や過去の取り組みの成功例や失敗例を収集し、シンクタンク的な機能を持ち合わせることで、企業局自身や自治体や民間企業が今後取り組む企業活動の力強い根拠や支援につながると考えられます。
ゼロカーボン政策が華やかし今、自然エネルギー源の宝庫を自称するからこそ北海道がとれる立ち位置なのではないかと信じています。
私は、このような基礎的活動と共に稼ぎ出さなければならない利益をシュミレーションしたり、事業計画を立案し上申する部署が必要だと提案させていただきます。
企業局は、「工水事業部門」と「電気事業部門」を抱えるのですから、横断的に検討を重ねられるように、また道総研や民間企業と協働して世界の新技術情報に敏感になる為に、公営企業管理者直轄での経営戦略室の創設を提案します。また、先に質問した通り、この構想は道庁全体の財政やエネルギー政策に資するものでありますので、知事部局からも人材を集めた全庁横断的な組織づくりを検討すべきだと考えています。
知事と公営企業管理者の見解を伺います。
<答弁>
(知事)
企業局との連携についてでありますが、道では、「ゼロカーボン北海道」の実現に向け、国内随一のポテンシャルを有する再生可能エネルギーなど本道の強みを活かし、脱炭素化に向けた様々な取組を展開することとしており、そうした中で、水力やバイオマス、太陽光など、本道の豊富なエネルギー資源の利活用や調査研究を進める企業局の果たす役割は非常に大きいものと考えております。
これまでも企業局が有するノウハウや知見を全庁的に活用する観点から、庁内関係部局で構成するプロジェクトチームへの参画や、人事面での交流を行ってきたところであり、今後とも、企業局において、再生可能エネルギーの導入促進に向けた体制づくりが進むよう、より一層連携を深めてまいります。
(公営企業管理者)
組織体制の強化についてでありますが、企業局ではこれまで、電力システム改革や産業構造の変化の荒波の中で、電気事業や工業用水道事業の安定経営のため、施設の計画的な管理運営や新たな需要開拓に取り組むとともに、地域の再生可能エネルギーの導入に向けて、「アドバイザー制度」や「小水力モデル事業」などを通じ、道内市町村への側面支援により、脱炭素化を後押ししてきたところでございます。
「ゼロカーボン北海道」を旗印に大きく舵が切られる中で、今後とも事業の安定経営に努めるとともに、地方公営企業法の基本原則のもと、「稼ぐ」という視点を持ちながら、しっかりと収支見通しを定め、収益性のある新たな事業についても積極的に検討を行ってまいります。
こうした取組の実現に向けて、企業局としては、経営の専門家や関係する団体、企業との意見交換をはじめ、議員のご提案のように、庁内関係部局との連携強化を図りながら、企業局内に企画調整ポストを新設するなど、組織の充実に努めてまいります。

⑦知事の決断について
最後に、知事の決断について伺います。
道財政への貢献についてこれまで提案してきたように、企業局には「稼ぐ企業局」となり得るために野心的な改革を求めています。
「経営戦略室」の立上げを通じて企業局の稼ぐ力を高めると共に、生み出された収益を道の一般会計に繰り入れることで、道庁全体で、より効果的な事業を生み出し、道財政の健全化にもつなげていくことが可能だと考えています。
道では、「行財政改革の基本方針」を定め、2025年までの収支対策や財政健全化の目標を掲げていますが、企業局の収益を活用することにより、財政改革を一層加速すべきと考えます。
知事の挑戦的な英断を期待して見解を伺います。
<答弁>
(知事)
今後の財政運営についてでありますが、電気事業会計においては、平成29年度からその収益の一部を一般会計へ繰り出し、道内の再生可能エネルギー導入拡大の推進などに寄与してきているところであり、今後とも、企業局と庁内関係部局がより一層連携し、電気事業の収益を活用しながら、引き続き、ゼロカーボン北海道の実現に向けた取組を進めていくことが重要であると考えています。
こうした中、この度、改訂を予定している「行財政運営の基本方針」においても、更なる歳入の確保のほか、民間資金の積極的な活用などによる政策財源の確保に取り組むこととしているところであり、道としては、ゼロカーボン北海道をはじめとした政策展開にも適切に対応していくことができるよう、財政の健全化に向けた取組を進めてまいります。
令和4年2月24日の環境生活委員会で「北海道百年記念塔の説明会について」の質問を行いました。
北海道百年記念塔の解体については、現在の私は「解体反対」の立場を取らせて頂いています。
北海道の開拓に関わられた全ての先人への感謝と、北海道の未来を担う子供たちへの期待を込めた開拓記念塔を解体することは避けなければなりません。
特に、先日、道によって開催された説明会を通して、道による瑕疵や不作為を整理していくことによって、最悪の事態への収拾を図りたいと考えています。
残念ながら北海道議会自民党会派では、北海道百年記念塔解体に賛成している議員が多く孤軍奮闘中ではありますが、会派内有志と共に活動中でございます。
更には、ほとんどの道民が北海道百年記念塔の解体を知らないという惨憺たる状態であることも判明しております。
北海道議会議員の一人として、その責務を果たしてまいります。
よろしくお願いいたします。
———————————————————-
(一)説明会について
早速ですが、幾つか質問をしてまいります。先日開催された北海道百年記念広場の整備等に関する説明会について伺います。
私はこの説明会の2月9日に参加させていただきました。ZOOMでのWEB開催となりましたが、他の開催日も含めた参加人数や、寄せていただいた意見等の傾向について教えてください。
(文化振興課長)
説明会の開催結果についてでございますが、道では、記念塔解体の判断に至った考え方や解体後の跡地を含みます今後の広場整備の方向性をお示しした「交流空間構想」につきまして、これまで様々な機会を通じて説明を行い、広くご意見を伺ってきたところでございますが、改めて、道の考え方を説明する場として、2月9日から3回に渡り、オンラインによる説明会を開催したところでございます。
説明会への参加人数につきましては、それぞれ定員100名に対しまして、1回目が32名、2回目が26名、3回目が51名となっており、合計109名の皆様に貴重な時間を割いていただき、ご参加をいただいたところでございます。
参加された皆様からは、塔の解体に関しまして、これまでの道の維持管理や道民の皆様などへの周知のあり方、また、新たなモニュメントに係る費用や今後の進め方などについてのご質問のほか、塔の存続を求めるご意見などをいただいたところでございます。

(二)説明会の開催方法について
次にですが、この説明会の内容についてでございます。この説明会に参加した私の率直な感想は、道としては、北海道百年記念広場の整備等について説明し、道の考え方を通したかったのでしょうが、寄せられた質問のほとんどが、百年記念塔の維持管理や解体についての質問であって、道が目論んだものとは相違していたと受け止めております。
以前の私からの質問で、何度も丁寧に説明すると答弁し、約束していただいたところではありますが、開催したアリバイが残っただけであり、とても丁寧に対応したとは受け止めておりません。それは寄せられた質問の主旨と異なる回答が目立ち、さらに都合が悪いと目される質問に回答しないといった有様です。これが丁寧な対応と言えるはずがありません。
道も想定していなかったと思われる量の質問が寄せられて、終了時間が迫る頃には、私から「回答しきれない質問に対しての対応について」質問をするといった事態になった程であります。その質問に対する道の回答として、後日全ての質問に対して、回答をホームページで公開する約束をすることになったと承知をしております。
今回の説明会は、コロナ禍の影響を理由にして、ZOOMによるテレビ会議方式で開催されています。参加者からの質問はチャット形式によって寄せられ、道からの回答は映像と音声によって返されました。しかし、音声が正常に聞き取れない事による苦情も多く寄せられたところです。それは私には滑稽にさえ映っていましたし、これでは開催の意義は満足させられないと受け取っておりました。
道による以前の説明によりますと、この説明会は、当初予定ではリアル開催の設定になっていたと承知しております。しかし、今後の感染症流行の状況を踏まえながら、Web開催になったと説明をされております。今後、具体的にはどのように丁寧に対応していくことを想定されているのか、寄せられている意見や質問に対して丁寧に対応することを、改めて確約していただきたいと思います。見解を伺います。
(文化振興課長)
道民の皆様などへの説明についてでございますが、この度の説明会につきましては、当初、札幌市など3カ所で会場にお集まりをいただく方式での開催を予定をしておりましたが、新型コロナウイルスの感染状況に鑑みまして、オンラインでの開催とさせていただいたところでございます。
参加された皆様からは、記念塔の解体に関するご質問やご意見に加えまして、説明会の開催方法についてもご意見をいただいたところでございます。道といたしましては、まずは今回の説明会におけるご意見に対する資料や会議録を道のホームページで公開するなど、道の考え方について丁寧にご説明をし、ご理解をいただけるよう努めてまいりたいと考えております。
(再質問)
質問を重ねます。私はですね、今の答弁では不十分であると受け止めております。この3回の説明会で果たし切れていない道の役割を、改めてリアル開催の説明会によって丁寧に対応することが必要だと考えております。また、道は、道の考え方を丁寧に説明すると繰り返しますが、先程の答弁の中にありましたけれども、道の考え方を説明する場と道は位置づけていてですね、事の本質がそこにないということはですね。道民から寄せられている意見や質問に丁寧に対応することが必要なんです。道民から寄せられている意見や質問によって、道の案を検証し、公表することが必要となります。リアル開催の確約と、丁寧に対応する内容についての見解を求めます。
(文化局長)
重ねてのお尋ねでございますが、道民の皆様への説明についてでございますけれども、会場にお集まりいただく方式での開催につきましては、今回の説明会でのご意見や、道民の皆様から寄せられる問い合わせの状況、それから新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえまして、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。
(指摘)
私はリアル開催の確約を求めた訳でありますが、必要に応じて検討ということが何にあたるのか。これは日本語の解釈上の話でもあるし、道庁内の不文律というか、解釈によっても異なるところだとは思いますが、今後、質問を進めるにあたって、いかにこのリアル開催のですね、必要性が高まってくるのかということを、道にはしっかりと受け止めていただいて、開催を調整し、実行していただきたいと要請をしておきます。

(三)会議録等の公表について
次に道が約束した議事録の話です。3回の説明会で数多く寄せられた質問に対して、時間制限によって回答できなかった分も含めて、1週間程度の後に議事録を公開されると説明会の中で道は約束をされました。
実は、参加者による議事録は、3回目に開催された14日夕方の2日後にはウェブ上で公開されておりました。今週の月曜日には道が作成した一部が手元に届いたところではありますが、いまだ半分以上の質問に回答出来ていない状態でありました。これはウェブ開催、覆面開催の弊害と解釈するしかありません。
質問の中には、道にとって回答し難い内容のものも見受けられると考えております。また、説明会内で約束していただいている全ての質問に回答し公開するには、今しばらく時間を要するものと感じているところでもあります。
道は、道の考え方を知らしめる場としてしか今回の説明会を位置付けていないのではないでしょうか。要するに、寄せられる意見を受け止める考えなど最初から無かったのではないでしょうか。いわばガス抜きです。実は、あえて具体的な指摘はしませんが、その意図を道の発言の端々から感じることが出来ていると私は捉えています。
この度に寄せられた質問に対して、道はどのように対応していくお考えですか。また、遅れている議事録の公開について、期限や公開場所を明示いただきたいと思います。見解を伺います。
(文化振興課長)
説明会におけるご質問等への対応についてでございますが、今回の説明会の資料及び会議録につきましては、道のホームページで公開するとともに、時間の関係で、その場でお答えできなかったご質問に対しましても、回答を作成の上、公開してまいる考えでございます。
今日現在、各回の会議録及び第1回目の質疑応答につきましては、説明会に参加された方々にメールでお知らせした上で、ホームページに掲載しているところでございまして、第2回目及び第3回目の質疑応答につきましても、できる限り早急に回答を作成の上、同様に順次、公開してまいる考えでございます。
塔の存続を願う方々の思いや主張に対しましては真摯に受け止めながら、今後とも道の考え方について、ご理解いただけるよう、道民の皆様からの問い合わせなどに対して、丁寧に対応してまいりたいと考えております。
(指摘)
今、答弁の中にあったメールでお知らせいただいたというのは、私も第1回目に参加したわけでありますので、そのメールを受け取ったわけでありますが、道のホームページ上で公開されるといっても、巨大な道のホームページマップというかエリアではありますので、探しきれないことが考えられますので、メールでお知らせいただいたというのは、非常にありがたかったと感じております。2回目、3回目の質疑応答分に関してもですね、同様に対応願いたいと思います。
また、今回公開される議事録については、公開され次第、民間の手によって検証されることになると承知しております。検証された回答を基にして、改めて整理された意見と質問が寄せられることになるとお聞きしています。今後の委員会で、それらを基にした質問をさせていただくことになりますので、承知おきください。

(四)解体費の増額について
次に、道が計上しようとしている解体工事費等について伺います。
以前提出された資料やこの説明会によれば、解体工事費は7億2千万円程となっています。当初予算の4億4千万円と比較しても1.64倍です。更に前回の質問で、更なる増額が見込まれることも道は認めております。このままでは、この増額は認められるものではありません。この増額によって維持管理費との差は縮まるなど、道が解体の根拠としてきた根本が崩れているのだと理解しています。それらの具体的な指摘が、今回の説明会内で寄せられた意見等の中にも多く存在しています。その中には、目を疑うような内容のものもあったと捉えております。
前回の質問の際に別の委員からも指摘されましたとおり、承認されてしまった点については覆しようのない事なのかもしれません。しかし、私は、今回の説明会によって提示された質問内容が、議会に報告されていた内容と現実が大きく異なっている点や解体予算の大幅な増額と今後の更なる増額見込みなどについて、それらの状況は大きく変わっているものと理解しています。
この度の令和4年度予算として計上されようとしている解体工事費等についての道の見解を伺います。
(文化振興課長)
解体工事費についてでございますが、平成29年の調査につきましては、塔の内側に足場を設置し、解体を進めることといたしておりました。本年度に実施した実施設計の結果につきましては、塔の老朽化の状況に鑑みまして、工事に伴う落下物による被害を防止するため、作業工程を細分化し、塔の外側にも足場を設置して解体を進めることとしたことや、平成29年以降の労務・資材単価の上昇などによりまして、解体工事費が増加したところでございます。
(指摘)
実は、この質問を練り上げている最中に、本日の委員会に報告されている北海道百年記念塔解体費が、限度額を6億300万円とされていて、4千326万9千円のみを計上されていることを知ったところです。これはどういった意図なのかと考えておりますが、委員会内において報告のみということになっておりますので、指摘に留めますが、いずれにしても、私は、限度額増額についての承認を同意することは出来ません。明言をしておきます。

(五)寄せられた質問について
これまで、道は、一貫して「安全性の確保」と「将来世代の負担軽減」の観点で解体理由として議会に説明してきました。しかし、今回の説明会に寄せられた質問の中で、幾つも無視できない内容のものが存続しておりますので、その一部を検証してみたいと思います。
例えば…、
1 老朽化の原因について
第二回の説明会で寄せられた質問に対して、道は「塔の所有者として適切な維持管理に努めてきた」と繰り返し回答しております。この点は、そもそもおかしな回答となっていて、適切な維持管理に努めれば、腐食等の不具合は防げる又は進行を遅らすことができるものなのであり、道が提案している解体案は、この根本からずれていると断言できます。見解を伺います。
(文化振興課長)
塔の老朽化の原因についてでございますが、専門家の方々からは、塔の構造上、外板周辺部の錆の進行と剥落につきまして、その程度を軽減する処置はとれるにしても、完全に防止することは困難との指摘を受けており、道では、これまで、専門業者による調査結果に基づきまして、保守管理計画を策定し、錆の除去や防錆措置など計画的な維持管理に努めてきたものの、錆や腐食の進行など、老朽化の進行を完全に防ぐことは、難しいものと認識しております。
(指摘)
これは、禅門答ではないのですから、この度の道の答弁では承服しかねます。私は、形あるものは壊れることくらいは承知しております。しかし、それを計画的な維持管理によって長寿命化することが道の責務なのであって、不十分な維持管理を棚に上げておいて、それを理由に解体すると手続きを進める道には瑕疵があるものと考えております。この議論は、別の機会に取り上げてみたいと思います。
2 道民への周知について
道は、百年記念塔の解体について、どの程度の道民が知っているものと捉えているでありましょうか。説明会の質問によると、ごく限られた方しか周知されていないと捉えることができます。当該地元の住民でさえ、学校関係者でさえ、解体そのものをご存じないケースが多すぎます。例えば、町内会長がご存じでも町内会員が知らない、学校長が知っていても教師や生徒が知らないといったような場合です。
記念塔の建立経緯や塔に込められた開拓の感謝と思いを顧みると、道民の理解が少ない中で計画を推進することには同意できず、道議会の同意を得たことがこれにあたると道が捉えているならば、道議会議員が多くの道民に知らせる義務を果たしきれていないことが原因となります。道は、今後どのように周知を進める考えなのでしょうか。どの程度まで周知が進めれば、道民の理解を得られたと判断するつもりなのでありましょうか。
道が、こうしてまで進めたい計画であることはこれまでの立ち振る舞いで理解しておりますから、周知が進まない原因は道にあると言わざるを得ません。見解を伺います。
(文化振興課長)
道民の皆様への周知についてでございますが、道では、記念塔を含む百年記念施設のあり方に係る検討を行うにあたりまして、その議論の経過も含め、多くの道民の皆様に幅広く周知の上、ご意見をいただくことが必要と考えておりまして、道のホームページへの掲載はもとより、「交流空間構想」の策定にあたりましては、検討会議の開催の都度、報道発表を行うなど、周知に努めた結果、新聞やテレビなどで取り上げていただいたところでございます。
また、道民ワークショップや出前講座の開催、アンケート調査の実施などを通じまして、道民の皆様のご意見を伺うとともに、「交流空間構想」を策定する際には、その内容につきまして、北海道商工会議所連合会などの経済団体や北海道市長会、町村会をはじめとする各自治体、地元の市役所や区役所に加えまして、地元町内会の方々や記念塔を校歌・校章に用いている学校に対しましては、それぞれのご都合を伺いながら、可能な限り直接、お会いし、記念塔の解体もやむを得ないとした方針につきまして、説明を行ってきたところでございます。
道といたしましては、今後におきましても、様々な機会を通じまして塔の解体の判断に至った道の考え方につきまして、ご理解いただくよう努めてまいる考えでございます。
(指摘)
道が行ってきた周知のための方策が十分なものであったとは言い難いと考えております。要するに目的と手段が入れ違ってしまっております。
今、道が答弁した方策を行ったから十分な周知ができたと答弁すること自体が詭弁です。答弁にもあったとおり「塔の解体の判断に至った道の考え方についてご理解いただくように努める」といった立場をとるうちは、この問題は解決する訳がありません。
塔の解体の判断に至った道の考え方についてご理解いただくよう努めるために、丁寧な対応をいくら繰り返しても、この問題は解決しないのであります。まずは、十分な周知を行うために、どんな方策をとらなければならないかを真剣に考えていただきたいと強く要請しておきます。

3 道民への効果的な周知方法について
道がこれまでに行った周知案について、どうして周知が進まないと考えているのでしょうか、伺います。その周知を満足させるために、具体的にどのような方策をとる考えなのかも伺っておきます。
(文化振興課長)
道民の方々への周知方法についてでございますが、道政を進める上では、様々な情報をタイムリーに発信をし、広く道民の皆様からのご理解とご協力を得ることが不可欠でありますことから、道といたしましては、ホームページや報道への情報提供などを通じまして、幅広く情報をお伝えできるよう取り組んでいるところでございます。
こうした中、平成30年12月に発表いたしました交流空間構想につきましては、道民ワークショップの開催や大学への出前講座のほか、全道各地から参加が見込まれる行事と連携をしたアンケート調査の実施、さらには、道のホームページを活用し、広く意見を募集するなど、道民の皆様にご理解いただけるよう取り組んできたところでございます。
また、構想策定後の一昨年の6月には、老朽化した記念塔の現状を認識していただくため、報道機関とともに、塔の存続を求める団体の方々からのご要望による視察を実施をし、この様子については、多くの新聞やテレビで大きく取り上げられたことから、報道を通じまして、道民の皆様に塔の現状を相当程度認識をいただけたものと考えているところでございます。
道といたしましては、今後、新たなモニュメントの設置や百年記念広場の整備に関する情報につきましても、道の広報媒体等を積極的に活用しながら、地元住民の方々はもとより、道民の皆様への効果的な周知について鋭意取り組んでまいる考えでございます。
(再質問)
量的に必要な道民の周知を獲得し、仮に過半以上の賛同が得られるならば、道の考え方にも正当性は帯びてくると思います。しかし、実際には満足な周知も得られぬままに、道の考え方を周知したと都合良く解釈する姿は、褒められたものではありません。それを道民に見抜かれてしまっているのだと私は捉えております。
さらに、今の答弁の中で、最後に「道としては、新たなモニュメントの設置などの情報について周知を進めていく」これはですね、答弁として悪質だと思います。私が伺っているのは、その正当性、道がこれまでとってきた解体案についての根拠とされてきたことに対しての疑義を説明会等によってつきつけられているものに対し、どのように答弁、回答しながら、多くの道民の皆様に理解を求めるように周知をするということをしているのであって、論点がかわされていると思います。見解を伺います。
(文化局長)
道民の皆様への周知に関しての重ねてのお尋ねでございますけれども、道といたしましては、今後、記念塔の解体の判断に至った考え方も含めまして、新たなモニュメントの設置や百年記念広場の整備に関する情報につきまして、道の広報媒体等を積極的に活用し、道民の皆様への周知に鋭意取り組んで参ります。
(指摘)
まあ、同じ内容の答弁の繰り返しなんでしょうね。このまま、答えてください、道の考え方についての説明の周知、もう行ったり来たりでありますので、まとめに入りますけれども、いずれにしても、道が説明したくない解体に至る考え方を理路整然とまとめると、多くの質問や意見がそこに寄せられているわけですから。そこについての議論をかわし、道の考え方、交流空間構想をつくります、新しいモニュメントをつくります、という説明でつきとおすということに対し、非常に違和感を覚えるところでありますので、今後の委員会質問等で明確にしていきたいと考えるところであります。

4 アンケート結果について
第3回目の質問の中に、平成30年4月から6月の施設利用者に行われたアンケートによると、存続して欲しいとの回答が59%であったとのことです。これを以て道民の意思と断言することはもちろん出来ませんけれども、過半であることは事実です。道はこの道民の意思に「丁寧に対応した」とは言えません。見解を伺います。
(文化振興課長)
アンケート調査の結果についてでございますが、道では、「交流空間構想」の策定に当たりまして、百年記念施設の利用状況を把握するとともに、記念塔の存続などについて、道民の皆様から幅広くご意見を伺うため、アンケート調査を実施したところでございます。
百年記念施設を利用される方々におきましては、記念塔の存続を希望する意見が多く、一方で、全道の社会人及び大学生に対するアンケート調査では、解体もやむを得ないとする意見が多いなど、道民の皆様の間には様々な考え方があったところでございます。
このため、道といたしましては、塔の安全性につきまして、専門家の方々の知見も伺いながら、検討を行いましたが、最終的に、塔の構造上、老朽化の進行を完全に防ぐことは難しく、公園を利用される方々の安全確保などの観点から、解体もやむを得ないと判断したところでございます。
(指摘)
今の答弁で明確になったことは、道は道民の意思はさておいて、専門家による知見と安全確保の観点から判断したとおっしゃるのであります。この点については、この後に質問する項目など、後日の委員会等において反証をしていきたいと考えております。
5 維持管理について
第3回の質問によると少なくとも平成29年度から維持管理費を掛けなくなったと指摘されています。維持管理費が極端に少なくなったのは平成22年度からという質問もありました。これは施設管理者としての単純な瑕疵に違いありません。見解を伺います。
(文化振興課長)
記念塔の維持管理についてでございますが、道では、塔の完成から10年を経過した昭和55年以降、概ね10年ごとに専門家の方々によります老朽化の状況調査を実施するとともに、以後10年間の保守管理計画を策定した上で、老朽化した箇所の修繕や老朽化の状況に応じた大規模な修繕を行うなど、塔の所有者として必要な維持管理に努めてきたところでございます。
なお、ボルトの緩みや錆片落下が確認をされ、塔の立入禁止措置を講じた平成26年以降につきましては、専門業者による調査結果に基づきまして、緊急的に補修が必要な箇所の修繕を優先して行うとともに、塔の解体方針の決定後におきましても、必要な点検・補修を行ってきたところでございます。
(指摘)
この点に関しては意見交換時に示していただいた資料によって、維持管理費を掛けていない訳ではないことを確認をしております。しかし、何に費やしたのかまでは確認をしてはおりませんが、平成30年に488千円、令和元年に242千円 とんで令和3年度に420千円という実績は健全な維持管理に努めた証とは言えない金額だと受け止めています。
それまでの4,200千円から21,800千円に比べても明らかです。この点についても民間による検証を待つこととします。

6 建築家からの提案等について
第3回の質問によると、北海道百年記念塔の未来を考える会は建築士有志の皆さんで組織された会と承知をしております。いわば、専門家です。重ねるならばボランタリーベースの会です。
道はこの会から知事あてに3度の公開質問状を受け取っています。さらに、十数名の建築士さんによって塔内の視察も行われていて、「塔は健全」、「外皮は熟成」として、大修繕は不要であり、維持管理についての提案を受けております。
しかし、回答を避けております。避け続ける理由と回答を求めます。見解を伺います。
(文化振興課長)
建築家の方々からのご提案などについてでございますが、ご指摘の内容につきましては、一昨年の11月に道の方に提出をされました公開質問状の中で述べられております「塔は健全である、大規模改修の必要性はない」との記述を指しているものと考えているところでございます。
この主張に関します道の考え方につきましては、既に同年6月の公開質問状に対する道からの回答の中で、「平成29年度に民間事業者に委託して行った維持管理に関する調査におきまして、主体鉄骨部は、最低限必要な状態を維持継続している一方で、塔体については、常に過酷な環境下にあるため、経年とともに、二次部材の腐食、溶接の破断、錆片、錆粉等の不具合が進行すること、不測の落下事故を完全に防ぐことは不可能に近い」との調査結果をお示ししながら、回答させていただいたところでございます。
また、こうした状況から、記念塔存続をさせ、今後とも維持管理を行う場合には、定期的な保守管理の費用に加えまして、大規模改修に要する費用がかかる、との調査結果につきましても併せてお示しし、その必要性についてお答えをさせていただいたところでございます。
(再質問)
今の答弁の中で、指摘の内容は「一昨年の11月に道に出された」というふうにおっしゃった後、「同年6月の公開質問状に対する」というふうにお答えいただいていると思いますが、時系列的にちょっとおかしいような気がするのですが、これでよろしいのでしょうか。
(文化局長)
時系列的には答弁させていただいたとおりで、11月の公開質問状の前にいただいている公開質問状の中で、時期が6月になりますが、お答えをさせていただいているということです。
(再々質問)
3回質問されている中の、2回目3回目とか、1回目2回目ということで理解しました。
道はいずれにしても、この百年記念塔の未来を考える会の質問と要望に真摯に答えていかなければなりません。この春には、新たな専門家による塔内外の視察と診断を受ける必要があると思います。現状、隠す必要は全く考えられないので、場合によっては有効な案が提案されることもあるでしょう。当然ですが、私も含め、有志でご同行したいと考えております。この未来を考える会からは改めて10階以上の視察に含めても申出があったところでありますが、この開催を約束していただきたいと思いますが、見解を伺います。
(文化局長)
記念塔内部への視察などについてでございますが、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、道では、塔の老朽化の現状や解体の判断に至った考え方をご理解いただけるよう、存続を求める2つの団体の方々からのご要望を受けまして、一昨年の令和2年6月に報道機関15社の方々とともに普段立入ができない記念塔内部の現状をご覧いただいたところでございます。
この視察の結果を受けまして、令和2年11月に北海道百年記念塔の未来を考える会の皆様方から提出のあった公開質問状に対しましては、先ほど答弁をさせていただいたとおり、平成29年度の調査結果をお示ししながら、道の考え方につきましてお答えをさせていただいたところでございます。
現在、記念塔はエレベーターが使用できないことに加えまして、錆や腐食の進行に伴う錆片などが視察者の歩行に支障をきたす可能性があるなど、安全性を十分に確保することが難しい状況にありますことから、再度の視察の実施につきましては、慎重な対応が必要と認識しているところでございます。
(再々々質問)
この件も「視察させてください」「危険です」の繰り返しでは、話が収まるところに収まりません。いずれにしても、私たち道議会議員の立場で視察の実行をすることは可能だと考えておりますので、その場合に、考える会の皆さん、要するに建築士・専門家の皆さん、同行いただくスタイルは、申し入れ、実現実行させていただこうと考えておりますので、そのつもりでいてください。
先日の報道で知ったところでありますが、この塔を設計された井口健さんがインタビューに答えていらっしゃって、「道民の意思が最終的に正常な情報を与えられた上で判断されたことについては、その決定について僕はそうですかわかりました、と素直に受け止める」とおっしゃっております。これは一昨日放送された部分です。
しかし、私は、道民はとても正常な情報を与えられたと思っておりません。井口健さんに、まさにこの台詞「最終的に正常な情報を与えられた上で判断されたことについて」と言わしめてしまう環境が、今あるのだと思っております。このことについて、道はどのように受け止めていらっしゃるのか伺います。
(文化振興課長)
記念塔に関する情報についてでございますが、道といたしましては、記念塔のあり方の検討にあたりましては、様々な分野の専門家・有識者のご意見や、道民の皆様から寄せられた様々なご意見を踏まえた上で、十分に時間をかけ、慎重に検討を重ねるとともに、議論の経過や、塔の解体もやむを得ないと判断した考え方、安全性に係る専門家の方々のご意見や今後の維持管理費などにつきまして、広く公開をするとともに、様々な機会を通じて説明に努めてきたところでございます。
なお、塔の設計者の井口様に対しましては、塔の現状や議論の経過をご説明するとともに、今後のあり方などに関してご意見を伺うことが必要であると考えまして、平成29年以降、5回にわって直接、お会いし、道の考え方をご説明し、ご意見を伺ってきたところでございます。
(指摘)
道民に対しても、井口健さんに対しても、道の考え方は変わっていないと今の答弁ではっきりわかりました。ただ、これまでの質問、さらには今回の3回の説明会等々によって、道が様々に検討されてきた専門家だとか、道民を含めて、様々な意見、質問の都合のいいとこだけ取り上げて、だから、安全確保と将来世代に対する負担軽減という観点で解体するに至ったとおっしゃっている。
一方、説明会を中心に寄せられていることは、全てを正確な情報を明らかにした上で、その判断に至れないということをおっしゃる道民の方々が多くいるいうことなのであって、これはもう道が態度を変えていただくしか解決がないのかもしれません。
一連の質問で申し上げているように、公平な専門家による判断と、必要十分な道民の意思によって、記念塔の今後のあり方を模索する必要があると私は申し上げているのであり、道がこれ以上面倒を見れないと言うのであれば、民間による存続を含めた検討を行う時間が必要だと考えております。
7 道の立場について
ここに挙げていた質問はごく一部でありまして、冒頭でお話を聞いたように300以上の質問が寄せられているものに対して、道がその説明の中で答えたものが6、70くらいしかありませんし、そういった状況の中ではですね、道から公開される説明会の議事録を精査することによって具体にそれぞれを理解していくことができるんだと考えております。その中で、道の過失や不作為が明確になっていく点が多いと私は受け止めていて、今後の北海道百年記念塔のあり方が議論される中で、道の解体推進の立場が揺らいでくると私は想定をするわけであります。見解を伺います。
(文化局長)
道の立場についてでございますが、記念塔につきましては、昭和45年の完成後、建設主体の「北海道百年記念塔建設期成会」から道に寄贈されたものでございまして、その後、道は所有者として、完成から10年を経過した昭和55年以降、概ね10年ごとに専門家の方々による老朽化の状況調査を実施し、以後、10年間で修繕など対応すべき事項と費用を示した保守管理計画を策定した上で、老朽化した箇所の修繕や改修工事を計画的に実施してきたところでございます。
こうした中、平成2年に実施いたしました老朽化の状況調査の結果に基づきまして、平成4年にエレベーターの更新など約2億300万円の内部改修を行いますとともに、平成9年の調査結果に基づきまして、平成11年には、外部パネル接合部に係る錆片の除去など約3億4,500万円の外部改修を行ったところでございます。
道といたしましては、こうした施設・設備の耐用年数や老朽化の状況に応じた大規模な修繕を行うなど、所有者として適切な維持管理に努めてきたところでございまして、ご指摘されるような道の不作為などはないものと考えております。
(指摘)
この説明会に寄せられた質問の回答は終わることを知りません。それほどまでに多くの質問が寄せられて、道からはごく一部の回答に留まり、残された回答が公開されることによって、その検証は今後深められることと考えています。
また、寄せられた多くの質問主旨に噛み合わない紋切り型の回答を重ねる姿は、丁寧な対応と言えるはずがないのであります。
道が今後向き合わなければならない事態は困難の連続であることが想定されます。この点については、道と民間双方からの今後の報告を待ちたいと思います。

(六)解体工事費の報道について
令和4年度の予算の取り扱いについて伺います。この質問については予定していたものではなかったのですが、今月17日の報道を受けて避けられないものと考え、加えて質問をします。
私が、北海道百年記念塔の解体予算について説明を求めると、知事査定前であることを理由に断られ、今回の質問に引用しようと詳細を求めても、今回の委員会には報告であることを理由に委員会資料の数値を引用することを断られている始末であります。しかし、
17日の報道によるリークによって、それらの前提が踏みにじられたと受け止めております。どの部署がリークしたのかについては言及を避けますが、この所業は議会軽視でしかなく、道側と報道側に強く自制を求めるものであります。さらに、先程の報告によると、その一部の予算計上でしかなく、その意図を深読みせざるを得ないと不信感を抱いてしまっております。
環境生活部長に伺います。情報管理とルールの厳格化を庁内及び報道に徹底してください。必要に応じた厳格な対応を求めます。見解を伺います。
(環境生活部長)
記念塔に関する報道についてでございますが、この度の報道につきましては、道が報道機関に対しまして、令和4年度予算案の資料を配布する時点より前に掲載されたものでございまして、報道機関がどのような方法で情報を入手したかは承知していないところでございます。
いずれにいたしましても、道といたしましては、道民の皆様のご理解を得ながら道政を進めていくためには、必要な情報を適時適切にお伝えすることが重要であるとともに、政策形成過程における情報がされることにより、道民の皆様の誤解や混乱につながることは回避すべきであると考えておりまして、道議会における丁寧なご議論をいただくためにも、職員が、改めて、その重要性を十分認識するとともに、業務に関する厳格な情報管理の徹底に努めてまいる考えでございます。
(指摘)
環生部長のお立場でどこまでご答弁を頂けるものかと案じたわけでありますけれども、庁内はもちろんのこと、その良きパートナーとしてあるはずの報道との関係については、お互いの信頼がなければ成り立たないということを前提にすると、このルールが厳格に保たれるということが必要になる。先んじてというか、アクセルをふかして報道体制をとるというのも理解できないことではありませんけども、そこには道民に対する正確な情報の提供というのも同時に必要となりますので、その裏というか深い意味のところもきちんと理解した上での報道体制というものを要求していただきたいと要望しておきます。
(指摘)
最後に指摘を加えます。この度の3度にわたる説明会に対応された職員の皆さんには、勝手ながら慰労の意を表したいと考えております。津波のように寄せられる質問や罵詈雑言に対し、制限された問答の範囲の中で、職員の皆さんが精一杯に対応されたものと伺うことができるのであります。さらには諸計画の中から使える文言が限られる中で、それでも精一杯対応しようとしていた姿は、その説明会で、パソコンの反対側、私の方からも感じることができました。しかし、残念ながら道民の立場からは、それを「丁寧な対応」と受け取ることは出来ないのです。
北海道百年記念塔が持つ開拓精神溢れる先人への感謝と未来に向けた私たちの決意は、解体という一択の方針で邁進する道に対して、厳しい態度で向き合うだけのエネルギーをもたらしています。
道は、この件について、本当の意味での丁寧な対応を果たさなければなりません。議会に、道民に対して公開しきれなかった情報を含めて、示し直さなければならないと考えています。一事不再理というレベルではありません。都合の悪い情報を隠蔽して議会や道民にミスリードをしてきた現実を自戒する必要があります。しかし、これにはトップである鈴木知事の決断が必要となります。必要とあらばこの決断をした前知事に伺う必要もあるのかもしれません。その責務を職員の皆さんが背負う必要はないと考えております。
私は、今一度道民による事実の検証を行うことが欠かせず、それでも解体やむ無しと結論付けたならば、それを受け入れる覚悟であります。だからこそ、道には丁寧な対応を求めているのであります。本件が法廷の場に持ち込まれたり、不幸な住民運動に発展することを望んではいません。くれぐれもよろしくお願いいたします。
この質問は、第四回定例会前日委員会に引き続き行った質問になります。
実施設計が完了し、年明けに解体予算が計上され、令和4年第二回定例会で解体工事発注が議会承認されるスケジュールが見込まれています。
今のところ、私たちに残された時間は「ほぼ半年」ということになります。
更に検討を重ねていく為にも、出来得ることを戦略的に練り上げて行動していくことが必要となります。
ご地元の皆さんと連携することも必要です。
引き続き深堀しながら活動して参ります。
——————————————–
一 北海道百年記念塔について
言うまでもなく北海道百年記念塔は、昭和43年11月に北海道開道百年を記念して着工されております。それは、昭和46年4月から一般公開され、道内に限らず国内外からの来訪者に親しまれてきました北海道のシンボルとなっています。特筆すべきは、当時の先人によって、特定人物の顕彰に限定せず開拓の先人に対し感謝と慰霊のまことを捧げるためや、将来に向かってたくましい北海道の建設を誓う総意を込めた記念塔という思いが込められていることであります。この他、塔の根元にアイヌと和人の全ての先人への慰霊と感謝を込めたアイヌ文様を壁面に施した石積みのモニュメントを設置する案も存在したと聞きますが、予算不足を理由に実現しなかったとされております。時は流れ、平成29年11月には、百年記念施設の継承と活用に関する考え方が取りまとめられ、平成30年12月に『ほっかいどう歴史・文化・自然「体感」交流空間構想』が決定されるまで、様々に検討が重ねられてきたことは周知の事実であります。しかし、その後も「北海道百年記念塔」の存続に対しては、賛成と反対の双方の立場から市民運動が展開されていることは、皆さんもご存じのことかと思われます。そのような中で先日の環境生活委員会で、解体に向けた実施設計が取りまとめられたことを受けて報告がなされたところです。これらを受けて以下数点質問をさせていただきます。

(一)道の立場について
先人の思いを込めて建設された「北海道百年記念塔」を解体することについて、道の立場をお示しください。特に、解体が決定された以降に賛否が道民から示されていますが、検討を重ねてきた道として、この動きにどのように影響を受けているのか、応えているのかについても言及していただきたいと思います。
(文化振興課長)
記念塔のあり方についてでございますが、記念塔は、先人に対する感謝と躍進北海道のシンボルといたしまして、これまで約50年間にわたり、道民の皆さまに親しまれてきたところでございますが、老朽化の進行によりまして、錆片の落下等が確認されましたことから、道では、専門家の方々の知見も伺いながら、その保存・活用の可能性も含め、様々な観点から検討を重ねてきた結果、塔の構造上、今後の老朽化の進行を完全に防ぐことは難しく、公園を利用される方々の安全確保や将来世代への負担軽減の観点から、解体もやむを得ないとの判断に至ったところでございます。
また、塔の存続を求める団体の方々から、署名や質問状の提出があるなど、塔の解体に関しまして、地元住民の方々の思いや様々な意見があることは承知しており、道といたしましては、質問状への回答などにおきまして、その都度、丁寧に対応させていただくとともに、報道機関やこうした団体の方々に、塔の現状をご覧いただいたほか、地元町内会や記念塔を校歌・校章に用いている学校に直接お伺いをし、改めて、「交流空間構想」でお示しした内容について説明するなど、道の考え方をご理解いただけるよう、できる限り丁寧な対応に努めてきたところでございまして、今後とも、様々なご意見に対しまして、丁寧に対応してまいる考えでございます。
(二)維持管理について
道は、前回の委員会で現時点での解体する場合の概算の工事費とあわせて、維持管理させていく場合の試算も公開をしています。
維持管理については、これまでの46年間に掛けてきた約9億円に対して、今後50年間に30億円程度と想定しています。「これまで」と「これから」の対比の金額差が余りに大き過ぎます。過去にも大規模修繕は行われていて、単純にコストを解体の理由とするには片手落ちです。解体の決め手とされた修繕しきれなくなったとする排水対策を中心とした理由を、今後50年の維持管理費にどのように見積もったのかの詳細を教えてください。一体、今後の維持管理について、どのような内容で想定された見積もりとなっているのでしょうか。行政にありがちな過剰なものとはなっていませんか。それは過不足のないものであると判断できるものなのでしょうか。それを誰が判断できるものなのでしょうか。見解を伺います。
(文化振興課長)
維持管理費についてでございますが、道では、実施設計の結果を公表するにあたりまして、「交流空間構想」の中で明記しておりました、今後50年間の維持管理費につきましても、別途、設計・施工の専門業者に調査を委託し、その結果につきまして、あわせてお示ししたところでございます。この調査を受託しました株式会社ドーコンにおきましては、塔の施工者である伊藤組土建株式会社と合同で、検討委員会を設置し、専門的な知見に基づき調査が実施されたものと認識しているところでございます。
今後50年間の維持管理費の内訳といたしましては、早期に措置すべき経費、5年又は10年サイクルで経常的に措置すべき経費、塔の外部及び内部の大規模修繕に要する経費、エレベーターの修繕に要する経費となっておりまして、このうち、委員ご指摘の排水対策につきましては、外板接合部の錆遅延措置として、塔外部の大規模修繕の中で、目地の塗装・補強工事を行うこととしているものと認識をしているところでございます。
(指摘)
今、答弁いただいたところではありますが、指摘を加えておきます。道は実施設計会社と当時の建設会社が検討委員会を設置して調査を実施させた内容を根拠としております。この委員会が官と認識できるものなのか、民と認識できるのか、今は不明ではありますが、行政にありがちな過剰な見積もりであるのかを判断する必要があると考えます。そもそも基準が異なっているのではないかと考えているからです。検討委員会に求めた内容と存続を希望する皆さんが求める内容の比較が必要であると考えられます。道が将来世代に負担を残さないとする解体の根拠の大きな一つについて根拠が定かとはなっていません。一方で存続させるとしても誰が存続させるのか、あと何年存続させるのか、最後に誰が解体をさせるのか、そのときの解体費用は誰が用意するのかなど、存続させるとしても明確にしておかなければならない課題は山積しています。それらは簡単に判断できるものではありません。むしろこれらを将来世代に残すことの方が無責任だと思うのであります。道は与えられる限りの中で、残される時間の限りに賛否両論に向き合う必要があるのです。解体の結論ありきのこれまでの対応は決して褒められたものではありません。道が示してきた維持管理の年数設定と維持管理メニューについては、しかるべき検討の上で基準を公開して再検討を求めることになります。ご承知おき願います。

(三)建物解体費増額の理由と見通しについて
解体費については、平成29年調査時には4.4億円、今回の実施設計時には7.2億円と想定されています。1.64倍です。主な増加理由として解体方法の変更や各撤去数量の増加等が挙げられておりました。
この解体費の設定は、解体費を比較されることでコストが対比されていて、より多額の費用が必要であるからこそ解体が妥当とされてきた向きが感じられます。であるならば、解体費の増額は、維持管理費との差を縮めることに直結し、コスト効果による有利性は減少してしまいます。まして、維持管理費の幅を50年間としていることから、コスト対比として適切であるのかに疑義が残ります。道は、この度の増額の理由についてどう捉えているのか、また、今後の資材や人件費高騰などの影響から、どの程度の更なる解体費の増額を見込んでいるものなのか、見解を伺います。
(文化振興課長)
解体工事費についてでございますが、平成29年の調査におきましては、塔の内側に作業用の足場を設置し、解体を進めることとしていたところでございますが、工事に伴う落下物による被害を防止するため、作業工程を細分化するとともに、塔の内側に加えて、外側にも足場を設置して解体を進めることとしたことや、公園を利用される方々の利便性を勘案し、工事用道路の位置を変更したこと、さらには、平成29年以降、労務・資材単価が上昇していることなどによりまして、解体工事費が増加したところでございます。
現在、予算計上に向けて、更なる経費の圧縮を図るべく、外構工事の見直しなど、工事内容や金額の精査を行っており、現時点におきまして、更なる増額は見込んでいないものの、引き続き、社会情勢の変化などを注視してまいる考えでございます。
(四)存続の方法について
一方では、存続させるにもあまりに多くの課題を抱えることは、さきほども申し上げたように明白です。さきほど伺った、修繕しきれなくなったとする排水対策をはじめとして、形あるものはいつか朽ちるという自然の摂理とも言うべき、さきほどの繰り返しになるけれども、一体、いつまで存続させる考えなのかなどの存続前提の立場での検討が十分ではなかったと思うのです。存続させるにしても、手法は維持管理だけではないはずだと思います。
道は、存続を訴える団体や道民の方々から「存続させよ」との要望を聴くに留まることなく、具体的な存続計画を伺うなど、丁寧に対応し、解体した場合と対比した上で疑問を解消していく必要があると考えています。道として、解体前提で議論を進めてきたならば、冒頭に申し上げた、開拓の先人に対し感謝と慰霊のまことを捧げるためや将来に向かってたくましい北海道の建設を誓う道民の総意を込めた記念塔、という思いを完全に踏みにじるものでしかないということになります。道が想定した今後50年間の維持管理とは別の方法があって良いと考えているのですが、道の見解を伺います。
(文化局長)
これまでの検討などについてでございますが、道では、塔のあり方の検討にあたりまして、道民ワークショップの開催や専門家の方々からの意見聴取、アンケート調査の実施、さらには、パブリックコメントなどを通じまして、道民の皆様からご意見を伺う中で、塔の危険要因を取り除く提案など、様々な考え方があったことから、塔を保存・活用する可能性について、専門家の方々の知見も伺いながら、「交流空間構想」でお示しをした「展望室への立入を可能とする場合」や「モニュメントとして維持する場合」に加え、「外壁の素材を変更する方法」や「低層部のみ保存する方法」、「自然に朽ち果てるのに委ねる方法」などにつきましても検討したところでございます。
最終的に、塔の構造上、老朽化の進行を完全に防ぐことは難しく、公園を利用される方々の安全確保などの観点から、解体もやむを得ないとの判断に至り、こうした道民の皆様から寄せられたご意見や検討経過も含めて、「交流空間構想」の案を議会にご報告を申し上げ、多くのご議論をいただいたところでございます。
道といたしましては、塔の解体に関して、地元住民の皆様の思いや建築の専門家の方々の考えなど、様々なご意見があることは承知をしており、解体の判断に至った道の考え方や北海道の歴史・文化と今日の北海道を築き上げてきた幾多の先人の思いを引き継ぎ、お互いの多様性を認め合う共生の立場で、未来志向に立った将来の北海道を象徴する役割を担う新たなモニュメントを整備することにつきまして、今後、地元を含め道民の皆様に説明をさせていただく考えでございます。

(再質問)
ちょっと角度を変えて質問をしたいと思います。日本国内を始め世界には塔とされるものが様々ある訳でありますが、鉄骨もしくはその鉄骨に類するもので現存された建築物が、50年も保てないというものに対して、道としてどう考えているのか、どう自己評価をされているのかを伺いたいと思います。
例えば、国内であれば東京タワー、1958年ですね、もう63年経っております。スカイツリーができてもなお解体の話などは出てまいりません。通天閣、これも地域の象徴として親しまれている塔でありますが、
1956年、これも65年が経過しております。世界に目を向ければ、エッフェル塔などは1889年ですから、132年経過している訳であります。これに対して百年記念塔は、50年というところを一つの節目として解体の検討に入った。これはですね、言い過ぎなのかもしれませんが、管理者の過失も問われて当たり前というような状況なのではないでしょうか。
さきほども申し上げました、自己評価をどのようにされているのかをまずお聞かせください。
(文化局長)
道といたしましては、これまで維持管理計画を策定いたしまして、その中で適切に管理を行ってまいりましたが、雨水が浸入し、溜まりやすく、水分に触れたままで乾燥する機会の少ない箇所において、錆や腐食が進行するなど、錆片の落下等を招いているものとされているところでございまして、そういった現況がありますけれども、道としては、これまでも管理計画に基づいて実施をしてきた、というところでございます。
(再々質問)
それは違いますね。私が申し上げているのは、国内もしくは世界に様々に塔がある中で、それぞれ適切に維持管理をしてきた立場の中で、そのように親しまれてきた。一方で、今おっしゃった理由は、言うなれば適切に管理をしてこなかったとの説明をされていることであって、自己評価を伺った訳ですから、至ってなかったと、認めていただくしかないと思います。
結果として、今答弁していただいた事象が存在することは承知しています。それを違うと言うつもりはありません。しかし、それを50年間招いてきた道は、管理者として問われるべき問題を見過ごして、スルーしてこの議論を進めていく訳にはいかないと思う訳ですがいかがでしょうか。
(文化局長)
専門家の方々の知見を伺いながら維持管理計画を策定し、それに基づき、繰り返しになりますけれども、管理を行ってきたということでございまして、そういった中で、さきほども申し上げましたが、雨水の浸入ですとか、そういった要素で錆等が進行している、というような状況でございます。
(再々々質問)
まあ、なかなかこの場でお認めになれないという状況なんだろうと想定いたします。お伝えしたいのは、何もこの場で道の責任を明らかにして、解体を阻止しようなどという、そんな浅はかなことを考えているのではなくて、寄せられた意見に対して、解体を決定し、様々な構想を整えながら、進んできたものに対して、それでもなお、クラウドファンディングを募りながら道民への意見広告であるとか、大きな動きが存在するものに対し、道が目をそらして進めることは許されない、はばかれると考える立場から、この点に関して、ちゃんと道として、さきほど一問目でも答弁されたところではあるけれども、丁寧に対応すると言っている以上、丁寧に対応しないことは今後許されないことということを明確にしておきたいと思うのですが、いかがですか。
(環境生活部長)
塔の存続に関するご意見などにつきましてでございますけれども、道といたしましては、さきほどもご説明させていただいておりますが、様々なご意見をいただいております。その中で私どもといたしまして、その回答などにつきましては、その都度回答させていただいているつもりでございますが、今後におきましても、様々なご意見があると思いますので、そういった思いに関しましては、丁寧に対応させていただきたいという考えでございます。
部長にまでご答弁をいただきましたので、もう、それを信用するしかありません。くれぐれも宜しくお願いします。

(五)更なる検討の必要性について
先ほど伺った存続方法の聴取や検討を含めた賛否双方の主張を慎重に検討するためには時間が必要となります。道は、存続を希望する方々だけではなく、解体推進を希望する方々の考え方も把握する必要があると思います。私は、個人的に存続を希望する立場ではありますが、極めて間違った認識の中で、当時の記念塔に思いを馳せた先達を愚弄することは絶対に許すことが出来ません。今後も何度でも繰り返しますが、今を生きる私たちは、お爺ちゃんやお婆ちゃん、父さんや母さん、開拓に関わられてこられた全てのご先祖様の労苦によって、このような文化的で衛生的な暮らしを営むことができていることを忘れてはならないのではあります。それを子孫に繋ぐ責務があると考えます。それが150年以上にわたる北海道の開拓の歴史なのであります。それを否定することを理由として、北海道百年記念塔を解体させることは出来ません。今一度、存続や解体、その他の方法も含めて検討する時間を確保したいと考えているところであります。
ならばどのような方法が考えられるのか、存続させるにしても感情で無計画に委ねることも無責任過ぎると考えております。解体させるにしても、これまで述べてきたような先達の思いを何らかのモニュメントで代替出来る訳もなく、その大志を継承しつつ、決して捻じ曲げられた誤認によって解体を容認することは出来ません。その何らかに込める思いは、先達の大志と共に、北海道の未来人に正しく伝わらなくてはなりません。
道には、第三の道を探る選択肢を含めた謙虚に慎重に検討する時間を確保する必要があると考えておりますが、見解を伺います。
(環境生活部長)
記念塔に関する今後の対応についてでございますが、道におきましては、保存・活用の可能性も含めまして、様々な観点から検討するために、専門家や有識者の方々の知見を伺ってきたところでございますが、その構造上、今後の老朽化の進行を完全に防いでいくことは難しく、平成29年のあり方検討以降、塔の老朽化の状況などにつきまして、広くお示しするとともに、道議会でのご議論も踏まえまして、慎重に検討を重ねてきた結果、公園利用の方々の安全確保或いは将来世代の負担軽減の観点から、解体もやむを得ないとの判断に至ったところでございます。
道としましては、記念塔の解体に関する道民の皆様のご意見を真摯に受け止めつつ、解体の判断に至ったこうした考え方ですとか、周辺広場の活用の方向性などにつきまして、地元の方々をはじめ、道民の皆様への説明の場を設けるなどして、道の考え方をご理解いただけるよう努めるとともに、公園を利用する方々の安全確保が何より重要との考えの下、塔の老朽化の状況はもとより、現在精査を進めている解体経費の内容、さらには先人の方々の思いを継承する手法などにつきまして、様々な要素を総合的に勘案しまして、適切に対応していく考えでございます。
(再質問)
質問を重ねます。今回、道と意見交換をする中で、どうしてもお互い歩み寄れなかった点があります。それは、寄せられる意見に向き合う姿勢であります。これまで質問してきたことで明らかのように、道が安全性や各予算の根拠について揺らいできたことは明らかなことでありますし、加えて道民から寄せられている賛否に対して決して丁寧に対応してきたとは言えないと受け止めております。それは、先ほどもありましたが今後行うとしている説明会で道の考え方を理解していただく場としてしか位置付けていない答弁から明らかであります。道民に対して責任を果たす覚悟は道にないのでしょうか。道は、なぜそれほどまでに解体にこだわるのでしょうか。解体しなければならない理由が先ほど挙げたような老朽化なり、安心安全以外に何かあるんではないでしょうか。それは何なんでしょうか。見解をお聞かせください。
(文化局長)
記念塔に関する今後の対応などに関する重ねてのご質問でございますけれども、塔の周辺広場の活用の方向性につきましても、今後設けることとしております説明の場におきまして、地元住民の皆様はもとより、他の地域の皆様にも、時間を確保しながら丁寧に説明をさせていただくことになりますけれども、道の説明に関して、参加者の方々から発言があった場合には、その発言を真摯に受け止めてまいりたいと考えております。
(再々質問)
これは意見交換の中でも言いましたが、説明会というものは決して道のアリバイ作りの場であってはならないと思うのであります。道の考え方を説明する場ではなくて、寄せられる意見に対して道が向き合うかというのが大切なのであって、これまでそれをしてこなかったものに対して今後進んでいくスケジュールの中で行う説明会でそれが果たせることを約束してほしいわけです。今の質問の冒頭でも申し上げました。道側との意見交換をするの中でどうしてもお互い歩み寄れなかった点がそこです。道のこれまでの考え方を説明する場というのはいわばもう不要です。寄せられた意見に対して向き合う場として説明会を設けていただけるならば、大歓迎でありますし、今までの質問の中で重ねてきた、例えば解体費用の今後の上昇というか、様々な理由に対して増加される見込みのあるものについてどうしていくのか。更には維持管理のコストがどうして50年なのか。50年である必要はないわけでありますから、その金額差について、差が無くなっていくときにどうするのか。一方、存続するにしても先ほど申し上げたような、どのくらい残すのか。形あるものはいつか壊れるわけでありますから、誰が解体するのか。様々にその疑問が残っている中で、しっかりと道として向き合うということを申し上げているわけでありますから、この趣旨においてちゃんと説明会を実施していただけるという約束をいただきたいのですが、いかがでしょうか。
(環境生活部長)
記念塔に関します今後の対応についてでございますけれども、この度の実施設計の内容ですとか、周辺広場の活用の方向性などにつきましては、今後設けることとしております説明の場におきまして、道民の皆様に丁寧に説明させていただく考えであります。その際、参加者の方々から発言があった場合には真摯に受け止めながら、「交流空間構想」の推進に取り組んでまいる考えでございます。
(再々々質問)
今部長から答弁をいただいた内容を素直にそのまま受け取ると、道の考え方を説明する説明会だという説明です。もし意見が寄せられたら丁寧に対応する、その丁寧に対応する部分が私が先ほど言った寄せられた意見に対してしっかりと向き合っていくいう意味合いなのかどうかの確認をさせてください。
(環境生活部長)
記念塔に関する様々なご意見に関してでございますけれども、道といたしましては、これまでも様々に寄せていただいておりますご意見に関しまして真摯に対応してきたつもりでございます。今後におきましても、そういった対応で向き合ってまいりたいと考えております。
(再々々々質問)
水掛け論ぽくなってくるのでどこかで区切りを付けなければなりませんけれども、これまで対応してきたものにも問題があると先ほどから申し上げておりますので、そのように対応していくというのは、いわば拒否にしか受け取れない。要するに残された時間の中でもそれらの意見に向き合うことすら拒否する道の態度は問題だと思いますけれども、完全にこれはここで決着を付けておかなければならないといいますか、行われるはずの説明会、若しくはそれまでに寄せられるものに対して向き合う覚悟を求めているわけでありますから、重ねてその点に関して要望しますがいかがでしょうか。
(環境生活部長)
記念塔に関します様々なご意見に対する対応についてでございますけれども、繰り返しの答弁で大変恐縮でございますが、私どもといたしましては、これまで寄せていただいております様々なご意見に対しまして、可能な限り丁寧に対応してきたつもりでございます。引き続き、そうした対応をとっていきたいと考えてございます。
(指摘)
これまでもお話ししてきたように、中々合意を得られないというか、担保がとれない質問と答弁になっているものと受け止めております。この局面における百年記念塔の安心・安全が解体の免罪符になるわけもありませんし、道が示してきた根拠が一つ一つ別の考え方に移っていく中で、どう捉えるのかというのが、色んな潮目だとか、我が自民党の会派も含めて、今後様々な動きがでてくるであろう中においては、これは未来のことで断言はしませんけれども、道の皆さんにも、しっかりとそれに向き合っていただきたい。道の皆さんから寄せられる様々な意見、議会の中の議論も含めて、道がこれまでとってきたものの、継続が解体につながるということは絶対に避けなければならないと考えているものであります。
皆さんは先日、机上配布された文書をご覧になられたでしょうか。あえて特定はしませんけれども。私に言わせれば、誤認著しく、恩讐の先にある解体は未来に禍根を残すものになってはいけないと考えているし、それを主張される方々にも言い分はあると思うのです。しかし、道は、それを代弁する必要はありません。あくまでの第三者であるべきです。過去の否定に加担する必要はないと考えております。私は、多様性とは、他方の否定からでは何も始まらないと信じていますし、共生とは、否定からでは何も生まれないと信じております。
今後、第二回定例会あたりに、解体発注への決裁等が行われてくることになると思いますけれども、少なくともその間にも議論を進めていかなければならないと考えておりますし、必要によってはそれ以上の時間をかけてでも補完をしていかなければならない課題であると私は考えています。必要なことは、排除ではありません。共生であるべきです。一方を否定する選択は、北海道と未来人に残すべき文化ではないと考えております。
この質問については、地元の方々と連合しながら継続していきます。地元の方々の意思に反したものにする考えはございません。時に知事にも直接答弁をしていただく機会を得なければならないと考えていますので、よろしくお願いいたします。
この質問は、先日配布された資料(下部に添付)を基にして行いました。
「開拓記念塔」の実施設計が完了したことをにより、来年上程される解体予算の根拠となるものです。
今後も慎重に議論を重ねていくためには、更なる時間が必要だと考えるに至りました。
以下に、11月29日に開催された環境生活委員会での質問と答弁内容を公開させていだきます。
北海道百年記念塔の解体工事に係る実施設計の結果について
(一)これまでの対応について
解体をめぐっては、様々な議論が続いていることは承知しております。
それは、先の一般質問等でも取り上げられていることであります。
そこで、今回の結果の報告があったことを受けて、数点質問をさせていただこうと思います。
まず、最初に、道として解体の方針を打ち出し、準備を進めてきたところでありますが、この間寄せられた道内外からのご意見等にどのようなものがあり、それを道がどのように捉えているのか、教えてください。
<答弁>(文化局長)
記念塔の存続活動をされている団体の方々からは、これまでも存続を求める署名や質問状の提出がありまして、道では、質問状が提出される都度、交流空間構想でお示しした考え方をご理解いただけるよう、公園を利用される方々の安全確保や将来世帯への負担軽減などの観点から解体もやむを得ないと判断したことなどにつきまして、繰り返し回答をさせていただくとともに、昨年6月には、設計者の井口氏も参加いただきまして、普段立入ができない、記念塔内部の現状をご覧いただいたところでございます。
こうした中、本年6月に存続を願うプロジェクトが、意見広告を出すためのクラウドファンディングを行い、10月にその意見広告が掲載されるといった活動があったことを把握しているところでございます。
道といたしましては、記念塔の解体に関して、地元住民の皆様の思いや、建築の専門家の方々の考え方など、様々なご意見があることは承知しており、今後とも、様様な機会を通じまして、道の考え方についてご理解いただけるよう、努めてまいる考えでございます。
(二)解体工事費の増加への対応について
今回の結果によると、解体費用に関しては、予算ベースで1.64倍、それは今後さらに増えると考えるのが自然なのだと思います。
解体と維持の差が縮まるばかりと捉えるわけですが、これは道が主張してきたコスト面での根拠が弱まっていくことに繋がってしまうのだと思います。
これは金額のみではなく効果も同様だと考えます。
また、なぜ対比が50年という尺なのか、そこに私は様々に考えを巡らせてしまうわけです。
この費用増に対して、どう捉えていくのか、どこまでの増額を許容していくものなのか、考え方を教えてください。
<答弁>(文化局長)
工事費に関してでございますけれども、道では、今回の実施設計の結果を基に、今後、工事内容及び金額を精査することとしているところでございます。
道といたしましては、地元住民を含め、道民の方々に今後とも、公園を安全かつ安心してご利用いただくためには、利用者の安全確保が何よりも重要であり、記念塔の老朽化の状況や工事内容の精査、更には先人の思いを継承いたします未来志向のモニュメントの設置など、様様な要素を総合的に勘案し、対応してまいる考えでございます。
急な質問の通告にも関わらずお受けいただきましたことについて感謝を申し上げたいと思うのですが、いずれにしても、なぜ、例えば維持が行政でなければいけないのか、今後、今日の質問をさせていただいた内容を含めて、改めて終日委員会で議論させていただこうと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
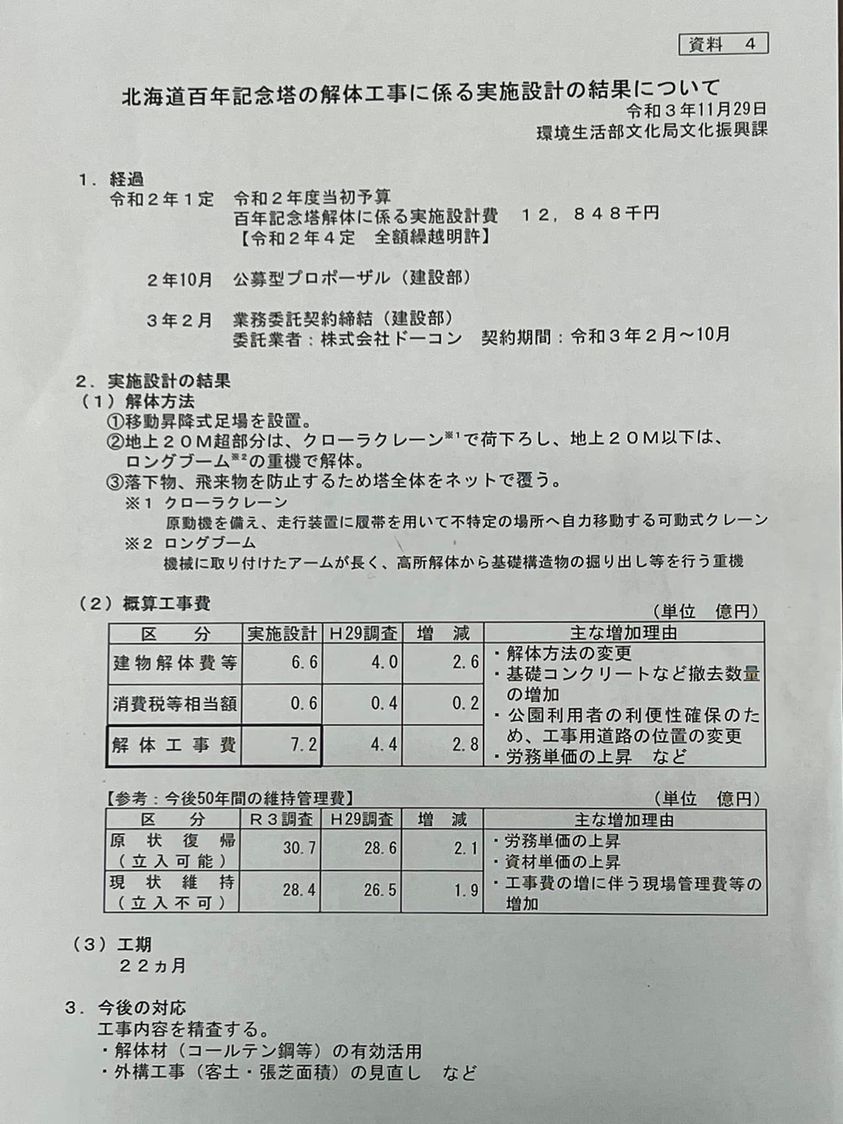
【エゾシカの捕獲について】
エゾシカの捕獲について、以下数点質問させていただきます。
言うまでもなく、北海道内におけるエゾシカ生体数の管理は、共存共生への第一歩となります。
直近の調査によると、道内には、67万頭生息しているとされていて、東部に32万頭、西部に35万頭、それとは別枠で南部に3~15万頭と推定されています。
交付金の対象となる捕獲については、農水省や環境省等の交付金を活用して市町村単位で取り扱われていますが、実質地元の猟友会次第となっていて、部外者にとって極めてハードルが高いものとなっています。越境を含めた区域外からの参画は実質困難となっています。
しかし、それは捕獲が許可されている道内における有資格者の高齢化や猟友会自体の会員数の減少などが大きく影響していて、ニーズとの乖離は大きいものと承知しています。

①捕獲関連交付金について
最初に、エゾシカの計画的な捕獲に対する交付金の状況を伺います。
<答弁>
エゾシカの捕獲に関する交付金の状況についてでございますが、捕獲関連の交付金の総額は、令和元年度から前年度比で増加しておりまして、令和2年度は、農林水産省の鳥獣被害防止総合対策交付金事業で、約7万7千頭捕獲し、約5億4千4百万円、環境省の指定管理鳥獣等捕獲事業などで、835頭捕獲し、約6千4百万円、また、道の地域づくり総合交付金事業では、交付金額は約4千8百万円で、捕獲頭数につきましては、市町村独自の捕獲事業への支援に加え、一部国の交付金事業への上乗せ分もありますため、延べ頭数となりますが、約6万5千頭でございました。
②市町村の交付状況について
次に、道内179市町村の交付状況はどのようになっているのか伺います。
<答弁>
市町村の交付状況についてでございますが、農林水産省の鳥獣被害防止総合対策交付金事業によりますエゾシカの緊急捕獲対策に関し、令和2年度、道内の市町村の交付金の「エゾシカ管理計画」における地域別の執行状況は、東部地域では、捕獲数は約4万頭で、総額で約2億5千9百万円、西部地域では、捕獲数は約3万5千頭で、総額で約2億6千9百万円、南部地域では、捕獲数は約2千頭で、総額で約1千5百万円となっておりまして、東部及び西部地域に比べ、南部地域では、捕獲、交付金とも少ない状況にございます。

昨今では胆振や南部地域における生息数が増加の一途であることを現場で耳にしています。それは、単純に増加数と捕獲数のバランスが取れていないことが主因であると容易に想像できます。
③南部地域の実態調査について
そこで、南部地域の実態調査について伺います。
4年前にも当委員会で質問してある点ですが、南部地域における生息数は、調査方法の確立が困難であることを理由に、おおよその推定値扱いでしかありません。
その後に調査方法の確立が為されることなく、生息数の増加を許してきた現実があります。結果として、エゾシカ行政が目指す姿と実態の乖離が大きくなってきています。
これ以上の放置は許されるものではありません。
道は、南部地域における生息実態数の調査方法の確立を急ぎ、計画的な捕獲数の設定を行う必要があります。見解を伺います。
<答弁>
南部地域の捕獲目標についてでございますが、道内では、平成30年に発生いたしました狩猟死亡事故に伴う狩猟規制などの影響により、捕獲数が伸びませんでした。
捕獲目標の設定に必要となる推定生息数は、ライトセンサス調査の目撃数や捕獲数などにより算出いたしますが、エゾシカの捕獲数が伸びなかったことに伴い、推定値の精度が低くなったものと考えているところでございます。
道では、各種調査結果や捕獲実績などを踏まえて、南部地域の目標数を徐々に上げ、現在、6千頭に設定し、対策を進めておりますが、今後更に、推定生息数の精度を上げるためには、有識者の方々の御意見もいただきながら、補足調査の方法などについての検討を進める必要があると考えているところでございまして、こうしたことを踏まえ、道といたしましては、地域の実情に即した捕獲目標について、可能な限り早い時期に設定できるよう、取り組んでまいる考えです。
<指摘>
いま答弁を頂いたところですが、一点指摘を加えておきます。
実は、冒頭に述べましたが、道内に生息するエゾシカの生息総数は67万頭ではありません。別枠になっている南部地域を加えた82万頭と表現しても決して間違いではないのです。
この数のインパクトは決して少なくはなく、調査方法の確度を理由に別枠にしてきたことによって、南部地域のエゾシカの生息数の激増を見過ごしてきたことは否めません。
「可能な限り早い時期」と答弁を頂きましたが、現実はさほど待てる状況ではないことを道は知る必要があります。
早々に対策会議の関係者にこの意向をお伝えして、直近の対策会議で南部地域の総数の設定を行うことが必要です。再来年とは言わず来年の猟期開始の頃には示して頂けるように要請しておきます。

④市町村の捕獲交付金申請等について
次に、市町村の捕獲交付金申請等について伺います。
先の二番目の質問で伺った内容を基にすると、特に南部地域における市町村の取組みを三番目の質問にある実態調査を根拠として適正な捕獲を継続する必要があり、道は、該当市町村に対して国の交付金を活用しながら捕獲数を維持する為の協議助言していかなければならないと考えています。同時に市町村は、地元猟友会に限ることなく、狩猟や有害捕獲を行う有資格者の活用を広く実現させなければなりませんし、一方で、市町村は計画上の捕獲数を十分なだけ確保する必要があり、それらは、誰がどのように行うことになるのか伺います。また、道は何にどのような立場で関わっていくことになるのか明確にしてください。
<答弁>
捕獲等に関する有資格者の活用についてでございますが、鳥獣被害防止総合対策交付金に関しましては、市町村が設置する対策協議会が交付金の受け皿となり、地元ハンターを中心に体制を構築し、捕獲を実施しておりますが、外部の有資格者を参画させて、捕獲サポート体制を構築することについても同交付金の支援対象とされているところです。
市町村におきましては、エゾシカの捕獲を円滑に推進するため、地元の農業関係者や捕獲協力者の理解の基に見回りや追い払い、わな・緩衝帯設置などの役割分担について調整を行っているために、外部有資格者の活用を進める場合は、地元関係者と十分な調整を図る必要があるものと考えます。
現在、道では、全市町村に対しまして、これまでの実績を上回る目標を示し、来年度事業の捕獲目標を増やすよう、協力要請しているところでございます。
また、今後、高齢化や過疎化によりまして、地域の捕獲従事者の不足が想定されるために、振興局の鳥獣対策協議会を通じ、外部有資格者の活用も含めまして、捕獲体制の充実を図る方法を市町村に積極的に周知するとともに、南部地域など被害の拡大が懸念される地域におけるエゾシカ対策の着実な推進に取り組んでまいる考えです。
<指摘>
ここでも指摘を加えます。先ほどもお話ししましたが、南部地域の生息数の激増を鑑みると、南部地域における市町村の有害捕獲数の設定が不足していることが主因であると考えられます。増加数と捕獲数のバランスが著しく取れていないのです。完全に後手にまわってしまっています。
それは、道や振興局による積極的な周知だけで解決できる課題ではないと承知しています。
エゾシカ行政の考え方が、市町村毎に異なる状況にあっては、数の相談だけに留まらない支援が必要です。今一度南部地域におけるエゾシカ行政のあり方については精査していただく必要があると考えています。この点を強く要請しておきます。
⑤エゾシカ行政の今後について
次に、エゾシカ行政の今後について伺います。
私たちは、古い過去にエゾシカを乱獲し生息数の著しい減少を招いています。その後の保護政策等を経て今に至るのですが、生息数の管理だけではなく、狩猟したり有害捕獲されたエゾシカ肉の利活用を同時に推進することができるように施策を講じなければなりません。
道のエゾシカ行政の、これまでと、今後の受け止めについて、部長の見解と抱負を伺います。
<答弁>
エゾシカ対策についてでございますが、エゾシカにつきましては、過去の保護政策に伴う生息数の増加を受けまして、市町村、関係機関との協力体制を築きながら、捕獲対策を推進した結果、平成23年度をピークに減少傾向を示しておりましたが、30年に発生した狩猟事故に伴う銃猟規制などの影響により、捕獲数が減少し、昨年度、再び上昇に転じたところでございます。
また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、エゾシカ肉の需要にも影響が生じておりますことから、捕獲と有効活用を進めることが喫緊の課題と認識しております。
道といたしましては、今後とも、市町村への的確な情報提供や助言などを行い、連携を強化し、捕獲の推進や人材の育成に努めますとともに、道内外の飲食店などにおける、安全・安心な食材としてのエゾシカ肉の消費拡大や、ペットフード、皮革製品などの幅広い分野での利用を含め、ポストコロナも視野において、認証施設数の増加や需要の拡大に向けた取組を進めるなど、捕獲と有効活用の両面からエゾシカ対策の一層の推進に取り組んでまいる考えです。

<指摘>
最後に、一点お伝えしておきます。
この質問については、一年後位に改めてお聞きしたいと考えています。
一年後にお聞きした際には、生息数や捕獲数、特に南部地域については、積極的な利活用の手応えが実感できる答弁を返して頂けるように実務にあたって頂けますようにお願いしておきます。
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
この質問は、コロナとの闘いに見通しがつかない中であっても、将来の北海道の成長を担保していく為に、道の海外事務所等の戦略・戦術を整えていかなければなせないとの想いから、鈴木直道知事に質したものです。
海外事務所に赴任している道職員や現地スタッフの仕事は、普段から道民の皆さんの目に届かぬ活動ではありますが、日々懸命に汗して働いていることを承知しています。
益々活躍して頂く為にも、今後とも最大限に応援してまいりたいと考えています。
--------------------------------------------------
【 道の海外事務所等について 】
次に、道の海外事務所等について伺います。
道は現在、海外事務所4か所を開設しているほか、職員を派遣している在外公館やジェトロ、道内金融機関の海外拠点が5か所あり、これらに9名の道職員と2名の民間派遣者、7名の現地事業スタッフを配置していると承知しています。

これらの海外事務所と駐在所を最前線として、道内経済や地域社会の活性化を図るため、「世界の中の北海道」として道が中長期的に進むべき将来の方向性を「めざす姿」として明らかにし、道内の行政、企業・団体、道民の皆様と協力・共有しながら、世界の活力を取り込んでいかなければなりません。
特に、昨年から新型コロナウィルス感染症と闘いに苦しむ私たちは、インバウンドを取り込んだ観光産業の展開の見直しを強いられ、改めて国内や道内の観光客の重要さを思い知ることになったと承知しています。
しかし、引き続き海外からの観光客の取り込みなど観光業のみならず道内産品の輸出を目論む私たちが、人口減少に伴う経済規模の縮小が避けられない北海道にとって、海外、特に人口急増に伴い経済発展を続けるアジア各国の消費力に期待を寄せることは避けることが出来ない流れであると考えています。
その最前線として活躍が期待される海外事務所と駐在所については、これまでさまざまに議論されてきたことを承知しています。
それらを踏まえた上で、以下に伺って参ります。
①道の海外事務所等の現状について
最初に、海外事務所と駐在所の現状について伺います。
世界が、新型コロナウィルス感染症と闘う今日現在、海外事務所と駐在所については、道職員や駐在所スタッフがどのように配置され、ているのか、どのような活動を行っているのか、現在の活動内容と共に予算執行状況を伺います。
<答弁>
海外事務所等の活動状況についてでありますが、海外事務所等の職員は、これまで、派遣先の国や地域の感染状況等を踏まえ、昨年2月から4月にかけて帰国し、現地の事業スタッフと連携しながら道内で活動を続け、外国人の入国禁止措置の解除後、6月から順次、駐在地に渡航し、現地での活動を再開してきたところ。
現在、海外事務所等では、感染症の拡大により、現地での移動やイベント等の開催に制約がある中、道内観光地からのライブ配信や、小売店・飲食店と連携したフェアの開催など、北海道への関心を高める事業を実施しているほか、現地バイヤーと道内企業の仲介や、渡航できない企業に代わって商談会で商品説明を行うなど、本道の魅力発信や道産品の販路開拓に取り組んでおり、事務所運営費予算は、旅費を除き概ね執行予定となっているところ。
②コロナ禍における役割について
次に、コロナ禍における役割について伺います。
昨年来、世界が闘ってきた新型コロナウィルス感染症ですが、最中にあっても、道内経済や地域社会の活性化を図るため、「世界の中の北海道」として海外事務所と駐在所が担う役割は変わっていません。むしろ、ピンチはチャンスと唱える知事にとって、このタイミングから立て直しを目論み、コロナ収束後に備えてコロナ禍における戦略を整えておく必要があると考えています。
最近の報道によると、世界ではワクチン接種が進んでいて、ウィズコロナの状況にある私たちにとってのコロナ克服は、もう目の前のことなのかもしれません。そうであってほしいとさえ願っています。
だとすると、「世界の中の北海道」として海外戦略の立て直しを、この段階で打ち出す必要に迫られていて、その最前線である道の海外事務所等の役割について、知事の見解と展望を伺います。

<答弁>
海外事務所等の役割についてでありますが、海外との経済交流の促進に向け、道では、重点とする地域に職員が駐在し、行政機関や企業との人脈形成、現地情報の収集、事業活動へのサポートといった駐在ならではの役割を果たしており、海外との往来が困難な状況にある中、その必要性は一層高まっていると認識。
現在、情報通信技術を用いたコミュニケーションが急速に普及しているといった変化も踏まえ、道としては、こうした技術を積極的に活用し、これまでは対面を前提に困難だった案件についても、人脈を提供し、言語や商慣習の違いをサポートしているところであり、これまで以上に海外事務所等が、海外と道内各地の中継点となり、新たな経済交流の促進につながるよう、取組を進めてまいる。
③コロナ収束後の施策展開について
次に、コロナ収束後の施策展開について伺います。
コロナ後といっても、新型コロナウィルス感染症の根絶は出来ないものと承知していますし、感染症との闘いが人類の歴史であるといっても過言でないことを知った私たちにとっては、海外戦略をどのように描いていくかが問われているのだと考えています。
先ほど申し上げたように、感染症の流行如何に関わらず、世界の活力を取り込まなければならない北海道にとって、海外事務所と駐在所の役割については、臨機応変に戦術を組み直さなければならない施策であると考えられます。
私は、そろそろコロナ後の海外戦略について準備を整えなければならない時期であると考えますし、その検討にあっては、コロナ以前の体制に戻すことが大切なのではなく、より積極的な展開が必要であると考えている一人であります。
世界が委縮したこの災禍に、共に縮むのではなく、世界をリードする北海道である為の政策や施策を展開することによって、世界の消費を取り込むことの出来る体制を、その最前線である海外事務所と駐在所に担っていただくことの出来る体制を敷いて頂きたいと考えています。人員のみならず予算面に至るまで強化させる必要があります。
知事には、海外事務所について、新たな目標設定と共に人員配置や予算設定を充実するなど積極的な施策展開を求めます。知事の見解を伺います。
<答弁>
海外事務所等の今後の取組についてでありますが、本道経済の発展に向けては、感染症の収束後も見据え、道産品の海外販路拡大や外国人観光客の誘致、海外からの投資受入れなどを促進し、海外の成長力を取り込むことが求められており、その最前線で活動する道の海外事務所等の役割は大変重要と考えている。
このため、道としては、輸出拡大やインバウンドの再獲得に向け、本道の食や観光などの魅力発信に加え、道産品を扱う海外ECサイトの紹介のほか、北海道に関心がある現地企業の発掘と、貿易や投資の商談の仲介など、海外事務所等の独自の施策を積極的に展開するとともに、多くの海外拠点を持つジェトロや金融機関との連携を一層強化し、現地でのノウハウやネットワークを互いに活用しながら、成長が見込まれるアジアや欧米などの国や地域において、新たな市場や需要の開拓に取り組んでまいる。
この質問は、初当選以来、北の元気玉が「新エネルギー導入の加速化」について取り組んできた成果について鈴木知事に質したものです。
①地域産業の課題を解決しながら地域内で「再生可能エネルギー燃料」を作り出す。
②地域内で発熱電を行い、作り出した電気や熱を地域内で消費する。
③地域内で消費する分には、富を囲い込める。(流出しない)
④更に、再生可能エネルギー事業の実証試験等を呼び込みやすい政策を展開し、地域内に事業を誘致する。(雇用が生まれる)
⑤伴って地域内で消費する以上の再生可能エネルギーを作り出すことが可能となり、その分は域外に売ることが可能となる。
⑥地域外に売った再生可能エネルギーは、その地域に富を呼び込むものとなる。
これらを可能にする技術が「マイクログリット」なのです。
このマイクログリッド技術を、道自らが推進させることに舵を切ることによって、系統接続が脆弱であるが故に進まなかった
新エネルギー導入の加速化を推進させることが可能となるのです。
北の元気玉は今後も積極的に取り組み、道民の皆さんに安価で安定した「再生可能エネルギー」を使った暮らしをお届けします。
--------------------------------------------------
エネルギー政策による北海道の活力の創出について
最初に、エネルギー循環型社会システムの実現が急がれる視点から、この質問をさせていただきます。
道は、昨年3月に、2050年までにゼロカーボンの実現を宣言し、更に2030年に目指す姿を具体化させています。それが、次期「省エネ・新エネ促進行動計画」の策定であります。
新エネルギー導入の加速化については、前知事の段階から取組まれてきているものであり、それらを一層推進させていく為の道程を明らかにしているものと承知しています。
私は、これまで一般質問等の機会を通じて提案してきたところでありますし、国や道が目指す姿に同意できるものではありますが、その手段としての政策・施策が不十分であることを議論させていただいて参りました。
そこで、今回は、次期「省エネ・新エネ促進行動計画」の策定が進むこのタイミングで、知事に質問させていただきます。
行動計画では、目指す姿の実現へ向けた「3つの挑戦」を明らかにしています。それぞれについて課題を明らかにし、達成へ必要な行政の取組みを加えて頂けるように要請させて頂きます。

①多様な地産地消の展開について
はじめに、多様な地産地消の展開について伺います。
エネルギーの多様性や循環型社会システムの構築を活かすためには、その地域でのマイクログリッド技術を確立することが必須です。それは、域内経済の自立と強化に直結します。
また、道内に限らず系統接続の脆弱性によって不自由を極めている事業環境を改善していく為には、系統インフラの整備も欠かせませんが、同時にマイクログリッドの実現による地産地消のエネルギー環境を整えることの方が、自然災害等による非常時電源確保の実体に即したものとなり得るのです。広範な送配電線網のデメリットを目の前に突き付けられたのが、2018年北海道胆振東部地震によるブラックアウトの経験だったのではないでしょうか。
これまでに何度も主張してきていますが、非常時電源の確保に躍起になるよりも、マイクログリッドの実現によって事業環境整備を推進することの方が、理に適っていることに議論の余地はありません。
道には、農業・観光業に続くエネルギー産業を北海道の主力産業とするために、この度の策定等において発想の転換が求められています。知事の見解を伺います。
<答弁>
マイクログリッドについてでありますが、道は、次期「省エネルギー・新エネルギー促進行動計画」において、さまざまな新エネルギー等を活用し、地域単位でエネルギーの需給を管理し、活用する、需給一体型の分散型エネルギーシステムの構築・展開を促進することとしており、構築にあたっては、災害時を含めた電力の安定的な確保とともに、これまで域外に流出していた資金を地域内で循環させ、経済の活性化につなげていくことが重要と認識。
このため、道としては、取組を進める上で課題となっている電力の制御技術の高度化や発電設備の立地手続きの迅速化などについて、国に対応を要望するほか、地域におけるマイクログリッドのモデル形成に向けて、計画づくりを支援し、その成果を全道に普及するなど、地域における多様な地産地消の取組を促進してまいる考え。
②「エネルギー基地北海道」の確立に向けた事業環境整備について
次に、「エネルギー基地北海道」の確立に向けた事業環境整備について伺います。
自然エネルギー源の賦存量が豊富な北海道では、さまざまな先進技術の取り込みと実証試験地としての体制整備、特区化を見込んだ政策展開が必要となります。
しかも、道内のいずれかに集積すれば良いものではなく、地域の特性を活かし、且つ地元産業の課題解決をセットにしながら、各所で実施されることが必要であると考えています。
これらの実現へ向けた厄介なポイントは、様々な規制や担当する知事部局が横断してしまう民間事業者にとっての不自由なのであります。特に、新エネルギー事業にとっては、経済部と農政部、水産林務部、時に環境生活部、カウンターパートとしての登場部署や人物が多過ぎます。既に、その産業界にとっては常識である法律や条例、規制や規則も、産業界を跨いだ新技術の確立のためには、障害でしかないことが多々見受けられるのです。
よって、さまざまな先進技術の取り込みと実証試験地としての体制整備、北海道の特区化を実現させることで、それらの障害を調整することができる環境が整うことになります。実証地はそれぞれであるべきですが、調整機関は集積させることが可能です。
道の役割は、調整機関と民間事業者が取組む事業の実現へ向けたバックアップなのであり、既に存在する規制の適応に腐心することではないのです。
道には、農業・観光業に続くエネルギー産業を北海道の主力産業とするために、この度の策定等において、ここにも発想の転換が求められています。知事の見解を伺います。
<答弁>
エネルギー関連プロジェクトの誘致などについてでありますが、次期「行動計画」においては、本道の豊かな新エネルギー資源を最大限活用し、道内はもとより、国に電力を供給し、地域経済の好循環に結び付けていくため、「エネルギー基地北海道」の確立に向けた取組を進めることとしている。
このため、道では、本道の特性を活かした、風力発電や水素関連などの、大規模新エネルギー開発プロジェクトや国や企業などの実証事業の誘致、受入を進め道内企業に先端技術を普及していくとともに、実証事業に必要となる制度面の課題を解消するため、国に対し、規制の緩和を提案、要望していくほか、新たに、新エネルギー導入に関するワンストップ窓口を設置し、庁内関係部局が連携して、課題や要望に対応する体制を強化してまいる考え。

③省エネ促進・新エネの開発の導入と一体となった環境関連産業の振興について
次に、省エネ促進・新エネの開発の導入と一体となった環境関連産業の振興について伺います。
言うまでもなく、広大な北海道においては、その地域や根付いている産業の特性を活かした展開を欠かすことは出来ません。更に、民間事業者のみならず、自治体や地域住民の理解と協力は、定着と継続が必要なこの取組みには不可欠なのであります。
特に新エネルギーの世界では、日進月歩で技術開発が続いていて、私たちの国や地域に提案され、採用されたとしても、製造・設置・稼働した段階では、更なる新技術が生み出されていることは日常茶飯事であるのが実態です。
道は、広大な北海道であるからこそ、積極的に世界の新技術の取り込みに挑戦し易い環境を整備して、民間事業者を支援していく必要があります。
環境関連産業の振興を実現させなければならないのであるならば、道として、民間事業者と協力しながら、新旧技術のデータベース化とその経過と結果、地域のニーズの把握を行い、マッチングや事業推進支援を行わなければならないと確信しています。
これまで、経済部では、自治体が取り組む北海道新エネルギー導入加速化基金をはじめとする施策を講じてきましたが、いずれも自治体ベースとなっていて民間事業者にとっては使い勝手が悪く、技術の進歩に追い付くことの出来ない状況となってしまっています。
道の支援とは、補助金ばかりなのではなく、部局を横断できるフレキシブルさと規制の突破なのであり、もはや道自身では気付きづらく、事業者等からの要請を受付け、解決させていくことが望まれる支援となり得るのです。
道には、このような場を提供する必要があると考えていますが、農業・観光業に続くエネルギー産業を北海道の主力産業とするために、この度の策定等において、更にここにも発想の転換が求められています。知事の見解を伺います。
<答弁>
環境関連産業の振興についてでありますが、環境関連産業は、従来の省エネルギー、新エネルギー設備に加え、地域マイクログリッドの構築に資するデジタル制御技術といった先端技術の開発などにより、今後の市場の拡大が期待される産業であり、省エネや新エネの開発・導入と、国内外からの投資や道内企業の参入などによる環境関連産業の振興を一体的に推進し、地域経済の好循環につなげていくことが重要と認識。
このため、道としては、省エネや新エネに関連する企業の投資や立地を促すほか、道総研などとも連携し、新たに、企業や自治体が抱える新エネ導入に関する課題や要望に対応するワンストップ窓口を設置し、道内各地における新エネを利用した取組の状況に加え、技術相談や支援制度などに関する情報提供を行い、事業化につなげていくとともに、環境関連事業に取り組む企業に対し、構想段階から技術開発、販路拡大まで総合的に支援するなどして、企業の皆様の声に耳を傾けながら、環境関連産業の振興に取り組んでまいる。
④目指す姿の実現によるエネルギーの主力産業化について
次に、目指す姿の実現によるエネルギーの主力産業化について伺います。
このマイクログリッドの技術の確立は、系統接続の脆弱性によって不自由を極めている北海道にとって、飛躍的な新エネルギー導入の加速を実現させることにつながります。
マイクログリッドの技術のほとんどは、該当する地域内の電流と電圧を制御する技術といっても過言ではありません。現在では、北海道電力が道内を一括して制御している状態ですが、その地域を独立させて制御することが出来るならば、道内のいずれの地域でも系統接続することが可能になると承知しております。
更に、FITによる売電は、設備資金の償却に大きく貢献する制度となっていますが、例えFIT制度を利用しなくとも、その地域で長期間にわたって売電できるマイクログリッドであれば、道内で販売される電気料金並みの価格を実現することが可能です。
まさしく地産地消であり、地域に根ざした産業との連携が可能であり、域内経済の強化に直結させることが出来る、目指す姿の実現がそこにはあるのです。
更に、売熱を組み合わせることによって、発電のみであれば投入したエネルギーの3割弱しか電気に変換することはできませんが、排熱とされていた6割程度の発熱を有効利用することで売電価格を低減させれば、循環型社会システムの完成を成し得ることが可能です。
現在、系統接続が出来ない道内のほとんどの地域では、結果として新エネルギーを発熱として利用することしか出来ない有様です。それは、あまりに非効率です。
これら北海道の系統接続の充実を待たずして推進できる技術が、マイクログリッドということだと確信しています。道こそが、率先してマイクログリッド技術の確立に舵を切るべきです。それらを確立させたうえで、エネルギーの主力産業化を実現させるべきと考えます。
道には、農業・観光業に続くエネルギー産業を北海道の主力産業とするために、この度の策定等において、またもや、ここにも発想の転換が求められています。知事の見解を伺います。

<答弁>
新エネルギーの活用に向けた技術開発等についてでありますが、マイクログリッドを含む需給一体型エネルギーシステムの構築に向けては、地域特性に応じた新エネを活用した発電や、それに伴う熱の有効利用はもとより、デジタル技術を活用して電力の需要と供給を双方向で調整するといった新たな技術の開発や、太陽光発電や蓄電池などの分散型エネルギーリソースの家庭や事業所への導入促進が必要。
このため、道総研では、木質バイオマスや温泉熱など未利用資源を活用したエネルギーの地産地消に関する技術開発や利用モデルの構築などに取り組んでいるほか、道としても、環境関連産業への参入を希望する企業の技術開発を支援するとともに、来年度新たに、家庭や事業所に向け、分散型エネルギーリソースの導入メリットを調査・PRすることとしており、地域特性に応じた需給一体型エネルギーシステムの構築と展開を促進してまいる。
⑤国内の地域新電力の取組みについて
最後に、国内の地域新電力の取組みについて伺います。
マイクログリッド技術による国内における地域新電力の取組みについては、地方自治体が主体となった地域PPSは現在30ヶ所程度が立ち上がっていて、検討されている自治体に至っては86ヶ所であると報じられています。国の意向を踏まえると、全国で100ヶ所程の地域PPS事業が立ち上がる見込みと承知しています。
この地域PPSは、新エネルギーの導入を加速化させるばかりか、電気料金等として地域外に流出している富の一部を地域内に留めるためのダム機能となるべく設立され、得られる利益相当分は、地域振興は基より、人口減少対策など公益的な事業に還元させていくことが可能です。官と民の中間のポジションを取りながら、その時々に合った地域課題に柔軟且つ民間ならではのスピード感をもった取組みを推進させていくことが出来るとされています。
これらは既に確立されている技術であり、自然エネルギー源の宝庫であることを謳ってきた私たち北海道にとっては、これまで実現できていないことが滑稽にさえ映る有り様だと考えています。
道は、地域の新エネルギーを集約して、まずは地域に提供し消費できるようにし、消費以上に生産された新エネルギーを域外にもたらすことによって「富」を獲得する取り組みを、知事と道が先頭に立って、導入し易い環境を整えていく必要があると考えています。
知事。私たちは、既に待ったなしの状態に突入している人口減少や、コロナ禍で痛み尽くしている地域経済の立て直しの為に、即効性の高い政策と施策を次々に投じていかなければならないのです。
次期「省エネ・新エネ促進行動計画」の策定によって目指す姿を示すことも必要ではありますが、これまで質問してきたように、概念的な構想に留まるステップは、とうに過ぎているのではありませんか。
次期「省エネ・新エネ促進行動計画」の策定と同時に、既に全国で散見されている具体な事例を積極的に取り込み、賦存する自然エネルギー源を最大限に活用した北海道ならではの新エネルギー事業の振興と、それに地域PPSを組み合わせての推進が欠かせないのです。
私たちは、エネルギー政策による北海道の活力の創出を実現させなければならないのです。 知事の決断を求めます。見解を伺います。
<答弁>
地域における新エネルギーの活用についてでありますが、道では、新エネ導入加速化基金などを活用し、市町村が実施するエネルギー地産地消の先駆的なモデルとなる取組への支援に取り組んでいるところ。
このうち稚内市や上士幌町では、地域新電力会社を設立し、地域資源を活用した電力を地域内に供給することで、雇用創出などを図る取組が進められている。
道としては、引き続き、こうしたエネルギー地産地消の先駆的なモデルとなる取組を支援するほか、取組から得られるノウハウのコーディネーター派遣による普及などを通じて、他の地域での課題解決につなげるとともに、来年度新たに、関係部局が連携しながら、地域が主体となって取り組む新エネ導入の掘り起こしを行うなどして、エネルギーの地産地消の取組を全道に広げ、地域経済の好循環を実現してまいる。
脱炭素社会の実現に向けては、どうしてもパラダイムシフトを変えていく必要があると考えています。言い換えるならば、既得権益にどのように横串しを刺して組み替えていくかであって、それこそが行政の役割なのであり、それが何であるのか、何を求められているのか、推進する上での不自由さを明らかにし解決していくことが重要なポイントとなるに違いありません。しかも、それらの場の提供にコストが掛かるものではないのです。
しかし、その働き掛けは、残念ながら既得権者側からは出てくることはありません。
これは、ゼロカーボン宣言を果たした鈴木知事だからこそ取り組むことの出来る政策であるに違いありません。
このエネルギーの主力産業化は、北海道にとっても、その地域にとっても決して避けることの出来ない人口減少に立ち向かう大きな原動力となり得ます。
広域でありながら系統連系が脆弱な北海道だからこそ、日進月歩で進む発熱電技術開発に遅れを取ることなく、マイクログリッド技術による循環型社会システムによる域内経済の底上げを実現させることの出来る政策・施策に仕上げて、素早く講じて頂けるように強く要請して、この質問を終わります。
この質疑につきましては、本日付け地元紙で取り扱われた内容となります。
是非皆さまにご覧いただき、記事として取り扱われることになった経緯と顛末に注目頂きたいと願うところです。
記事にある「訂正」とは、「甘やかしている」という表記を『より適切な言葉で言い換える』という意味であり、その真意や狙いが変わるものではありません。
北の元気玉「道見やすのり」は、己の主義主張に基づいて質問・質疑するのであって、マスコミの取り扱われ方への配慮は一切しておりません。
一方で、私の質問・質疑の内容に対する賛否・ご意見やご助言について大歓迎ですので、ブログやSNS等を通じてお寄せいただきますようにお願いいたします。
最後に改めて明言させていただきますが、私は「正しい」アイヌ文化の認識を実現し、文化振興を通じたアイヌの人々の自立を促す政策に舵を切りきるべきだと考えている立場です。
アイヌ文化の消滅を望んでいる訳でなければ、「正しい」文化振興施策を止めるものでもありません。
これまで約60年もの間に、約120億円もの金額を投入して展開してきた施策の効果を明らかにし、温く継続させることを善しとしない主張です。
多くの皆さんにご覧いただきご理解いただければ大変うれしいことでありますし、今後共に国や道に、そしてアイヌの人々に対して提案を続けていきたいと覚悟しておりますことを申し述べておきます。
北の元気玉、今日も一日、「ウガイ・手洗い・たっぷり栄養補給、余裕があるなら笑って暮らす」を実践して働いて参ります。
何卒よろしくお願いいたします。
-------------------------------------
一 北海道アイヌ政策推進方策について
(一)アイヌ政策の効果について
それでは、機会をいただきましたので、方策についての質疑をさせていただきます。最初に、アイヌ政策の効果についてお聞きをしておきます。
道は、生活向上の名の下に、生活保護受給率の低下や進学率の向上等の施策を約60年続け、約120億円を費やしながら、どれだけの効果があったのか、客観的な道の見解を伺っておきます。
(アイヌ政策課長)
生活向上施策についてでありますが、道では、道内のアイヌの人たちの生活の実態を把握するため、市町村やアイヌ協会のご協力をいただきながら、昭和47年から8回にわたり「北海道アイヌ生活実態調査」を実施し、アイヌの人たちの生活向上施策の推進に努めてきたところでございます。
直近に実施いたしました平成29年の調査におきましては、生活保護率につきましては千分率で現していますが、昭和47年の115.7パーミルが36.1パーミルとなっております。また、高校の進学率につきましては41.6%から95.1%に、昭和54年で8.8%であった大学等への進学率は33.1%となっております。
このように、アイヌの人たちの生活は改善傾向にございますが、アイヌの人たちが居住する調査対象市町村全体との比較におきましては、依然として格差が見られるところであり、新たな方策に関する地域のアイヌの人たちとの意見交換におきましても、修学への補助など生活向上施策を求める声も多かったところでございます。
(指摘)
今の答弁の意味を汲みますと、継続していくということなのでしょうね。なお効果が足りないということであるならば、先ほど伺った60年、120億続けてきた政策の効果としては、非常に薄いというか、長きにわたり続けてもこの状態であるという解釈ができるのかと思います。
紆余曲折がありながら継続してきて、到達できない計画や目標に対して、これからも同じ調子で継続をしていくということは、むしろ拡大していこうとしていること自体に無理があるというふうにも理解をいたします。
まだ尚、差別があるから改善できていないというので、継続をするというロジックからは、支援のスパイラルから抜け出せない、いや、抜け出したくない思惑が、アイヌの人々や道に見え隠れしているのではないでしょうか。
(二)アイヌ政策の基準について
次の質問に移ります。政策による現状と基準について伺っておきます。
道の見解によると、これまでの効果は出ているということでもありますが、その効果は至って客観的でなければならず、バイアスの掛かった恣意的な調査などを根拠として政策を展開し続けることは、今の時世で認められるわけがないのであります。しかし、長きにわたり、国や道がそれらに頼ってきたことは事実です。その効果が、誰がどうやって把握をしてきたのか。その効果は一定基準が満たされるまで続けるのか。その基準とは何を指すのか、道の見解を伺っておきます。
(アイヌ政策課長)
アイヌ生活実態調査についてでございますが、生活の状況や教育、課税の状況などにつきまして、アイヌの人たちが居住する市町村が実施する市町村調査及び地区調査、それから、家族や所得の状況、アイヌ文化や帰属意識、差別の状況などについて、アイヌの人たちに直接伺う世帯調査及びアンケート調査により実施をしております。
道におきましては、この実態調査の結果や、国における政策の動向、アイヌの人たちからの意見などを踏まえまして、今後のアイヌ政策の検討を進めているところであり、アイヌの人たちの生活実態は、道民一般との比較においては依然として格差が見られることから、引き続き施策を推進する必要があるものと考えております。
(指摘)
道の主張とですね、道の見解と私の意見の相違ということがここで明らかになっているわけでありますけれども、60年続けてきて、なお縮まらないという政策が問題だというのであって、そもそもアイヌ政策が不要であると、私は述べているわけではありません。
その方法というものを見直すきっかけに、このウポポイ
が、そしてこの施策推進法が資していかなければならないというお話を申し上げているのであって、格差、格差と強調する道にあっては、この政策を続けなければいけない理由を一生懸命探しているにすぎないと私は受け取っているのであります。
(三)未来志向の意味について
次の質問に移ります。人の使う言葉の意味について伺っておきます。これまでの政策を受けて、アイヌ施策推進法からも使われることになった「未来志向」という言葉では、何をこれは意味をするものなのか、今一度、確認をします。
この表現は、いかにも抽象的で、互いに都合よく解釈できる妥協の言葉でしかないと考えますが、今一度明確な見解を伺います。
(アイヌ政策推進局長)
未来志向によるアイヌ政策についてでございますが、道では、昨年策定した「北海道におけるアイヌ施策を推進するための方針」におきまして、「アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、その誇りが尊重される社会の実現を図り、全ての道民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する」ことを目標としているところでございます。
道といたしましては、この目標の実現に向けまして、新たな方策では、これまでの生活向上に加えまして、民族としての誇りの源泉であるアイヌ文化の振興や、これらを活かした地域の活性化、産業や観光の振興などを含め、アイヌ施策を総合的に推進してまいる考えでございます。
(指摘)
今の答弁からは、誠にきれいな赤レンガ文学を聞いているわけでありますけれども、その真意は、妥協の産物でしかないと私は受けとめるわけであります。
せっかく、この未来志向というのは前向きな言葉であるわけですから、改めて、その意味、真意について、明確にできるよう、いや、明確にできるというよりは、国に、国民に、道民に、そしてアイヌの人々にとって必要である言葉として位置付けられるように国や関係者と議論を重ねていただきたいと思うところであります。
(四)アイヌ文化の未来について
次に、アイヌ文化の未来について、伺っておきます。
道は、アイヌ文化をどうしたいのか、私は、この5年間、環境生活委員会等で皆さんと意見交換を含めて機会を重ねてきたところではありますが、未だ、その真意を受けとめていることができません。
質問の最後に、監の見解を伺います。
(アイヌ政策監)
アイヌ文化の振興についてでございますが、アイヌ文化は、アイヌの人たちの民族としてのアイデンティティの基盤であり、本道にとってかけがえのない財産でもございます。
こうしたアイヌ文化の伝承や振興を図ることは、アイヌの人たちの社会的・経済的地位の向上はもとより、多様な文化の発展、本道経済や地域の活性化にとっても、大変重要なことと考えてございます。
このため、道といたしましては、アイヌの人たちが受け継いできた文化の保存・伝承や普及・啓発を促進いたしますとともに、アイヌ文化の復興等に関するナショナルセンターでございますウポポイをはじめ、道内各地域の活動が活性化するよう、国や市町村、関係団体などと連携しながら、より一層のアイヌ文化振興に取り組んでまいる考えでございます。
(指摘)
最後に、指摘を加えておきたいと思います。
今回、この質問をさせていただくに当たり、どのような形で質問を行えばいいのか、非常に悩みました。その表現、一つ一つ、様々に悩みながら、当たり障りのない言葉を選ぶのではなく、その真意、実態について、さらには、この環境生活委員会において、いかにこの国の政策と道の政策、さらには道民の意識、アイヌの方々の意識、これを前向きに、未来志向に、真の意味での未来志向という意味に向けていくためにどうしたらいいんだろうということを考えたのであります。
ただ、どうしてもその根底にある様々な不都合、こういうものが邪魔をして、質問に対する答弁を道庁の皆さんからいただくことができなかったり、さらには、私自身も萎縮してしまうというか、遠慮してしまう。言ってみれば、忖度をしてしまうような場面にも出会うわけであります。
この機会に、国と道、さらには当事者の皆さんにお伝えをしておきたい、申し上げておきたいことがあります。
アイヌ文化を利権と化してはいけないと思うのです。群がる勢力の目的を慎重に見抜かなければいけないのだと思います。実は、アイヌの人々を甘やかしているのは、国であり、道であり、そしてアイヌの人々自身なのではないでしょうか。
アイヌ文化を私たち日本国民が、地域の宝の一つとして伝承をし、アイヌの人々も、私たちも正しく文化の振興を図らなければなりません。このまま利権としか扱われないのであれば、アイヌ文化の末路は消滅でしかないのであります。これは断言できます。
確かに、過去に不幸な歴史があったのかもしれません。
それを御旗に利権の確保に努めても、生活の向上にはつながりません。それは60年続けていても今のようなありさまなのでありますから、事実なのだと私は判断します。
先ほどの報告にあった地域意見交換会の内容を伺っても、前向きなものとはほとんど見受けることができません。
今なお、欲しがる、まさしくこの状態が今なのだと判断することができます。
私たちの日本において、アイヌ政策は既にタブー視されている領域でもあります。今回の質問では、アイヌの人々が先住民であるとかないとか、差別があるとかないとかを取り上げて考えるつもりはありませんでした。なぜならば、その時点で前向きな政策、未来志向な政策として前進させることでしか、共生が実現できないからであります。
これからの日本では、国民と道民と、アイヌの人々が、力を合わせてアイヌ文化振興に努めることを通して、アイヌの人々の地位向上と経済的な豊かさをもたらす基盤を自ら整えていかなければならないのです。
これまでの政策に新たに加えられた文化振興施策を、生活向上施策とともに推進させるのではなく、文化振興を通して生活向上を実現させる覚悟を携えていただきたいとお願いしているのであります。そのためには、さらなる力強い文化振興施策が必要であることを理解することはできます。
道におかれては、国に追従することでしか展開できない政策だけではなく、真の意味で政策の実現を目指さなくてはなりません。
道には、このような考えがあることを必ず検討会議の場で示していただくとともに、私自身も引き続き正しいアイヌ政策のあり方について提案していくことを約束し、今回の質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。
(広田委員)
手続き的にどういうふうするのかというのはあるのですけれども、もしよろしければ、今、副委員長の御質問の中でですね、アイヌ民族を甘やかしているという、その表現は削除していただきたいと思います。お取りはからい、委員長にお願いいたします。
(荒当委員長)
理事会で諮ることにいたします。質問を進めていいですか。
(広田委員)
はい。委員長にお任せして。
(荒当委員長)
はい。
四,動物衛生検疫協定について
外務省の発表によると、日本産牛肉の対中輸出を再開することで、両国政府は、25日、「動物の衛生及び検疫における協力に関する日本国政府と中華人民共和国との間の協定」(以下、日中動物衛生検疫協定)に署名したと発表しています。
中国は、日本での牛海綿状脳症(BSE)発生を受けて、2001年から輸入を禁止してきました。再開されると、20年振りとなり、国内は基より道内の畜産農家にとっても朗報と言えます。
① 動物衛生検疫協定について
まず、この動物衛生検疫協定とは、どのようなものであるのでしょうか。これまでどのような協議を経て本協定の署名に至っているのかについても教えて下さい。
<答弁>
動物衛生検疫協定についてでございますが、外務省の公表によりますと、本協定は、国境を越えた動物疾病の管理における、日中間の協力強化を通じ、動物及び動物由来の製品の安全な取引を促進することを目的として締結されたものでございます。
協定の締結により、牛肉などの畜産物の対中輸出解禁に向けた両国間の調整の加速化が期待されますとともに、両国における疾病の発生等について、相互に情報を提供することが規定されており、より確実な水際検疫体制の構築に寄与するものと認識をしております。
なお、協議経過につきましては、平成30年12月6日に第1回政府間交渉を開催して以降、これまで3回の交渉を重ね、平成31年4月14日の日中ハイレベル経済対話におきまして、日中両国政府が合意に至り、令和元年11月25日に署名されたと承知をしております。

② 他国との協定締結状況について
今回は中国政府との協定ですが、他国との実績はあるのでしょうか。過去に類似の協定等が結ばれた事例について教えて下さい。
<答弁>
他国との協定締結実績についてでございますが、農林水産省に確認したところ、動物の衛生及び検疫における協力に関する協定につきましては、中国以外の国と類似の協定等が締結された事例はないと聞いているところでございます。
③ 他国との協定締結へ向けて
本協定は対中国との協定ですが、他国との協定に至るには、どのようなか課題が存在し、どのような対応や協議が必要で、どの位の時間を要するものであるのか、見解を伺います。
<答弁>
他国との協定締結についてでございますが、農林水産省によりますと、日中動物衛生検疫協定は、食肉等の安全な取引を促進するため締結したとのことであり、中国以外の国と締結した実績はございませんが、このたびの例では、第1回の政府間交渉から署名に至るまで、約1年を要しているということでございます。
④ 本協定が道内に与える影響について
道は、この協定が道内の畜産農家に与える影響についてどのように捉えているのでしょうか。見解を伺います。
<答弁>
畜産農家に与える影響についてでございますが、本協定の締結により、牛肉をはじめとした畜産物の対中輸出の解禁に向けた両国間の調整が始まり、様々な協議などを経て、将来的に中国への輸出が可能となれば、道産牛肉等の輸出拡大に大きく寄与することが期待されまして、畜産農家をはじめ関連産業に大きな経済波及効果があるものと認識してございます。

⑤ 道の必要な対応について
本協定を受けて、道は、国や道内の事業者に対して、どのような対応が必要となってくるのか、来年度予算措置を含めた対応について見解を伺います。
<答弁>
必要な対応についてでございますが、農林水産省に確認したところ、本協定により対中輸出が解禁に至るまでには、今後、中国が我が国のBSE・口蹄疫の禁止令を解除した上で、両国による食品衛生に関する評価や、と畜場などの施設の認定、輸出に関する条件や証明書の様式に関する協議等を行う必要があると聞いているところでございます。
道では、今後、両国間の交渉の状況を注視しながら、輸出が可能となった際には、速やかに輸出が開始できるよう、必要な対応を検討してまいる考えでございます。
⑥ 道内のこれまでの実績について
道内では、本年10月、香港向け道産牛肉輸出のための肉処理施設の認定が行われたと承知しています。その経緯と本協定の違い、更に、取扱実績量や見込量等について教えて下さい。
<答弁>
香港向けの牛肉輸出施設についてでございますが、香港へ牛肉を輸出するためには、香港食物環境衛生署との協議により厚生労働省が策定をいたしております「対香港輸出牛肉の取扱要綱」に基づき、と畜場等について、国の認定を受ける必要があります。
道内におきましては、この認定を受けるため、帯広市内で、と畜場を運営しております事業者が本年8月に申請を行い、10月3日に牛肉の香港輸出が可能な施設として道内で初めて認定を受けたところでございます。
現在、厚生労働省では、実際の輸出開始に必要となる香港からの登録通知を待っているところでありますが、今後、事業者における道産牛肉の輸出が円滑に進んでいくよう、道としては、輸出に必要となる衛生要件の確保や食肉衛生証明書の発行等に努めてまいる考えでございます。
⑦ 道内で対応可能な種について
特筆すべきは、本協定には、家畜のみならず鳥獣類や野生の動物も含まれていることです。道内での対応種は多いと見込まれます。牛肉のみならず、どのようなものが見込まれることになるのか伺います。
<答弁>
本協定の対象についてでございますが、本協定の対象は、動物及び動物由来の製品とされ、動物は、家畜、家きん、鳥獣類、野生の動物など、動物由来の製品は、肉、原皮、いわゆる皮だとか、内蔵などが定義されてございまして、牛肉をはじめ、豚肉、羊の肉、鶏肉、エゾシカ肉などが該当するものと考えられてございます。
⑧ ジビエ対応への課題について
海外におけるジビエ需要については旺盛なニーズが期待されるところです。
特に、エゾシカの場合の課題について、どのような対応が必要になると具体的に想定されるのか、見解を伺います。

<答弁>
エゾシカ肉の輸出についてでございますが、道では、これまで、エゾシカの有効活用を推進するため、高度な衛生管理を行うエゾシカ肉の処理施設を認証する制度を創設し、安全・安心の確保に取り組んできたところでございます。
エゾシカを食肉として輸出するためには、相手国との合意や安全性を確認するための手続きが必要となりますが、現段階では具体的な手続き等が国から示されていない状況にありまして、今後、こうした所要の環境が整い、輸出が可能となった場合には、本道独自の衛生管理基準に基づいて処理されたエゾシカ肉の販路拡大に繋がることも期待できますことから、道としては、今後、国の動向を注視しながら、エゾシカ肉のブランド向上に努めてまいる考えでございます。
⑨ 道の期待と意欲について
道として、今後、道産食品輸出の拡大へ向けて、中国のみならずアジアや欧米、世界へと市場を拡大していく必要があります。
しかし、協定は政府間交渉であるために、道の一存では何も進めることが出来ません。道は、国の働き掛けや海外マーケットへの直接的なアプローチについて、今後の展望をどのように見込んでいるのか、道の期待と意欲について見解を伺います。
<答弁>
道産農畜産物等の輸出の拡大についてでございますが
先月、日本と中国の両政府は、「日中動物衛生検疫協定」に署名し、今後、動物衛生や食品衛生などの協議が進められ、牛肉などの畜産物の輸出環境が整えられることが見込まれております。
道では、「第Ⅱ期北海道食の輸出拡大戦略」におきまして、牛肉や米などを重点品目として位置付けており、新たに米国向け輸出可能施設が認められた牛肉については、米国でのテスト販売やベトナムでの商談会の開催、昨年、中国向け輸出の精米施設等が登録された米につきましては、中国や香港、米国などでのプロモーションや商談会の開催など、販路拡大に取り組んでおります。
道といたしましては、今後とも、国家間交渉に基づく相手国の規制の撤廃等について国に要請してまいるほか、重要な輸出先国として期待される中国などにおきまして、今後、畜産物の輸出が可能となる好機を想定し、円滑な輸出に向けた取組を先んじて進めるなど、関係団体や輸出関連企業等との連携のもと、北海道の認知度を高め、新たな市場を開拓するために、海外におけるプロモーションや商談会を積極的に開催しながら、一層の輸出拡大に努めてまいります。
<指摘>
ありがとうございました。一連の質問としては、これで終わりなんですが、最後にまた指摘をさせていただきます。実は今回質問することとなりました、この日中の動物衛生検疫協定、この存在を知ったのはごくごく最近でありまして、11月25日に協定署名と、このほぼ当日にですね、存在を知ることになりました。このときに驚いたわけであります。もちろん、中国というですね、14億の胃袋に対して、私たちの安心で安全な牛肉を、さらには、様々な動物と規定される様々な食品を輸出できるようになるということは、非常に大きな私たちにとっての希望、期待となるからであります。これまで様々なですね、道内業者の皆さんが挑戦しようとしてきても、実現できなかったことであります。もちろんこれは対中ということでありますが、今後、アジアに、先ほども申し上げましたけれども、欧州に、牛肉をはじめとする様々な動物を、エゾシカをはじめとする様々なジビエをですね、輸出をしていく環境を整える、これが私たちにとっての活路であると信じますので、お願いをしたいところでありますし、ひとつ気になるのはですね、答弁の最中に国の動きを注視してまいるということがたくさん出てまいりました。私はですね、注視では不足だと思うんですね。道のみなさんには、積極的で、いや、もっと前のめりでできることは今からどんどんと取り組んでまいることが必要なんだと思います。国の予算がつかなければ、道が動けない、これはナンセンスであります。予算ならば取りに行けばいい、どうしても必要なものであればですね、民間とタッグを組みながらPRをしていくことは可能であります。先手を打って、先の先を打ってですね、125億のまずは達成を、その先を、その先の道をですね、道民に示していただきたいと思うところであります。ありがとうございました。
三 収入保険について
次に、収入保険についてですが、
今年は、台風15号や19号、21号の本州上陸などにより、全国各地で大きな農業被害が発生しており、現在もその復旧に向けて、懸命な作業が進められています。
幸い本道では、台風等による大きな農業被害もなく、天候にも恵まれたこともあり、農作物の作柄は概ね良好となっています。
農業は、自然災害や天候などによる収穫量の減少だけでなく、農産物の需給状況などによる価格変動の影響も受けることから、国は、新たに収入保険制度を創設し、農業共済制度と併せて、農業者のリスク軽減を図ることとしています。
9月の農政委員会でも、我が会派の同僚議員が収入保険について伺いましたが、改めて、収入保険制度の現状について、何点か伺います。

(一)収入保険の加入状況について
今年1月から受付が始まった収入保険制度について、本道の加入状況はどのようになっているのか、全国の状況と併せて伺います。
<答弁>
収入保険の加入状況についてでありますが、農林水産省は、本年10月に、8月末現在における収入保険の加入実績について、都道府県別に、青色申告者数を基に設定された「加入推進目標」、「加入実績」、目標に対する「加入割合」をそれぞれ公表したところでございます。
それによりますと、本道は、6,440経営体の目標に対して、1,360経営体が加入し、割合が21パーセント、全国では10万経営体の目標に対して、22,543経営体が加入し、割合が23パーセントとなっております。
(二)都府県における状況について
全国の状況について、都府県別に見ると、どのような地域で加入実績が高くなっているのか、また、その要因は、どのようなところにあると分析しているのか、伺います。
<答弁>
都府県における加入実績などについてでありますが、農林水産省の発表では、愛媛県が、2,000経営体の目標に対して実績が1,389経営体で割合が69パーセントと最も高く、次に青森県が、2,580経営体の目標に対して実績が1,627経営体で割合が63パーセント、次に島根県が、910経営体の目標に対して実績が519経営体で57パーセントとなっております。
次いで、秋田県、大分県の順となっております。
農林水産省によりますと、加入率の高い要因としまして、愛媛県や青森県にあっては、収入保険の方が果樹共済よりも補償割合が有利であること、島根県、秋田県や大分県にあっては、今年度の共済掛金が上昇し、収入保険に割安感が出たことを挙げております。
(三)他制度からの移行と品目別加入状況について
これまでの共済制度やナラシ対策などから、収入保険に移行している状況はどのようになっているのか、また、収入保険の品目別の加入状況はどうなっているのか、伺います。

<答弁>
他制度からの移行状況等についてでありますが、農林水産省が公表した本年4月末現在の移行件数は、ナラシ対策からが7,811件、果樹共済からが4,573件、野菜価格安定制度からが4,427件、畑作物共済からが2,588件となっております。
また、本年8月末現在の品目別の加入状況は、米が14,494件、野菜が10,503件、果樹が6,856件、豆類が3,057件、麦類が2,974件、花きが1,253件などとなっております。
(四)本道の加入実績の受け止めについて
安定した農業経営を進めていく上で、収入保険を有効に活用していく必要があると考えます。
制度発足1年目ですが、本道の加入実績を、道は、どのように受け止めているのか、伺います。
<答弁>
加入実績の受け止めについてでございますが、本道においては、加入経営体数が1,360と全国で三番目に多い一方、目標に対する加入実績の割合は21パーセントと、全国平均の23パーセントとほぼ同水準となっております。
本道では、共済制度やナラシ対策などの類似制度への加入率が高く、加えて、昨年は災害による共済金の支払を受けたことで、様子見となった農業者も多かったと考えられているところでございます。
引き続き、農業者が適切な制度を選択できるよう、収入保険の周知を進めていく必要があると考えております。
(五)加入の促進に向けて
9月の農政委員会では、「農業者が無保険の状態とならないよう、様々な機会を捉えて、共済制度を含めて、収入保険の周知に努める」との答弁がありましたが、その後、加入促進に向けて、どのような取組を行ってきたのか、伺います。
<答弁>
加入促進に向けたこれまでの取り組みについてでございますが、収入保険に関心が高かった道央・道南地域において収入保険の周知を効果的に進めるため、本年10月から11月にかけて、空知、石狩、後志、檜山、上川の各振興局において、道と農業共済組合及び北海道農業共済組合連合会との意見交換を実施し、道から共済組合に対し必要な情報提供を行うとともに、園芸施設共済とセットで収入保険の周知を行うとしたところでございます。
また、これと併せ、収入保険を選択した農業者から、加入理由などの聞き取り調査を実施するとともに、各振興局や普及センターの職員に対し、収入保険の見直し内容などの情報共有を行ってきたところでございます。
(六)今後の対応について
自然災害による農業被害や、農産物等の需給緩和等による価格変動など、農業者の経営リスクを軽減するためには、収入保険は重要な制度であると認識しており、積極的な制度周知と普及を図っていくことが重要と考えます。
道では、今後、収入保険の加入促進に向けて、どのように対応していく考えなのか、所見を伺います。
<答弁>
今後の対応についてでございますが、収入保険は、品目の枠にとらわれずに、自然災害による収入減少だけでなく、価格低下なども含めた様々なリスクによる収入減少を補てんする保険でございまして、近年、災害への備えの重要性が増す中で、収入保険の積極的な理解を図っていく必要があると認識をしてございます。
国は本年9月、補償金額を小さくする代わりに、掛金の安いタイプを追加する見直しを行った中で、道といたしましては、まずは収入保険への関心が高かった道央・道南地域への重点的・効果的な普及推進活動を行い、それ以外の地域につきましても、収入保険に係る最新の動向を情報提供するなど、農業者が無保険の状態とならないよう、引き続き、様々な機会をとらえ、関係機関・団体と連携をいたしまして、共済制度を含めて、収入保険の周知に努めますととともに、北海道農業共済組合連合会などと情報交換を行いながら、必要に応じて、制度の充実などを国に求めてまいりたいと考えてございます。
二 農畜産物等の輸出拡大について
次に、農畜産物等の輸出拡大についてですが、
道では、第Ⅱ期北海道食の輸出拡大戦略に基づき、2023年までに道産食品の輸出額を1,500億円、そのうち農畜産物・農畜産加工品の輸出額を125億円とする目標を掲げ、現在、輸出拡大に向けて取組を進めています。
TPP11や日EU・EPAの発効、日米貿易協定の締結などグローバル化が進展していく中で、本道農業の生産力や競争力を高めながら農畜産物等の積極的な輸出拡大を図っていくことが重要と考えますので、今後の取組などについて、以下、伺います。
(一)農畜産物等の輸出の現状について
今年の農畜産物等の輸出実績はどのような状況なのか、品目別に伺います。また、主な国別・地域別への輸出実績についても、併せて伺います。
<答弁>
本年度の輸出実績の状況についてでありますが、2019年の上半期の農畜産物等の輸出額は16億4千万円となっており、米や日本酒の輸出額が伸びたことによりまして、2018年と比べて1億9千万円増加したところでございます。
品目別では、台湾、米国、シンガポールを中心に輸出している長いもは、収量が平年をやや下回ったことから、前年と比べ、8千万円減少の6億4千万円、米は、香港、米国、台湾、ベトナムなどに加えまして、昨年、輸出向け精米工場等が登録され、10月以降、道内港から中国への輸出が開始されたことなどによりまして、前年と比べ、1億1千万円増加の2億2千万円、日本酒は、香港での日本酒の需要が拡大し、輸出量が大きく伸びたことによりまして、前年と比べ、5千万円増加の1億6千万円、ミルク等は、香港などへのLL牛乳の輸出量が伸びたことにより、前年と比べ、4千万円増加の4億7千万円、牛肉は、シンガポール、ベトナムに加え、一時停止していましたアラブ首長国連邦向けの輸出が再開したことなどによりまして、前年と比べ、2千万円増加の3千万円となったところでございます。
また、主な輸出先である国や地域では、香港が7億1千万円、次いで、台湾が3億4千万円、米国が2億8千万円、シンガポールが1億7千万円、中国が1億円となっております。

(二)輸出拡大に向けた道や産地の取組について
道では、農畜産物等の輸出目標125億円の達成に向けて、今年度、どのような取組を進めているのか、特に、輸出に取り組む産地づくりへの支援を行っていると聞いていますが、そのような地域では、どのような取組が行われているのか、併せて伺います。
<答弁>
輸出拡大に向けた取組についてでありますが、道では、米・日本酒・青果物・牛肉を重点品目に設定し、品目ごとに様々な取組を実施しており、米については、中国における展示会への出展やレストランでの個別商談会の開催、日本酒につきましては、フランスや香港における展示会や商談会への参加、青果物につきましては、台湾における高級スーパーや百貨店での店頭プロモーションや、輸送の効率化に向けた実証試験、牛肉につきましては、ベトナムにおける調理方法の工夫による試食商談会の開催などに取り組んでいるところでございます。
さらに、関係団体と連携しまして、千葉県で開催されました国内最大級の輸出商談会であります「日本の食品 『輸出EXPO』」における北海道ブースの出展や、台湾からのバイヤーの招へいなどを実施しているところでございます。
また、道では、長いもの輸出量の拡大に向けた新品種の導入や輸送時の品質保持のための包装資材の開発、米の輸出用多収品種の研究や、玄米調製施設の改修、相手国に応じた牛肉の処理加工施設の整備や販路開拓に向けた調査など、輸出に意欲的な産地の取組を支援しているところでございます。
(三)台湾での農畜産物等のPR活動について
道では、先日、道内のJA関係者などとともに、台湾で道産農畜産物のPR活動等を行ったとのことですが、具体的にどのような取組を行ってきたのか伺います。
これまでも、台湾には、本道を含め多くの都道府県から様々な農畜産物が輸出されており、輸出相手国としては成熟国とも考えられますが、今後の輸出拡大に向けて、どのような課題があり、どう対応していこうと考えているのか、併せて伺います。
<答弁>
台湾における輸出拡大に向けた取組についてでございますが、台湾は、本道の農畜産物等の輸出額の3割を占めます重要な輸出相手国でございますことから、道では、平成28年度から台湾におきまして、量販店などでの販売促進活動や高級スーパーにおけます常設売り場の設置、百貨店におけます北海道フェアの開催などを行ってきたところでございます。
こうした中、台湾におきましては、残留農薬基準などの検疫条件や輸出手続きへの対応、さらには、国内外の産地との競争が激しいことが課題となってございます。
道といたしましては、こうした課題に対応いたしまして、道産農畜産物等の輸出を拡大するため、輸出規制の撤廃や緩和を国に要請しますとともに、プロモーションや商談会の開催によりまして北海道の安全・安心な農畜産物のさらなるPRに努め、輸出に取り組む産地を支援してまいります。

(四)新興産地等のPR活動について
道内の産地では、農畜産物等の輸出拡大に向けて、様々な取組が進んでいますが、輸出の取組を始めたばかりの新興の産地からは、地元産品の海外への売り込みを行おうとしても、単独では、勝手がわからずに厳しい状況があるとの声も聞かれます。
今回の台湾でのPR活動では、世界中の輸出入のバイヤーが一同に集まるイベントが開催されるとの情報をキャッチして参加したと聞いていますが、このことは、台湾だけでなく、世界中から食のプロが集結する一大イベントであり、こうしたイベントに、道内産地が結集して出展するなどの取組を進めることが、新興産地の輸出拡大のきっかけにもなると考えます。
今後、このようなイベントなどにおいて、産地の関係者と連携してPR活動を行っていくことが、農畜産物等の輸出拡大に向けた重要な取組と考えますが、道の見解を伺います。
<答弁>
産地と連携した輸出拡大の取組についてでありますが、新たに輸出に取り組もうとする産地におきましては、海外から求められるニーズや市場動向、検疫条件や輸出手続、輸出事業者など、様々な情報の把握が不可欠なことから、道では、国の事業などを活用して、輸出診断に基づく専門家によるアドバイスや、必要な情報の提供を行っているところでございます。
道としましては、今後とも、関係団体や輸出関連企業等と連携し、国内外で開催される展示会や商談会、販路開拓に向けたプロモーションなど様々な機会に意欲的な産地が参加できますよう、輸出に取り組みやすい環境を整えてまいります。
(五)今後の対応について
台湾を始め、中国へのコメや、米国への牛肉の輸出など、新たな市場や品目が拡大している中で、一層の輸出拡大に向けて、相手国となる様々な国や地域の文化、食生活などの状況をしっかりと見極めながら、チャレンジしていくことが重要と考えます。
農畜産物等の輸出目標125億円の達成に向けて、今後、どのように取組を推進していく考えなのか、所見を伺います。
<答弁>
輸出拡大に向けた今後の取組についてでございますが
日本とは異なる食文化や食習慣を有する諸外国への道産農畜産物等の輸出拡大に向けましては、その国々の嗜好に合った品目を選択して、その品目の特性を活かした調理方法や食べ方の周知と併せたプロモーションなどを実施することがさらなる需要の創出につながるものと認識してございます。
このため、道では、「第Ⅱ期北海道食の輸出拡大戦略」におきまして、米や青果物、牛肉、日本酒を重点品目として位置付けており、例えば、米については、炊飯方法の実演による商談会を開催するなどし、 国ごと、品目ごとに市場ニーズを分析し、ターゲットを絞りながら戦略的に輸出の拡大に取り組んでおります。
道といたしましては、今後とも、関係団体や輸出関連企業等と連携をし、展示会や商談会などによりまして、世界から信頼される北海道ブランドの認知度を高めながら、海外市場を積極的に開拓してまいる考えでございます。

<指摘>
この質問に関しては、指摘を加えさせていただきます。
これらの問題は、台湾が、わりと出てきましたが、台湾に限った課題ではないと捉えてはおりますが、今回の質問について、理事者と意見交換をする中で、2023年まで道産食品の輸出額を1,500億円にすると、そのうち農畜産物・農畜産加工物の輸出額を125億円にする目標であるとのことは伺っております。
申し上げておきたいことは、例えば、この125億円の内訳をどの国に、何をどれだけ輸出する戦略をとっていくのか、いわゆるセグメントされた目標額を設定しなければならないということであります。
さらに言うと例えば、私たちの北海道は台湾からどれだけの台湾産食品を輸入し、農畜産物・農畜産加工物の輸入を行っているのかと問い合わせたところ、把握ができていないとのことでもありました。
輸出・輸入は、商売でもあります。それは等価でなくても相互交流であることは間違いありません。
観光客数を伸ばそうと期待する時に、さらには道産食品輸出を伸ばそうと期待する時に、一方的な増進のみを見込むことは無理があり、摩擦や軋轢を生んでしまうことに繋がります。
それは歴史が教えてくれることであります。
まずは、相手を知ること。その国から、地域からどれくらいの人と物が流れ混んでいるのかを相互に行き来があるのかを把握することが欠かせません。
その上で、何をどれだけ伸ばしていくのか国家間や地域間で相互に売り込んでいくことが必要です。
そのために必要な手立ては、戦術は千差万別であります。
ただ125億円分の輸出をしたいとPR等を重ねれば、実現すると信じることは、自己中心的な妄想でしかありません。
行政として自制してしまったり、自ら一線を画してしまうことは、攻める行政が求められる未来にとって足かせにしかならないのであります。
同時に、国内には、46都府県が存在し、それらは競合先であることを意味します。
地域間競争を勝ち抜いていかなければならず、そのような中でも北海道が優位性を保っていることに議論を待ちません。
だからこそ、道内の生産体制、相手国等の状況、情勢の変化を敏感に察知し、適宜、的確に後押ししていなければならないのです。
道は受け身であってはいけません。
これまでの行政手法に満足することなく、可能な限り、民間感覚で政策を推進していかなければ、目標の達成はおろか、その先の道を道民に示していくことはできません。
セグメントとされた個別目標に対して、必要な手段を講じることができるように国や民間そして相手国や地域と交流を深めながら、力を合わせて、元気あふれる北海道を実現して欲しいと強く要請をしておきます。
一 日米貿易協定について
はじめに、日米貿易協定についてですが、
日米貿易協定による本道農業への大きなダメージが危惧されることから、今定例会でも、我が会派では、一般質問で道の対応等を伺ってきましたが、新たな国際環境の下で、本道の基幹産業である農業が持続的に発展していくためには、対策の一層の強化が必要なことから、今後の対応などについて、以下、伺います。
(一)影響試算について
道は、日米貿易協定に係る影響試算において、関税削減に伴い生産額は減少するものの、国内対策の効果を見込み、生産量は維持されるとしています。
国でも同様の表現をしていますが、何故、生産量が維持されることになるのか、改めてその考え方を伺います。
<答弁>
生産量の維持についてでありますが、道が行いました影響試算では、産地パワーアップ事業、畜産クラスター事業などの体質強化対策により、生産コストの低減や品質向上による国産の需要を確保することができ、牛・豚マルキンなどの経営安定対策により、価格下落に対しても所得が確保されることで、生産量が維持されると見込んだところであります。

(二)道の要請について
日米貿易協定により、国が「総合的なTPP等関連政策大綱」を改訂する方針を示したことを受けて、道は、関係団体とともにオール北海道で要請を行ったところですが、大綱の改訂に向けて、どのような点を重視して要請を行ったのか、伺います。
<答弁>
国への要請についてでありますが、道では、総合的なTPP等関連政策大綱の改訂に向け、日米貿易協定の合意による影響などについて、丁寧な説明を求めるとともに、農業の再生産を可能とする万全な対策として、体質強化対策、経営安定対策、TPP11協定の見直しを国に要請したところであります。
具体的には、体質強化対策として、 畜産クラスター事業や産地パワーアップ事業をはじめ、多様な担い手の育成、スマート農業の推進など、農業の生産基盤の強化に向けた対策の充実、輸出の拡大に向けた環境の整備、国産ナチュラルチーズ対策などの農林水産物等の競争力の強化を、また、経営安定対策として、牛・豚マルキンや加工原料乳補給金制度、畑作物の直接支払交付金などの対策の適切な運用を、さらに、牛肉、豚肉、ホエイのセーフガードが適切に発動されるよう、TPP11協定の修正をそれぞれ求めたところでございます。
(三)牛肉のセーフガードについて
牛肉のセーフガードについては、2020年度の発動基準数量が24.2万トンと、昨年度の米国からの輸入実績を下回る水準となった一方で、TPP11のセーフガード発動基準数量は、米国を含むTPPの数量のままであり、実質的には、豪州などからの輸入増に歯止めが効いていない状況と考えます。
道は、どのような認識でいるのか、伺います。
<答弁>
牛肉のセーフガードについてでありますが、日米貿易協定の合意により、米国産牛肉の輸入急増に対するセーフガードが措置された一方、TPP11協定に基づくセーフガードの発動基準数量が、米国を含むTPP協定と同じであり、実質的に発動しづらい状況でありますことから、TPP11協定の修正が必要と認識しております。
このため、道では、10月下旬に実施した総合的なTPP等関連政策大綱改訂に関する要請や、11月下旬に実施した、国の農業政策に関する提案において、セーフガードが適切に発動されるよう、TPP11協定の修正を要請してきたところでありまして、今後とも、適時適切に国に求めてまいります。

(四)牛肉生産への影響について
道が行った日米貿易協定の影響試算では、とりわけ米国産牛肉と肉質面で競合するホルスタイン種などの乳用種への影響が大きくなっています。
本道でもこれからは、他府県の主産地に負けない、国内外から高い評価が得られるような和牛の生産拡大に取り組んでいく必要があると考えます。
道では、和牛の生産振興をどのように考えているのか、伺います。
<答弁>
和牛の生産振興についてでございますが、本道は、和牛の飼養頭数では、鹿児島県や宮崎県に次ぐ、第3位の産地でございまして、府県に子牛を販売する、いわゆる、素牛供給地域としての役割を果たすとともに、近年は、国内外において和牛の需要が高まる中、北海道ブランドとしての牛肉生産の取組を進めてきたところでございます。
こうした中、このたびの日米貿易協定におきましては、米国向け牛肉の輸出枠が拡大されたほか、先月25日には、日中間で動物衛生検疫協定が署名をされるなど、今後、牛肉の輸出機会が拡大していくものと承知しております。
道では、これまでも、令和7年度を目標年とする「第7次北海道酪農・肉用牛生産近代化計画」に基づきまして、和牛の生産振興に向けて、優良な種雄の造成や繁殖雌牛の確保、飼養管理技術の向上などに取り組んできたところであり、今後も引き続き、関係団体・機関と一体となりまして、更なる和牛の生産振興を図りながら、本道の和牛の主産地としての確固たる地位の確立に努めてまいります。
(五)畑作農業の課題について
今回の日米貿易協定では、道の試算で生産減少額が大きいとされた牛肉や乳製品など、畜産・酪農への対応ばかりがクローズアップされていますが、日米貿易協定だけでなく、既に発効しているTPP11や日EU・EPAにおいて、小麦を始め、畑作物についても関税削減による生産額の減少といった影響があると試算されており、輪作を基本とする本道の畑作農業への影響が懸念されます。
道では、こうした情勢を踏まえ、本道の畑作農業が抱える課題をどのように認識しているのか、伺います。
<答弁>
本道の畑作農業の課題についてでありますが、日米貿易協定など、国際化が進展する中、実需者のニーズに即した高品質な畑作物の安定生産が課題となっているほか、地域におきましては、農業の担い手不足や高齢化が進行し、労働力不足が深刻化しております。
また、本道の畑作の安定的な生産に不可欠な輪作を構成します畑作4品につきましては、小麦や大豆の作付面積が増加する一方、これらに比べ、労力を必要とするてん菜や馬鈴しょの作付が減少傾向にありますことから、バランスのとれた輪作体系を維持することが課題となっております。
(六)畑作農業の推進方策について
適正な輪作体系を維持しながら、土地資源を活かした本道の畑作農業が、今後とも持続的に発展していけるよう、道として、どのように取り組んでいくのか、伺います。
ドローンによる農薬散布など、スマート農業の積極的な導入による省力化の推進のほか、排水対策などの農業基
<答弁>
畑作農業の振興についてでございますが、本道の畑作農業は、我が国の食料の安定供給とともに、地域の産業と結びつきながら、雇用や経済を支える基幹産業として重要な役割を果たす一方、国際化への対応や労働力不足など、多くの課題を抱える中で、関係機関・団体が一体となって、これらを克服し、国内外に競争力のある生産体制を構築することが必要と考えてございます。
このため、道では、国の「産地パワーアップ事業」や「畑作構造転換事業」などを効果的に活用しながら、てん菜や馬鈴しょの大型移植機や収穫機の導入をはじめ、トラクターの自動操舵や
盤整備の推進、さらには、実需者が求める品質を確保するため、新たな品種や技術の開発・普及などを総合的に推進し、実需者ニーズに即した生産や適正な輪作体系の維持・確保を基本に、本道畑作農業の持続的な発展に取り組んでまいります。
(七)財源問題について
日米貿易協定の影響で、関税等の削減・撤廃により、関税等を財源とする牛・豚のマルキン事業や、小麦など畑作物の経営所得安定対策などが、今後、安定的に講じられるかどうか懸念されるところです。
今回の協定の締結で、どの程度の関税等の減少が見込まれるのか、また、道は、これにどのように対応していく考えなのか、伺います。
<答弁>
関税等の減少についてでありますが、国においては、日米貿易協定の合意内容の最終年度における我が国の関税収入減少額等を機械的に試算しており、それによりますと、農産品については1,020億円、麦のマークアップについては208億円、それぞれ減少することとされたところであります。
一方、国は、現行の総合的なTPP等関連政策大綱におきまして、農林水産分野の対策の財源については、将来的に麦のマークアップや牛肉の関税が削減することにも鑑み、既存の農林水産予算に支障を来さないよう政府全体で責任を持って毎年の予算編成過程で確保する、としておりまして、道としましては、今後とも、対策に必要な予算の確保を、国に求めてまいります。

(八)今後の対応について
日米貿易協定により、農畜産物については更なる交渉が行われる可能性があることから、一般質問では、再協議に関する道の認識と対応について伺い、「国は、今後の再協議については、自動車、自動車部品を想定しており、それ以外は農林水産品を含め想定していない」との答弁でした。
しかし、一部の報道では、米議会下院が開催した公聴会で、農業団体から、米や乳製品の市場開放が不十分であり、追加交渉の対象とするよう求める声が相次いだことが報じられるなど、予断を許さない状況にあります。
道は、今後の日米交渉の行方にどう対応していくのか、また、新たな国際環境の下での持続的な発展に向けて、どのように取り組んでいく考えなのか、伺います。
<答弁>
今後の対応についてでありますが、日米貿易協定の合意により、グローバル化が一層進展する中、本道の基幹産業である農業が、いかなる環境下においても、その再生産を確保し、持続的に発展していくことが何よりも重要であります。
このため、道といたしましては、今後の日米間の交渉状況を注視しながら、国に対し、交渉に関する丁寧な情報提供と必要な国境措置の確保を求めてまいります。
また、関税の削減・撤廃の影響は、長期に及ぶ中で、農業者は将来に不安を抱えていることから、道といたしましては、協定の発効による影響を継続的に把握し、引き続き、国に対し、必要な対策と予算の確保を適時適切に求めていくとともに、改訂される総合的なTPP等関連政策大綱に基づく体質強化や、経営安定に向けた施策も効果的に活用しながら、農地や営農施設、農畜産物の集出荷施設等の生産基盤の計画的な整備、多様な担い手の育成・確保、生産性を高め、省力化を進めるスマート農業の推進、北海道のブランド力を活かした米や牛肉等の輸出の拡大など、生産力と競争力の一層の強化に努め、多様な担い手が将来に希望をもち、安心して営農に取り組み、次の世代に引き継いでいける北海道農業の確立に力を尽くしてまいります。
この件については、既にFacebook等で公開してきた内容です。
この度、鈴木知事や山岸道警本部長とも共有させていただくことになりました。
野党は基より、現場で加勢する「専門家」を自称する輩とも対峙していく覚悟です。
何も乱暴なことは致しません。法治国家として、毅然と対処していくのみです。
※更に、近日中に動画による質問&答弁も試みたいと考えています。乞うご期待。
—————————————————————–
C,アイヌ総合政策の推進について
次に、アイヌ総合政策の推進について伺います。
この件につきましては、先の環境生活委員会で触れましたが、道警察本部にも関わることでありますので、改めて一般質問とさせていただき、知事と道警本部長から見解を伺います。
この事件は、9月1日に、紋別市内藻別川で、道の許可を得ずにサケを数十匹採捕した事件が発生したと報道されています。その場で道の職員が中止を求めましたが、紋別アイヌ協会の畠山会長が、9月1日午前5時頃に違反行為に及んだと承知しています。

① 事実関係他について
最初に、事実関係他についてお聞きします。
当日は、オホーツク総合振興局の職員がその場に居て中止を求めているとお聞きしています。昨年は、道警に協力を求め、立会って頂き、中止を求めて採捕が行われなかったと聞いています。その意味からも意図的であり、同一人物によって繰り返されている点からも、この密漁犯行は悪質であると言わざるを得ません。
道警が把握しているこれまでの経緯と、密漁犯行を未然に防ぐ意味から何故今年は道職員に同行することができなかったのかを、また、今回は既に道から告発を受けているとされていますので速やかな対応を求めます。道警本部長の見解を伺います。
<答弁> 道警本部長
・昨年の対応
道からの協力要請に基づき、警察官が現場に赴き、
法令に違反するサケ・マスの採捕がまさに行われようとするのを認めたことから、
その予防のため関係者に必要な警告を発し、
違反行為の発生を未然に防いだもの。
・本年の対応
道と対応策を繰り返し協議し、
伝統的な儀式に関連する行為であることから、まずは、
行政指導により、特別採捕許可の申請が行われることが
望ましいと判断し、道職員に同行しなかったもの。
② 再発防止について
次に、再発防止について伺います。
紋別アイヌ協会の畠山会長は、認められてもいない「先住権」や「自己決定権」を振りかざし、特別採捕の申請を拒否して、その場で密漁犯行に及んだと聞いています。
これは、権利云々の前に、身勝手な行動であり、国内のアイヌの人々やアイヌ施策推進法の成立に関わった方々にとっても迷惑であると断ずることが出来る密漁犯行であると言わざるを得ません。
私は、来年以降の密漁犯行を防いでいく為にも、今回の事案については厳正に対処していただかなくてはいけませんし、一方で、アイヌ施策推進法に則った特別採捕の申請については、柔軟な対応を検討する必要もあると考えます。
今回の件をどのように受け止め、またどのように対応していく考えであるのか、知事に伺います。また、密漁犯行の再発を防止するため、どのように取り組む考えなのか、道警本部長に伺います。

<答弁> 道警本部長
・来年以降の対応
これまでの経緯を踏まえつつ、
道を始めとする関係機関との連携を図り、
行政指導では違反行為を予防できないおそれがある場合
には、警察としても早めの指導や警告を行い、
道職員と共に特別採捕許可の申請を促すなど、
違反行為の未然防止に努めてまいる。

<答弁> 知事
・河川内におけるサケマスの採捕は、法や規則で禁止。
・アイヌ文化の伝承等を目的とする採捕は、特別採捕許可で認めている。
・今回、再三の指導にも関わらず、採捕行為に及んだことは、誠に残念。
・道としては、アイヌ施策推進法の主旨を踏まえ、
採捕が円滑に行えるよう検討しているところ。
・今後とも、申請が適切に行われるよう関係者に対し働きかけるなど、
道警と連携して再発防止に努めてまいる。
この質問は、未来の私たちにとって「新・エネルギー革命」とも言える大きなテーマとなっています。
その事実に気付いて頂ければ幸いです。
この課題についても、皆さんとお約束している「北海道の元気」の為に、必ずや実現させていきたいと決意しています。
※更に、近日中に動画による質問&答弁も試みたいと考えています。乞うご期待。
——————————————————————-
B、家畜排せつ物の利用促進について
次に、北海道家畜排せつ物利用促進計画について伺います。
農水省の畜産統計や畜産物流統計、そして、道による第7次北海道酪農・肉用牛生産近代化計画などを見ると、北海道については、飼育農家戸数は減少しているものの、飼育農家の大規模化によって飼育頭数は増加傾向にあるとされています。基より、北海道が国内に向けて担うその役割は決して少ないものではなく、農業立国を目指す私たちは、効率的な大規模化を実現し「稼ぐ農業」を実現させていかなければなりません。
そのような中で、北海道家畜排せつ物利用促進計画が平成28年3月に策定され、令和3年3月には次期の見直しを予定していて、令和2年度に検討を行うと承知しています。
① 道内の状況について
最初に、道内において飼育頭数が増加するということは、自ずとその排せつ物の増加が必然であり、その処理については適切な有効活用と循環利用が求められます。
その発生量の将来見込みについて伺います。
<答弁>
・平成30年における道内の家畜排せつ物の年間発生量は、
約2千万トンと推計され、その9割が牛由来。
・道内の家畜の飼養頭羽数は、今後とも微増で推移すると見込まれる。
・家畜排せつ物の発生量についても、微増していくと見込まれる。
・一方、1戸当たりの飼養頭羽数は、
経営規模の拡大に伴い、着実に増加していることから、
排せつ物の戸当たりの発生量は増加するものと見込まれる。

② 家畜種別排せつ物の処理状況と課題について
次に、その処理状況と課題について伺います。
道内の家畜、いわゆる乳用牛、肉用牛、豚そして鶏、家畜種別によって排せつ物の適切な処理方法や利用促進に向けた課題は異なります。道は、これまで以上に生産性を高めた利用促進を実現させていかなければなりません。道によると、現段階で家畜排せつ物の量的処理や処理技術等について困っている状況にはないと聞かされておりますが、現場からは決してそのような状況ではないと聞かされるところです。
家畜種別排せつ物の処理状況と課題について伺います。
<答弁>
・道内において発生する家畜排せつ物のうち、
約9割を占める牛では、堆肥や液肥として、農地に還元されているが、
近年、バイオガスプラントにより
電気や熱に変換して活用する動きもみられ、
平成29年度は、発生量の6%程度が利用されている。
・豚では、堆肥化や浄化処理など、鶏では、肥料等として利用。
・家畜排せつ物の課題としては、牛では、1戸当たりの飼養頭数が増加し、
排せつ物の処理量も増えていることから、
堆肥舎など既存の処理施設の容量不足や、
未熟な堆肥のほ場への散布が見られること、
また、豚では悪臭の発生などがある。
③ たい肥センターについて
次に、たい肥センターについて伺います。
道内の地域によっては、たい肥センターが設置され、排せつ物の有効な利用促進が進められているとお聞きしています。たい肥センターが設置されることになる理由と、それらの現状や課題について伺います。
<答弁>
・道内では、畜産農家と耕種農家が連携を図り、
主に市町村やJAが中心となって、
家畜排せつ物や稲わら、麦かんなどを原料に、
良質な堆肥を効率的に生産する堆肥センターが、
平成29年3月現在、51カ所で設置。
・堆肥センターでは、畜産農家や、耕種農家が堆肥を利用し、
地力の増進を図っているが、
施設の経年劣化による修繕費の負担増や従業員の不足、
農家の離農等に伴い、計画どおり、堆肥の原料が集まらない
などといった課題がある。

④ 本計画の見直しについて
次に、計画の見直しについて伺います。
家畜排せつ物のエネルギー利用促進に向けては、道内市町村や各地の農協、農家の皆さんと情報を共有すると共に、新たな技術開発や導入を実現させていかなければなりません。
特に、家畜排せつ物を「廃棄物」としてではなく、「生産物」として付加価値化させるこによって、農業経営のコストとしてではなく、農業収入源の一つとして対応させていかなければなりません。
既にこれまで取られてきたたい肥化支援の各施策や補助金によって、農業関係者のたい肥化への依存は大きいものとなっていて、エネルギー利用へ振り向けられる関心は薄く、更に、これまでの計画内で触れられているエネルギー利用についての部分は極僅かであるに過ぎません。それらが、これら有効活用拡大の障壁となっていることは事実です。
道が掲げる新エネルギー導入の加速化を推進させていくことにより、道内における農業収益力強化の有効策として、家畜排せつ物のエネルギー利用促進は欠かすことができないものとなるに違いありません。
本計画のエネルギー利用についての積極的な見直しと検討に向けた考え方を伺います。
<答弁>
・道が平成28年3月に策定した本計画は、
国の基本方針等を踏まえ、
家畜排せつ物の管理の適正化や利用促進に向けた
基本的な考え方や推進方向を明らかにしたもの。
令和7年度までの10年間を計画期間。
・計画においては、家畜排せつ物の利用目標の一つとして、
「エネルギーとしての利用の一層の促進」を掲げており、
道内各地でバイオガスプラントによる
エネルギー利用の取組が進められている中で、
来春に改定が予定されている国の基本方針を踏まえつつ、
道としても今後の対応を検討してまいる。
⑤ エネルギー利用の積極的な支援について
この計画によると家畜排せつ物については、たい肥化とエネルギー利用の両立による適正な処理と利用が求められています。しかし、道内では発生量に対して6%程度しかエネルギー利用が実現しておらず、現在、道が掲げる新エネルギー導入の加速化の観点からも、そこに期待される可能性は大きなものがあると見込めます。
計画の中で、規模の拡大によって処理施設の容量が不足し、応急的な対策を余儀なくされている状況がみられるとしているように、圃場の限界に留まらず高齢化や労働力不足なども相まって、たい肥化するにも限界があることを承知しています。
これまで処理高度化施設などへの支援によって適切な処理によるたい肥化を実現してきたように、これからはエネルギー利用に向けた積極的な支援を充実させることにより、発生量の増加が見込まれる排せつ物に対して、生産性が高い有効利用を推進させなければいけません。
知事の見解を伺います。

<答弁>
・近年、畜産農家では、1戸当たりの飼養頭羽数の増加に伴い、
家畜排せつ物の発生量が増えており、
地域からは、貴重な有機質資源やエネルギー源となる
排せつ物の有効活用を図るための支援が求められている。
・道では、良質な堆肥の生産や適切な施肥管理、
地域の実情に応じたエネルギーとしての
一層の利活用を図るとともに、国に対しては、
堆肥舎やバイオガスプラントなどの施設整備等に必要な
予算の確保などについて要請。
・今後とも、家畜排せつ物の有効活用を積極的に推進しながら、
環境負荷の少ない持続可能な酪農・畜産の確立に努めていく。
この課題については、予算特別委員会は基より、引き続き議論を重ねていくことになりました。皆さんに未来であっても事実をお伝えしながら、私たちが携えなければならない覚悟について、朝街頭など様々な機会を通じてお伝えして参ります。
※更に、近日中に動画による質問&答弁も試みたいと考えています。乞うご期待。
————————————————————
A,人口減少がもたらす危機について
最初に、北海道が直面している、人口減少がもたらす危機について伺います。
この質問は、「北海道人口ビジョン」及び「北海道創生総合戦略」によって示されている将来に渡る北海道の姿について、人口動態の捉え方次第では、北海道庁は基より、時に民間企業をも巻き込んだ諸計画に、大きな影響を与えるものとなり、その振れ方によっては、私たちや子供たち、未来に対して余りに大きな衝撃をもたらすことになると考え、知事にお伺いするものです。
敢えて言葉を選ばなければ、この危機の放置は、道内179自治体の存続を危ぶみ、北海道自身の破たんを容認しているとさえ受け取ることができるのです。
よって、以下に幾つか質問をさせていただきながら、私たちが覚悟しなければならない現実を整理した上で、新しい知事に、今後必要な政策及びその見直しを促すものとします。
なお、この質問のベースとなっているのは、本年7月に北海道経済同友会と北海道二十一世紀総合研究所が取りまとめられた「エビデンスから北海道の未来を~北海道経済白書に向けて~」であることを冒頭に紹介しておきます。
皆さんもご承知のように、北海道は、全国一早い人口減少による生産・需要の減少や国際的な観光地としての環境整備、あるいは広域での総合交通体系整備などの課題が山積しています。
特に、戦後に高度経済成長を遂げることができた先人と私たちは、拡大基調によって舵取りしてきたことを、それこそ拡大や成長によって幾つもの世界規模の危機を乗り越えてきたことを、成功体験として記憶しています。
しかし、これまで、先人と私たちが経験してきた成功体験とは大きく異なる現象によって、想像を遥かに上回る社会構造の混乱が既に始まっているのです。そんな縮小基調の中での舵取りがとれだけの痛みを伴い、目先の安易な選択に陥ってしまっていることが、将来に続く子孫たちに、計り知れない重荷を残していくことになるのかを覚悟しなければなりません。
最初に、現在の北海道のエビデンスを俯瞰しておくと、北海道の人口は、528万6千人(2000年対比93%、以下同様)、合計特殊出生率は、1.27(103%)、生産年齢人口は、58.3%(77%)、高齢化率は、30.7%(164%)、総生産額は、19兆181億円(92%)とされています。
僅か20年の変化としては、決して少なくないものと言えることが判ります。

① 人口動態の危機について
まずは、人口動態の危機について伺います。
私は、6年前に初めて朝の街頭に立って以来、北海道の人口が、驚くほどに急激に減ってしまうと訴えています。僅か25~30年の間に、北海道の人口は300万人を切ってしまうさえと訴えています。200万人以上の減少です。実に札幌市1つ分以上の減少です。人数が減るということは、伴って私たちの生産力が、消費力が、経済力が失われていくことを意味します。いわゆる「北海道の元気」が失われてしまうのです。
知事は、北海道の人口減少の現実をどのように捉えているのでしょうか。
維持することを目指すということではなく、現実をどう捉えているのかお聞きします。
<答弁>
・急速に進行する人口減少は、道政が直面する最大のピンチであり、
・様々な産業における担い手の確保
・消費の縮小
・地域交通の維持
・税収減による住民サービスの低下
など、幅広い分野において大きな影響を及ぼすもの
・地域社会の存亡にも関わる大変深刻な状況
② 諸計画の危機について
次に、諸計画の危機について伺います。
道が描く人口の未来像については、2040年には、人口を460~450万人を維持すると「北海道人口ビジョン」等で私たちに示しています。
同時に、そのレポートの中では、社人研が示す419万人という数値を引用することで、ある意味では計画自体に幅を持たせたいのだと、私は推測しています。
では、社人研説を用いて、2040年に419万人、2060年に308万人と覚悟した場合に、道が示してきた諸計画に与える影響はどれ程のものになるのでしょうか。
道が策定してきた諸計画について、社人研ベースの予想値も採用しているのか、その場合の影響はどれほどであるものか、主だった計画で構いません。その差異をお示しください。

<答弁>
・人口ビジョンでは、
2040年に「460万人から450万人の人口を維持する」との
人口の将来見通しと合わせて、
国の推計による2040年に419万人になるとの数値を示す
・各種計画においても、
国の推計を計画策定の基礎資料として取り入れていることから、
その影響はないものと考え
・そうした中、道としては、道民をはじめ、幅広い分野の方々と連携し、
人口減少対策を進めていく
・「460万人から450万人の人口を維持する」という
長期的な展望を現実のものとするよう、
人口の動向を注視しながら、創生総合戦略を推進
③ 必要な覚悟の危機について
次に、必要な覚悟について伺います。
決して避けられない少子化や高齢化は、昨日今日唱えられ出したものではなく、実は30年以上前から様々に説かれてきたことなのです。
しかし、時の為政者が有効な手立てを取ってこなかったのが事実です。私は、目の前の痛みを避けて、未来へと先送りしていただけと捉えています。
この春に新しく就任された知事には、明るく元気で夢や希望の持てる北海道の姿を示して頂くことも必要ですが、それでも未来を生きる子孫の為に相当の覚悟で道民に対して勇気を以って真実を語り、道民全体の覚悟を以って経営資源の<選択と集中>を断行し、未来に渡って勝ち残ることのできる北海道を創り上げていく義務があるのです。知事は、これからの道民の姿をどのように描いていらっしゃるのでしょうか。知事の見解を伺います。
<答弁>
・人口ビジョンにおいて、今後、有効な対策を講じない場合として、
2040年に本道の人口は419万人になるとの国の推計を示す
・全市町村の約半数が、現在の人口の6割以下になるという厳しい分析結果も提示
・次期創生総合戦略の策定にあたり、
・人口減少を巡る環境が依然として厳しい状況にあることを
改めて、道民の皆様とその危機感を様々な機会を通じて共有しながら、
人口減少に立ち向かう
・先人が幾多の困難に挑み乗り越えてきたように、
ひるむことなく勇気を持って「挑戦」
・将来にわたり安心して暮らし続けることのできる北海道づくりに全力で取り組む
④ 道都札幌市の危機について
次に、札幌市の危機について伺います。
先のレポートによると、札幌市の人口減少は独特であり、異質であると分析されています。札幌市の総人口は、まもなくピークを迎え、今後40年かけて減少する見込みとなっています。道内からの流入が続くと同時に、若者の流出が続くことで、2040年には極めて危機的な高齢化に陥ってしまうとされています。
更に、生産年齢人口が52.2%(2000年対比70%)と著しく落ち込み、北海道全体よりも経済・産業活動や雇用環境に大きな影響を及ぼすことになることが判っています。
実に40%を超える高齢化率と、2000年対比で2.6倍もの高齢者数となる現実は、有業率が示すように税収の深刻で大幅な減収を意味し、加えて医療介護費を含む義務的経費等によって、財政状況は危機的状況に陥るとさえ考えられています。
この予測を札幌市がどう捉えているのかは知る由もありませんが、先のレポートでは、札幌市の主力産業の市場は札幌市を含む北海道であり、札幌市を除く北海道の衰退が札幌市経済を直撃してしまう北海道の人口動態を踏まえると、外で稼げる食と観光や情報通信の成長を促すことが必要と論じています。
そのような状況であっても、札幌市が牽引役であることは変わりありません。北海道全体が運命共同体であることは変わらないのであります。
知事は、道市懇等で、相関関係にある札幌市と協力しながら、人口減少に立ち向かう術を、どのような政策を以ってこの難局に対峙しようとしているのか、見解を伺います。
<答弁>
・本道の人口の3分の1以上を占める札幌市との連携は大変重要
・これまでも、
・女性活躍の推進
・首都圏等からの移住
・UIターンの促進
・海外拠点によるアジアマーケットの開拓
など、連携した取組を進めてきたが、
札幌市と道、市町村が連携を更に緊密にして、
北海道全体の魅力を高めていく必要がある
・次期総合戦略の骨子案において、人口減少対策に関する札幌市との連携強化を盛り込み、
例えば、
・大学生や企業人材の交流
・生産から消費に至る経済活動
などを通じ、札幌市と道内各地域とのつながりを深めるといった観点
・具体的な連携方策等について、市と危機感を共有し、協議・検討

⑤ 将来税収の危機について
次に、将来税収の危機について伺います。
先のレポートでも示されているように…、
A,総人口の減少が大きく加速し、今の2倍のペースとなること、
B,年少人口が少なくなり、出生数の向上が非常に重要となること、
C,生産年齢人口が今後20年で82万人減少すること、
とされていて、これらはいずれも今後の産業・経済活動、雇用環境、社会保障に大きな影響を及ぼすことになると論じています。
1996年にピークを迎えた道内総生産20.9兆円は、このところ17~19兆円で推移しています。国レベルでは拡大を続けている現状からすると、全国に比べて回復が遅れていると評価することが出来ます。
更に、2040年には11兆円まで減少すると見込まれています。これは衝撃的な未来の姿なのであります。
そして、これはそのまま税収の減少を意味し、税収が2010年対比で2040年で64%、2060年で45%にまで悪化してしまうことが想定されています。道財政の環境悪化による諸計画の見直しが直ちに必要になることを自覚されています。交付金等による穴埋めは帳尻合わせの絵空事に過ぎないのです。収入が減る以上は将来に渡って支出を「増やせ」「廻せ」は通用しません。縮小の痛みは現実です。これまでの延長で図られる諸政策なのではなく、2040年以降の着地点を見据えた産業シフトの移行、言わば力点や支点を偏向させた諸政策の見直しが必要になってくると考えています。
道の見解を伺います。
<答弁>
・生産年齢人口が減少する本道
・高齢化の進展に伴う非就業者の増加等により、税収が大幅に減収となる一方、
・人口一人あたりの医療費、介護給付費の増加
など、行財政を取り巻く環境が更に悪化することが懸念
・こうした厳しい制約の下で、今後の施策の推進にあたっては、
労働生産性の向上等を図るため、
・AI、IoTや自動運転といったSociety5.0の実現に向けた未来技術の活用や、
・外需の取り込み
など、人口減少にも対応しうる本道の特性を生かした取組が重要
⑥ 数値設定の危機について
次に、数値設定の危機について伺います。
これまで質問してきたことからも、目指す姿を示すことも必要ですが、厳しい現実を道民に示していくことが必要です。
よって、これからの政策決定に用いられる人口設定を始めとした諸数値は、ダブルスタンダードであっても良いのではないでしょうか。縮小基調の中で必要なのは、目指す姿と同時に、「最小達成義務」なのではないかと考えます。道の見解を伺います。
<答弁>
・道では、5年を期間とする総合戦略において、
現状の数値を基準とした各種の数値目標やKPIを設定して取組を進めてきている
・こうした短中期的な見地から設定した数値目標の達成に向け、
毎年度、進捗状況を検証しつつ臨機に必要な見直しを行い、各般の取組を着実に進める
⑦ 必要な政策と見直しの危機について
次に、必要な政策と見直しの危機について伺います。
先のレポートでは、北海道が元気になるために欠かせない絶対条件は、域際収支の改善であると唱えています。それは、他地域に先んじて結果を残すことが出来ている農業、観光、エネルギー等の分野をより成長産業化していくことであるとしています。
これらについては、道によって既に十分に取り組まれてきた産業でもあり、とられてきた政策を推進させていくことは言うまでもありません。
しかし、人口減少と高齢化が想定以上に進んでしまう中で、就業者数の減少は顕著に進んでしまいます。持続的な経済成長を図っていくためには、道内総生産が就業者数と労働生産性に分解できるのであるから、労働生産性の改善が急務であると指摘されているのです。特に、小売り、運輸や建設、そして北海道の戦略産業である観光業の労働生産性の改善が必要であるとしています。
更に、現在、域際収支が大きなマイナスとなっているのは、輸出産業の集積・生産力が全国に比べて見劣りすることが大きな要因となっていて、道外・海外から稼げる産業の発掘、育成、強化が永続的な課題となります。
こうした中で、訪日外国人観光客の急増による道内での消費増加により、サービス輸出は著しく増加しています。そのまま域際収支の改善、道内総生産の増加に寄与しているのです。
道内においては、域際収支に拘った政策の展開によって、民間投資を喚起および呼び込むための戦略的な取組みが、北海道にとって喫緊の課題であると断言できます。
圏域外から稼ぎ出す力である域際収支は、そのまま地方創生の活性を計るバロメーターであるといっても過言ではありません。
知事は、北海道の域際収支の改善についてどのように考えているのでしょうか。
これまでの質問を通しながら、知事が捉えている危機感についてと、その危機に立ち向かう為に必要な政策とその見直しについての展望と見解を伺います。

<答弁>
・本道の強みである食や観光、エネルギーなどの地域資源を活かした産業振興や
インバウンドによる消費拡大など域際収支の改善に寄与する地域経済の活性化
・人口減少下においても、将来にわたり、心豊かに幸せに暮らし続けられる地域の実現
を見据えることも必要
・私としては、
・人口減少が地域に与える様々な課題への対応について道民の皆様と
その危機感をしっかりと共有
・道内179市町村とのスクラムを一層強化
・ 北海道を応援してくださる多くの方々の力も取り込みながら、
北海道創生の実現に向け、全力で取り組む
この質問は、アイヌ施策推進法の適切な実現とウポポイ年間来場者100万人の実現について議論させていただいたものです。
100万人の質問については、開設まで1年を切る中で、その効果を広げていくために避けて通れない「受益者」としての責務について問うと共に、一方で、現実的な目標設定を探る努力も怠ることは出来ないという思いからまとめてみました。
本件につきましては、引き続き注目して参ります。
——————————————————————————————-
【北海道のアイヌ施策の推進について】
まず、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」、以下「アイヌ施策推進法」と言いますが、今年の四月に成立しています。
私は、この質問によって、このこと自体に主義や持論を持ち込む気はありません。
しかし、アイヌ施策推進法によって示された幾つかの点については、関連して道の施策に大きく影響すると考えられることから、以下の質問によって議論を進めたいと思います。
A,アイヌ施策推進法について
アイヌ施策推進法の成立に基づいて、「北海道におけるアイヌ施策を推進するための方針」が定められています。先の委員会で説明され、パブコメが実施されました。
パブコメに寄せられた内容を読むと、実に多様な意見が寄せられていることに安心さえ覚えるところです。
先に示された素案によると、全ての道民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目標としています。
よって、アイヌだけの、アイヌだけによる、アイヌだけの為の新法でないことは明白です。
「相互」、言うなれば、日本国民としてお互いに人格と個性を尊重して共生していくことを目指したものと言えます。
① 「アイヌの人々」について
最初に、アイヌの人々について伺います。
アイヌの人々という定義が曖昧であるが故に、その対象は常にあやふやです。過去の委員会質問等で、その数についても議論してきたとこでありますが、急激に減り続けている実体を不都合として、これまでその表現に苦慮してきたことは明白です。そもそもアイヌ協会が認定することになっている「アイヌの人々」という過程が不適切なのであります。
アイヌの人々の数が減る一方であるのに対して、自らがアイヌであることを自覚しない日本国民を含めた「存在しているはず」の数を対象としたアイヌ施策の推進には、無理と無駄が生じます。
道は、アイヌ施策推進法の成立を契機として、国に対してアイヌ協会に頼らない「アイヌの人々」の精度の高い調査や特定を求めることが必要だと考えます。見解を伺います。
<答弁>
アイヌの人たちの実態把握についてでございますが、道では、道内のアイヌの人たちの生活の実態を把握するため、市町村やアイヌ協会のご協力をいただきながら、昭和47年から8回にわたり、「アイヌ生活実態調査」を実施し、アイヌの人たちの生活向上施策などの推進に努めてきたところでございます。
また、この度のアイヌ施策推進法の審議にあたっては、衆参両院において、アイヌの人々が北海道のみならず全国で生活していることを踏まえて、施策の充実に努めることや、施策の推進に当たっては、アイヌの人々の実態等の把握に努めることなどが附帯決議されており、国の基本方針にも、その旨が盛り込まれているところでございます。
道では、これまで、国に対しまして総合的な施策の推進を求めてきたところであり、今後におきましても、法の目的である共生社会の実現に向けて、国が主体となった先住民族施策としての総合的なアイヌ施策が一層推進されるよう求めてまいる考えでございます。
<指摘>
これまで行われてきた実態調査については、北海道アイヌ協会等の聞き取りが中心となっていて、客観的な調査であるとは言い切れません。むしろバイアスが掛かった調査となってしまうことは、これまで指摘した通りです。アイヌ施策推進法の成立を契機に、未来志向の政策展開を実現していくためには、肝心なところが偏向するのは許されることではないと考えます。決して出来ない相談ではありません。国に対して強く求めていくことを改めて要望しておきます。
② 未来志向について
次に、未来志向という捉え方について伺います。
これまで長きに渡り、アイヌ文化振興法等によって、アイヌの人々に対しては、生活支援や進学支援、生活全般に渡る施策を展開してきました。
しかし、その効果や成果は限定的であり、今回の「アイヌ施策推進法」へと繋がってきたのだと認識しています。
また、生活支援や進学支援については、国民の平均と比較して足りていないことが、繰り返し主張されてきたところでありますが、もはや優遇や配慮に過ぎることが逆差別につながっている段階へと入っていることが憂慮されていることも事実です。
地域によっては、アイヌ民族の意向が十分に反映されていないとの批判があるとお聞きしていますが、自立の可否が問われているとも言える「アイヌ施策推進法」にあっては、地域振興や産業振興などを含めて未来志向によるアイヌ政策を総合的に推進することが強調されていると考えています。
道が想定している「未来志向」のアイヌ施策とは何を指しているのか、見解を伺います。
<答弁>
未来志向によるアイヌ政策についてでございますが、道では、「北海道におけるアイヌ施策を推進するための方針(案)」におきまして、「アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もって全ての道民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する」ことを目標としたところでございます。
道といたしましては、道方針に定める目標の実現に向け、アイヌの人たちの生活向上施策や、本道にとってかけがえのない財産であるアイヌ文化の振興、さらには、将来にわたって輝き続ける北海道の実現に向けて、全道各地域の活性化、産業・観光振興などにも軸足を置いて、総合的なアイヌ施策の推進を図ってまいる考えでございます。
③ 道の方針や市町村の施策推進地域計画について
次に、道の方針や市町村の施策推進地域計画について伺います。
過去の委員会質問等で繰り返してきているように、私は、アイヌ文化の振興は、国や道、自治体が諸手を挙げて取り組むべきものであると考えています。アイヌ文化の振興を通じて、北海道や各地域が「北海道らしさ」を強みとして、観光産業のみならず、まちの元気に仕立て上げることが効果の高い一手であると考えているからでもあります。
アイヌの人々も色々です。アイヌ協会等を通じて新法制定まで努力を積み重ねてきた方もいらっしゃれば、アイヌ協会とは一線を画して活動を続けられる方もいらっしゃいます。いまだ差別を感じて不自由されている方もいれば、そもそも自覚のない方もいらっしゃるものと容易に推定されます。
北海道150年、否、それ以前からの北の大地には、私たちのご先祖様が連綿と繋がれてきた歴史が存在しています。
アイヌ施策推進法が制定された今となっては、アイヌの人々であろうとなかろうと、日本国民として、北海道道民として、活力あふれる元気な北海道の未来ために、新法を通じて何が出来るのか、その覚悟が問われているものと確信しています。
そのような中で、アイヌ施策推進法では、アイヌ民族の要望のみを尊重するためのものではなく、アイヌ文化をきっかけとして、地域振興や産業振興などを含め未来志向による施策の推進による双方の発展を求めているのでありますから、むしろアイヌ文化振興法では表していなかった部分、即ち、地域振興や産業振興などを通じた様々な取り組みが重要視されるべきだと考えています。本年9月中に取り決められる予定の道の方針や、その後市町村によって策定されるアイヌ施策推進地域計画においては、この点における取組に大きな関心が寄せられています。
そもそも道として、どのように考えているのか、どのように国と共に市町村に関わっていく考えであるのか、見解を伺います。
<答弁>
市町村のアイヌ施策推進地域計画についてでございますすが、アイヌ施策推進法では、市町村の地域計画に記載する事項といたしまして、アイヌ文化の保存・継承やアイヌの伝統等の理解促進、観光振興、産業振興、地域交流や国際交流の促進などの事業を掲げているところであり、道方針(案)におきましても、地域振興や産業振興などを含め未来志向によるアイヌ政策を総合的に推進することとしております。
道といたしましては、市町村が地域計画に基づく事業を効果的かつ効率的に実施できるよう、市町村との間で情報交換や協議を行うための場を確保し、国や市町村からの情報収集を行い、また、広域相談員を配置し、アイヌの人たちや地域が抱える課題などを伺いながら、地域の実情に応じた、必要な助言や協力を行うなど、本道におけるアイヌ施策の一層の推進に向けて、市町村の取組を支援してまいります。
④ アイヌ協会等の関わり方について
次に、アイヌ協会等との関わり方について伺います。
地域振興や産業振興などを含めた未来志向によるアイヌ政策を総合的に推進するために使われる交付金や法律の特殊措置については、アイヌ協会等が認定するものでなければならないのかを確認させてください。
北海道内に限らず、日本国内や世界には、アイヌ文化に関わる取組みは多数存在します。むしろ、アイヌ協会等と一線を画して活動する人々の支援に比重を置いて取り組むことが必要だと考えています。企業や地域・個人に至るまで、アイヌ施策推進法の趣旨に沿った多くの取組みがなされることこそが、これまでタブー視されてきた部分にも光が当たり、健全な法の趣旨を実現せしめることに至ることになると確信しています。
この交付金や法律の特例措置について、どのような方針や手続きとなるのかの見解を伺います。
<答弁>
アイヌ政策推進交付金などについてでありますが、アイヌ施策推進法では、総理大臣の認定を受けた地域計画に基づく事業を実施する市町村に対しまして、交付金の交付や、国有林野における林産物の採取、サケの捕獲許可等の配慮など、法律上の特例が定められているところでございます。
また、アイヌ文化の保存・継承などのほか、観光振興や産業振興などの、アイヌ施策の推進に資する事業を実施しようとする者は、市町村に対しまして、地域計画を作成することを提案することができるとされており、今後、市町村によるアイヌ施策が全道各地で積極的に展開され、アイヌ文化の振興や地域の活性化などにつながっていくことが期待されているところでございます。
<指摘>
今の答弁の中で、事業を推進しようとする者とあった「者」の部分ですが、くどいようですが「者」にあたる方々が、アイヌの人たちに限らないことを確認しておきます。
そこには、アイヌの人たちであってもアイヌ協会の非会員であったり、全国の企業・地域・個人が様々に、アイヌ文化を活用した事業について、その方の地元自治体を通じて事業を展開できることとなっていると理解しています。
私に言わせるならば、日本国民が、アイヌ文化を活用した健全な地域振興策に取り組む時に、地元自治体と協力して交付金を活用することができる、と理解することが出来るのです。
ここで、あるアイヌの方のご意見を抜粋して紹介します。
僕は、アイヌ政策の恩恵は受けていません。アイヌ協会の会員じゃないので、何の恩恵も受けません。でも、それが僕なので、恩恵は受けなくても、アイヌ文化を今の社会にリリースし共に共存したいと行動しています。道も国もアイヌを鍛えるべきです。(中略)差別だ何だと訴えて集まって来るだけです。(中略)補助金は生きたまま人を殺します。生きたまま死んでいるアイヌに僕はなりたくない。僕は日本社会の中で、補助金も無しで、ちゃんとアイヌとして、個人として、社会に必要とされ、生きていきたいだけです。アイヌ文化は北海道の社会でキチンと使われていないのです。まだ使える文化になっていない。だから関わる人たちが苦しむのです。僕は北海道のみんなに必要とされる、アイヌ文化のリリースをどうするか考えています。そんな僕なので、アイヌ政策には全く興味がないのです。アイヌ協会の人たちの為の政策です。僕はこれから、誰にも縛られないで、今を生きるアイヌとして、怒りでも恐れでもなく生きていけます。
これは実に重い言葉です。アイヌ協会の皆さんは基より、アイヌ行政に関わる私たちは、真摯に受け止めなければならない言葉だと考えます。
私たちは、何かをはき違えてしまっているのだと感じています。残念ながらその実態を鮮明にすることは出来ていませんが、今回のアイヌ新法の制定によって、一歩でもその実態に近づいていくことを、そして、アイヌ新法が目指す共生社会の実現を果たして参りたいと思うのです。道並びに道議会においても、タブーを恐れずに目標の実現に向けた取り組みが成されることを強く要望しておきます。
B,年間来場者100万人の実現について
次に、ウポポイの年間来場者100万人の実現について伺います。
この質問については、過去に三度、三年に渡り行ってきましたが、残念ながら時間を費やしただけであって、実感できる成果に辿り着けていないと地団駄を踏んでいるところです。
2020年4月24日まで1年をきる中、多くの課題と向き合っている現実を自覚しながらも、行政の限界を感じざるを得ない状態となっています。
① 年間来場者100万人の定義について
最初に、年間来場者100万人の定義について伺います。
これまでの質問で、明確にできていなかった、明確に答弁してこられなかった点です。
年間来場者100万人の対象範囲はどこになるのでしょうか。そして、それは2021年以降も継続されることになるのでしょうか。簡潔な見解を伺います。
<答弁>
来場者目標についてでありますが、目標の考え方につきまして、国に確認したところ、国立アイヌ民族博物館と国立民族共生公園からなる、いわゆる中核区域のほか、慰霊施設への来場者数を想定しているところでございます。
また、ウポポイはアイヌの人々による歴史・伝統・文化等の継承・創造の拠点となるほか、国内外の人々のアイヌに関する理解を促進するための施設でもあることから、開業年度のみならず、翌年度以降も、より一層多くの方々にお越しいただきたいとの考えでございます。
② 年間来場者100万人の実現責任について
次に、その実現の責任の所在について伺います。
私は、これまでの質問で、「主体」は国であって、道や自治体は「実体」であることは申し上げてきたところです。
しかし、これまで道は、「国及び道、北海道アイヌ協会など、関係者の協力のもと」に様々な取組が進められるものと認識していることや、「国やアイヌ協会、アイヌ文化財団、地元白老町などと一体となって」取組を進めると答弁されてきました。更には、応援ネットワーク会議やプロジェクトチームの設置によって、100万人の実現を果たすと答えるに留まっています。果たす責任がどこにあるのか、改めて、道の見解を伺います。
<答弁>
ウポポイについてでありますが、ウポポイは、我が国が誇るべきアイヌ文化を国内外の多様な人々へ発信することを通じ、アイヌ文化を復興・発展させる拠点として、また、我が国の将来に向けて、先住民族の尊厳を尊重し、差別のない多様で豊かな文化をもつ活力ある社会を築いていくための象徴という、重要な意義を有する国家的プロジェクトとして白老町に整備が進められているところでございます。
ウポポイは、本道にとっても、かけがえのない宝になるものであり、道内各地域のアイヌ文化の振興や観光をはじめとした本道全体の活性化につながるものと認識をしております。
このため、施設の設置者である国や運営主体となるアイヌ民族文化財団はもとより、道や地元白老町、道内自治体や企業・団体など関係機関が目標を共有し、オール北海道で実現に向けて取り組むことが重要と考えており、道といたしましても、広域自治体として、しっかりと役割を果たしてまいる考えでございます。
③ 実現に向けての行動について
次に、実現に向けての行動について伺います。
私が捉えているのは、その実現の責任は、関係する全ての方にあるのです。これは不変の事実です。
よって、道にも責任はあります。むしろ、その責任は少なくないものであると言えます。
その責任を果たすための施策が脆弱過ぎると問い続けてきたのであります。それは、今日現在であっても変わりありません。誠に残念です。
何度も言いますが、行政が出来ることを積み重ねた結果で100万人の実現が出来るならば苦労はしないのです。努力が足りていないと根性論で唱えているのではなく、実現されるための道筋が見当外れであることを訴えているのです。
確かに、2020年は東京オリンピック・パラリンピックの開催年であり、訪日外国人の数が更に伸びることは容易に想像できます。2020年程ではないにしても、その後もこれまで同様に順調に推移することになるでしょう。
しかし、100万人をセグメントした資料を要約すると、訪日外国人旅行者が50万人、国内旅行者が43万人(道内31万人、道外12万人)、修学旅行生が7万人、となります。
残念ながら、これらは期待値です。そうなれば良いな~的なものでしかありません。100万人を埋めるための当て込みでしかないと考えています。
何度も求めている説明は、これらの数値を実現されるに足る行動、営業が成されているか、継続されているかです。
道は、実現させるに足る行動や営業が成されているとお考えですか。それは一体どの組織がどのように展開されているのでしょうか。道の見解と共に、具体的に教えてください。
<答弁>
関係機関の取組についてでありますが、ウポポイのプロジェクトの中心となる国や財団においては、広報や準備に向けた体制強化を図りながら、アクセス道路や駐車場の整備をはじめ、アイヌ語や多言語による展示解説や最新のデジタル技術を活用した魅力あるプログラム開発などの準備を進めているほか、全国的な観点からの広報活動を担っているところでございます。
また、白老町では、インフォメーションセンターをはじめとした観光商業ゾーンの整備や町内の周遊ルートづくりなど、地元として、観光客をおもてなす環境整備を進めているところでございます。
道といたしましては、道内や道外、海外といった市場動向を把握しながら、ターゲットに応じた国内外でのPRや、多様なメディアを通じた情報発信に努め、認知度向上を図っているほか、開業後の具体的な誘客につなげるため、関係機関と連携し、教育旅行の誘致や旅行商品の造成に向けた働きかけ、さらには、JR特急列車の増便やバス路線の開設など、交通アクセスの確保に向けて取り組んでいるところでございます。
今後、より一層の取組の加速が必要と考えていることから、先般、担当局長の設置など庁内の体制強化を図ったところであり、開業までの残された期間、関係機関と連携しながら、全庁一丸となって目標達成に向けて取り組んでまいります。
④ ウポポイの入場料とその範囲について
先日、ウポポイの入場料が公表されました。公園及び博物館の入場料は、大人一般1200円とし、団体や年齢による割引の設定がされるようです。ちなみに、中学生以下は当面無料とされています。
この1200円が高いのか安いのかの議論は別にして、私が注目したのはその範囲です。
「公園及び博物館」とされている入場料の対象範囲は博物館を越えて、周辺のエントランス館、学習館や交流ホールを含んだ公園部分も入場料の対象となっています。
これは、周辺住民等が公園内を散歩したり、気軽に立ち寄る機会の逸失に繋がってしまいます。
私は、博物館に加えて、仙台藩白老元陣屋資料館などへの周遊性を高めた上で1200円に設定する方が、100万人の実現及び継続に大きく寄与するものと考えます。
道は、遅まきながらも国と財団に対して申入れを行う必要があると考えます。
見解を伺います。
<答弁>
周辺観光施設との連携などについてでございますが、来場者の目標達成に向けては、国内外からの誘客はもとより、地域の方々にも足を運んでいただくことが重要と認識しております。
白老町では仙台藩白老元陣屋資料館など観光施設と連携して誘客を図る方策や、地域の方々が気軽にウポポイに訪れることができる方策について検討しているところでございます。
道といたしましても白老町と相談しながら、国や財団と協議してまいりたいと考えております。
⑤ 在るべき姿について
次に、実現に向けた「在るべき姿」について伺います。
これも過去の質問の繰り返しになってしまいますが、私は、対象エリアの拡大と実現可能な数値の設定が必要だと考えています。開設まで1年をきった今となっては、それは急務に違いありません。
対象エリアについては、中核施設のみとせず、慰霊施設や関連区域を含めては如何ですか。せめて近隣宿泊施設や日帰り温泉客を加えることに無理はありません。来場者人数についても、過去のピークが87万2千人であったことは承知していますが、直近来場者数は18万9千人にまで落ち込んでいます。期待値で煽るのではなく、必要な行動を積み上げた結果としての数値を設定する必要があります。
100万人という設定が既に閣議決定を経ていることから、2020年の好環境を考慮すると避けることが出来ない数値設定なのかもしれません。しかし、2021年以降については十分に検討が可能です。また、それに向けての必要な行動の積み重ねも可能です。
年間来場者数の適正化と、その継続性の担保が求められます。そして、受益者としての国、道、そして地元白老町は、それから逃れられない責任があることを自覚し、覚悟するべきです。道の見解を伺います。
<答弁>
今後の取組についてでございますが、国におきましては、ウポポイが公開される次年度以降も継続して、多くの方々に訪れていただくことが大切と考えており、道といたしましても、ウポポイがアイヌ文化の振興はもとより、本道観光や経済活性化に向けた牽引役として、大きな役割を担うものと期待をしているところでございます。
このためには、国内外に向けたPRをはじめ、お越しいただく皆さまに満足いただけるよう、交通アクセスなど受入環境の充実を図るとともに、周辺地域との連携が不可欠と考えているところでございます。
今後、来場される顧客ニーズを的確に把握しながら、おもてなしやプログラムの充実を図るなど、継続して来場されるよう長期的な視点に立った、安定した施設運営につきまして、国や財団に対して働きかけを行っていきますとともに、道といたしましても登別や洞爺湖温泉などの観光地や道内のアイヌ文化、さらには、縄文遺跡やむかわ竜など、本道の魅力ある歴史・文化資源との連携を進め、相乗効果を高めながら、オール北海道で継続した取組を進めてまいる考えでございます。
<指摘>
道は、直ちに、国やアイヌ文化財団、地元白老町、応援ネットワーク会議やプロジェクトチームと協力して、現実的な数値と、それに必要な行動の決定を導き出して、国と協議を開始する必要があると考えます。
言うなれば、ウポポイは、観光立国を標榜する北海道にとって、大きなコンテンツの一つです。その評価の行く末が危ぶまれているこの段階で、指を咥えて眺めている訳にはいきません。なにも楽な道を選ぼうと勧めているのではありません。実現可能な数値に見合う予算しかかけられないことは周知の事実です。国立博物館だからと言って本関連予算執行に取り憑かれ過ぎ、本来の目的を見失うことは許されないのだということを明確にしているだけです。
特に、道と地元白老町にとっては、獲得する予算規模に見合う行動の積み重ねが足りていないと考えています。主体が国だからと言って責任逃れに終始するのではなく、受益者として積極的に必要な行動を積み重ねることが大切です。この点は深く理解していただきたいと切望しています。
言ってしまえば、年間来場者数設定の適正化の後に、アイディア豊富で経験十分な民間に委託してしまうことの方が、余程上積みの期待ができるとさえ思うのであります。
開設まで一年はきってしまいましたが、引き続き関心をもって議論を続けたいと思いますので、何卒よろしくお願い致します。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
先日の報道でもあった通り、9月1日午前5時頃、紋別市内藻別川で、紋別アイヌ協会の畠山会長が違法なサケ採捕を行いました。これは、「アイヌ施策推進法(平成31年4月成立)」によって、アイヌ民族の伝統儀式に使用するための採捕として、特別申請を行えば問題なく採捕して頂くことが出来ることとなっています。
しかし、認められてはいない「先住権」や「自己決定権」を振りかざして密漁犯行に及ぶことは、新法成立を目指し活動して来られた全国に住んでいらっしゃるアイヌの人たちや関係者の皆さんにとって誠に迷惑な事件であると断言できます。
よって、環境生活委員会で取り上げ議論させて頂くこととしました。
この件につきましては、引き続き第三回定例会の一般質問で、北海道警察の対応も踏まえた今後の在るべき姿を導き出したいと考えています。
————————————————————————————————-
A,アイヌ総合政策の推進について
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」以下「アイヌ施策推進法」としますが、平成31年4月の成立に伴い、これまでの考え方に、新交付金や各種規制緩和、象徴空間への対応などを加えた新法となっていると承知しています。
そのような中で、9月1日に、紋別市内藻別川で、道の許可を得ずにサケを数十匹採捕した事件が発生したと報道されています。その場で道の職員が中止を求めましたが、紋別アイヌ協会の畠山会長が、9月1日午前5時頃に違反行為に及んだと承知しています。
このような事件が発生したことは、アイヌ施策推進法の成立による未来志向の政策を推し進めていかなければならない私たちにとって、誠に残念なことであると言わざるを得ません。
そこで数点お聞きしておきます。
① 事実関係について
最初に、事実関係についてお聞きします。オホーツク総合振興局の職員がその場に居て中止を求めているとお聞きしています。これまでの経緯を教えて下さい。
<答弁>
(サケ・マス)
・ 水産資源保護法、北海道内水面漁業調整規則で
河川など内水面での採捕禁止
・ アイヌ文化の伝承等を目的とする採捕は、
同規則による特別採捕許可で認めている
(紋別アイヌ協会の会長)
・ 河川でのサケ・マスの採捕は、アイヌ民族の権利であると主張
・ 昨年から許可を受けずに、採捕に及ぼうとしていたため、
道は、再三にわたり、許可申請を行うよう指導
・ 9月1日、同会長ほか1名が、道職員の制止を無視し、
河川において、許可を受けずに、サケ・マスを違法に採捕
・ 道では、この違反行為を現認し、同日付けで紋別警察署に告発
<指摘>
この質問の意見交換の中で、「昨年は道警が立会い、中止を求めて採捕が行われなかったと聞いていて、今年はなぜ道職員に同行することができなかったのかと、また、今回は既に道から告発を受けているとされていますが、今後どのように対応されることになるのか」とお聞きしようとしたところ、道警から答弁を拒否されるという誠に遺憾なこととなりました。道警の犯行を見過ごす状況を放置することは出来ません。この件については、第三回定例会の一般質問で取り上げることと致します。
② 「アイヌ施策推進法」上の特別採捕等について
今年4月に成立した「アイヌ施策推進法」において、特別採捕については、特別採捕の申請を行えば、問題なく採捕して頂くことが出来るとされています。
しかし、紋別アイヌ協会の畠山会長は、先住権や自己決定権など認められていない権利をかざして、特別採捕の申請を拒否して、その場で違反行為に及んだと聞いています。
これは、権利云々の前に、身勝手な行動であり、国内ほとんどのアイヌの人々にとっても迷惑であると断ずることが出来る違反行為だと言わざるを得ません。
このケースにおいては、どうあるべきであったのか、「アイヌ施策推進法」に基づく、道の立場からの解釈を伺います。
<答弁>
(アイヌ施策推進法)
農林水産大臣または都道府県知事は、
市町村の地域計画に記載された内水面サケ採捕事業実施のため、
漁業法及び水産資源保護法による許可が必要とされる場合、
当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をする。
(今回の事案)
・ アイヌ文化の伝承等を目的として行われるサケ・マスの採捕
・ 北海道内水面漁業調整規則による特別採捕の
許可を受けて実施されることが適切
③ 今後の対応について
次に、今後の対応について伺います。
実は、紋別におけるサケの捕獲の違反行為は今年に限ったことではないようです。先ほども述べましたが、昨年は道警が立ち会うことで防止することが出来ましたが、それ以前については定かではありません。
同日、千歳アイヌ協会が行ったアイヌ民族の儀式では、特別採捕の申請が事前に行われており、伝統の漁法でサケの捕獲が実施され、160人もの関係者が集まり、感謝の祈りが奉げられたそうです。
一体、この差は何なのでしょうか。
道及び道警は、紋別アイヌ協会の畠山会長に、今後の無用な違反行為を防ぐために諦めることなく働きかけることが必要です。どのように働き掛けを行うことになるのかを伺います。
更に、「アイヌ施策推進法」の成立には、北海道アイヌ協会が深く関与されています。今回の残念な違反行為について傍観者を決め込んでもらっては困ります。紋別アイヌ協会に限ることなく、道内の各アイヌ協会や各地で伝統の儀式を行う際に、「アイヌ施策推進法」に基づいた諸手続きを取るように周知徹底させる協力を求め、早期に、継続的に実施されるように求めることが必要です。
それぞれに見解を求めます。
<答弁>
・アイヌの伝統的な儀式や漁法の伝承、知識の普及啓発は、
特別採捕許可の目的の一つに位置づけ
(アイヌ文化の伝承等を目的とする採捕)
北海道内水面漁業調整規則による特別採捕許可の
申請を行うよう、引き続き指導
(アイヌ施策推進法に基づく市町村の地域計画に記載される事業)
道アイヌ協会や市町村に対し、必要となる許可手続きを、各地域協会を
はじめとする等に係るアイヌの人たちへの周知について、協力を求めてまいる
<指摘>
今回の事件は、「アイヌ施策推進法」の趣意を翻弄させるものであり、まさに未来志向で取り組もうとする国や道、市町村や関係する企業・地域・個人に対する裏切りとも言える違反行為だと考えています。
一方で、ルールに則った特別採捕の申請については、柔軟な対応を検討する必要もあると考えます。
今回の質問を通じて、北海道アイヌ協会と道内各地アイヌ協会の関係性を知るところとなりましたし、「アイヌ施策推進法」によって目指す姿を邪魔する人たちに、アイヌの人々も居ることを知り、私は誠に残念な思いであります。
私たちは、日本に、北海道に住まう者として、「アイヌ施策推進法」の成立を通して、アイヌ総合政策の推進を実現させなければなりません。
もはや、民族問題としてではなく、地域振興が根底になければ、両者の元気が損なわれていってしまうことになりかねません。
既に、どちらかだけが通ればいいという環境にないことについて、議論の余地はないのです。
「アイヌ施策推進法」にも使われることになった「未来志向」という言葉に、私たちが直面する様々な危機を乗り越えていくために必要な「元気」を含ませなければなりません。
この件につきましては、改めて9日の前日委員会で触れさせていただき、今一度「アイヌ施策推進法」について整理し、優先して取り組むべき課題について議論させて頂きたいと考えています。
これで質問を終わります。ありがとうございました。
この質問は、地域のリーダーの方から要望を頂いた内容を基にして質問させていただいたものです。
私たちの日々の暮らしに広く浸透している「安心・安全どさんこ運動」です。http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/anzen-hp/dosankounndo.htm
更なる広がりを実現させていくことによって、初来目的を達成できるようにしていかなければなりません。
様々な手段を講じながら、多くの道民の皆さんに意識付けを深めていくことによって、安心と安全を身近なものとしていくことを実現させます。
また、このテーマについては、第二回定例会の一般質問と終日委員会で連続して議論を深めて参ります。
ご注目下さい!!
※この質問及び関連質問については、環境生活委員会の植村委員(空知地域選出)に行って頂いております。
————————————————————————————————————————
一 安全・安心どさんこ運動について
先日、滋賀県大津市において、またもや沿道で幼い子どもたちの命が交通事故の犠牲となりました。また、先月28日、川崎市多摩区で児童らが刃物を持った男に次々と刺され、児童の命が突然奪われるという日常では予想も出来ない悲劇的な事件が発生いたしました。近年、通行人などを無差別に狙った通り魔事件は、たびたび発生しております。対策は取られているが、完全に防ぐのは難しいのが実情であります。安全・安心なはずの公共の場が想いの足りない人の考えや身勝手な人の行動で突然にして危険な場所と化してしまう。誰もが起こしてしまうかもしれない交通事故や人として未熟で思いやりのない者が、幸せな人々の人生を一瞬にして最悪なものとしてしまう事故や犯罪を少しでも引き起こさないために私たち北海道議会議員としても使命感と緊張感を持って向き合っていかなければならないと思っております。
そこで、みなさまもご承知のことと思いますが、平成17年から北海道では犯罪のない安全で安心な地域づくりを進めるために道、市町村、道民、地域団体等が共通認識と意識の高揚を図り、防犯活動の促進に努めていくための組織として、北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり推進会議の設置をし、平成20年から道民運動として、安全・安心どさんこ運動を推進しております。そこで、お伺いいたします。
(一) 推進会議の取組状況などについて
推進会議では、運動開始以来、どのような取組を実施してきたのか、また、その取組はどの程度広がってきているのか、安全・安心どさんこ運動の参加団体数や運動資金の推移とあわせてお伺いいたします。
<答弁>
運動の取組状況等についてでありますが
○ 「北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり推進会議」では、
安全で安心な地域づくりを推進するため、道民運動として
展開している「安全・安心どさんこ運動」の普及に向けた広報啓発や
運動への参加の呼びかけなどに加え、防犯活動推進地区を指定して
重点的な活動の促進にも取り組んできたところ。
○ この運動に参加する団体・企業の届出数は、
初年度の289件から平成30年度末には722件と増加している。
参加団体等は82市町村に所在し、
中には、全道で活動する企業等も参加している。
このほか、届出はいただいていないが、
自主的に活動されている団体・個人等も多く、
道内に運動が浸透しているものと考えている。
○ こうした活動を広く周知し、活動の輪を広げるため、
啓発物品の作成などに充てるよう、企業等から協賛金を募っており、
運動開始から本年3月末までの累計額は、
約1,600万円となっている。
(二) 参加企業・団体などの活動状況について
運動への参加数は、平成30年度末までの累計で722件の届出等があったということですが、届出は最初の一度だけ提出し、翌年度以降は提出する仕組みになっていないと承知しておりますが、現在も継続して取り組まれている方々はどのくらいいるのか、また、具体的にはどのような活動が行われているのかお伺いいたします。
<答弁>
届出後の活動状況についてでありますが
○ 「安全・安心どさんこ運動」は、
安全で安心して暮らすことのできる北海道を築いていくことを
趣旨とした道民運動として展開するものであることから、
参加届出をいただいた後には、個々の団体に
自主的な活動をいただいているところ。
○ こうした自主的な活動の参考としていただくため、推進会議では、
「子どもの安全を見守る運動」と「あいさつ・みまもり・たすけあい運動」を
運動の重点推進事項として定め、防犯パトロール、
高齢者宅等への訪問による見守り活動のほか、
地域の除雪ボランティアや環境美化活動など
複数の事例を紹介しているところ。
(三) 運動に関する認識について
ここまで推進会議と安全・安心どさんこ運動の参加企業・団体などの活動状況それぞれについて伺ってまいりましたが、これまでの運動の成果について、道として、どのように受け止めているのかお伺いいたします。
<答弁>
これまでの成果についてでありますが
○ 推進会議では、ポスターやステッカー、カルタ、回覧板等の
さまざま啓発物等を作成し、運動の普及を図ってきたところであり、
賛同する全道規模の店舗や事業所、配送車、
その他の各種施設等にステッカー等が掲示されており、
運動の周知が図られてきたものと考えている。
○ また、企業・団体により、自主的に防犯啓発物等の作成や、
運動名を入れた腕章等を着用してのパトロール活動、
商品の配送時の見守りマニュアルの作成や実践など、
独自の活動も見受けられるところ。
○ こうした取組などから、道内において運動が浸透するとともに、
安全安心に向けた意識の醸成につながっているものと考える。
(四) 安全・安心どさんこ運動に関する推進会議の役割について
これまでの御答弁をお聞かせいただきまして、運動が10年以上経過して着実に広がりを見せている部分があると理解する反面、運動の範囲が道内市町村のまだ半分にとどまっているということと、初期に参加届を提出している団体がその後継続的に活動を展開されているのか把握できていないという点においては、これからの活動団体との連携のあり方や推進会議のさらなる推進力を求めていきたいところでもあると考えます。
そこで、さらなる活動の促進を図るために、ひとつの事例を紹介させていただきます。
ひまわりの絆プロジェクトといいまして、平成23年に京都府内の当時4歳だった男の子が、交通事故の犠牲となり、生前大切に育てていたひまわりの種をご遺族から警察官が引き継ぎ、全国各地でその種を広め、きれいに咲くひまわりを見ることがなく亡くなった男の子の生きた証を残したいとする遺族への支援とともに、命の大切さと交通事故防止を伝えていくために「ひまわりの絆プロジェクト」がはじまりました。
その活動の一端が、北海道警察内においても、取り組まれており、ひまわりを咲かせ、種を取り、近郊の学校や子どもの施設に配布しており、広がりを見せております。
このように、さまざまな活動があると思われますが、安全・安心どさんこ運動を推進する上での推進会議の役割について、道の考えをお伺いいたします。
<答弁>
推進会議の役割についてでありますが
○ 「安全・安心どさんこ運動」は、
道内で行われている企業・団体のさまざまな活動を
道民が心豊かに安全で安心して暮らすことのできる
北海道の実現という、統一した意識のもとに進めていくもの。
○ 推進会議は、
運動が地域に根差した幅広い道民運動として展開されるよう、
自治体、事業者、道民及び関係機関・団体と連携しながら、
組織の特性を生かして運動の普及促進を図っていくことが
役割となっており、
多様化する犯罪や交通事故などその時々の社会情勢も踏まえた
活動にも取り組むもの。
(五) 今後の展望について
先程「ひまわりの絆プロジェクト」についてご紹介いたしましたが、更なるどさんこ運動の促進の働きかけとして、安全・安心どさんこ運動の取組のひとつに「ひまわりの絆プロジェクト」を加え、「どさんこひまわり絆プロジェクト」という名称で活動を広めていくと効果的であると思います。
北海道には、花いっぱい運動や各市町村において、植花活動を推進している団体も多いことから、運動の理解も合わせていただくきっかけや、これまで理解が得られなかった方面においても、違った角度で広がりを持てることが期待できるのではないでしょうか?また、ひまわりと言えばひまわりの里北竜町といったひまわりでまちおこしをしているところもあり、それらの団体とも連携を図ることで、地域の美化活動とともに交通安全の意識も広がりを見せることにつながるのではないかと思います。
更に北海道の開花の時期は限られることから、ひまわりカラーを基調とした交通安全、犯罪防止のグッズなどをさらに増やしていくこともご検討いただきたく思います。黄色で特徴的な地域づくりを発信している代表格として、夕張市の幸福の黄色いハンカチがございます。今では、夕張市内では、このハンカチを販売して、その収益の一部を福祉施設などに寄付をしている活動も展開されているということです。これを夕張市内だけに留めずに、ハンカチにひまわりのプリントを施すなど、一年を通じてどさんこひまわり絆プロジェクトと一体となって、全道各地に展開をしていく可能性などさらに地域連携を進めることがどさんこ運動を広めることに繋がっていく と思います。
「どさんこひまわり絆プロジェクト」などの取組を安全・安心どさんこ運動の取組のひとつとして進めていくこと、更に、今後運動をどのように展開していくのかについて、部長の考えをお伺いいたします。
<答弁>
どさんこ運動の今後の展開についてでありますが
○ 住みよい地域づくりのためには、
道民の皆さん一人ひとりが具体的な活動に取り組むことが
重要であり、「安全・安心どさんこ運動」は、
こうした活動を社会に広めていくための運動として展開。
○ 委員からご提案のありました、
「どさんこひまわり絆プロジェクト」と関連する取組については、
今後、推進会議に諮ることを検討してまいる。
○ 地域の安全安心をおびやかす事件が連続しているが、
道としては、道民一人ひとりが地域の安全安心に関心を持ち、
参加していただける運動を推進することで、
「人・地域・社会の絆」を深め、
犯罪のない安全で安心な地域を構築してまいる考え。
<指摘>
今、熱心に活動されている団体の様子を伺っておりますが、メンバーの高齢化、後継者の問題や活動費の工面についての課題が直面しているようでございます。どの団体においてもそういった事態が考えられる時代背景でございますが、北海道の広大な地域を安全、安心に暮らすための最も基本の考え方としましても、住民の方々が自分たちの地域をどのように守っていくかといった意識の強化や日頃の運動の習慣が必要だと思っております。
ただ今、推進協議会のこれからの役割についてのご答弁におきまして、多様化する犯罪や交通事故などにその時々の社会情勢も踏まえた活動に取り組んでいただくということでございましたので、私自身もさらに日頃から地域の状況を把握させていただきながら、ともに運動に参画するつもりでいきたいと思っているとともに、これからの推進会議が、各地域の活動団体のみなさまとさらに連携を図り、活動意欲促進のための働きかけなど運動の取り組みに力を注いでいただくこととご期待しているところでございますので、何卒よろしくお願いいたします。
来る7月11日木曜日午後6時半から、札幌サンプラザにて、令和元年 感謝の集い が開催されます。
目下、皆さまにご案内状をお送りする作業中です。
発送後、皆さまの下に馳せ参じまして、参加のお誘いをさせて頂く予定です。
例年の「新春の集い」同様に、道政報告会の後に参加頂いた皆さまと近しく楽しい時を過ごさせて頂きたいと考えております。
早速にでも弊所までお問い合せ頂きましたら詳細をお知らせ申し上げます。
特に、新しく鈴木修道知事を北海道のリーダーとして迎えた私たちが、どのようにして北海道の元気な未来を創り出していくのかを問われる段階となっています。
道政上の課題を整理して参るとともに、その施策としての政策を、積極的に北海道議会の場で議論して参ります。
また、北の元気玉は、行動を通して、直接的に北海道の元気のために働いて参るとお約束してきましたので、有言実行、このような機会を通して、皆さまに政策。施策をお示しして参りたいと考えています。
どうぞ奮ってご参加いただけますようにお願いいたします。
北の元気玉 道見やすのり 拝
来る6月22日土曜日午前8時半から、東茨戸パークゴルフ場にて、第五回 北の元気玉杯 親睦パークゴルフ大会が開催されます。
天気が心配される状況ですが、雨天決行となっております。
既に募集を済ませ、組合せ等準備に余念がないところではございますが、まだまだ参加申込みも受け付けております。
お友達をお誘いあわせの上で、ご参加いただけますようにお願い申し上げます。
平成31年3月10日日曜日、午後6時から、太平百合が原地区センターにて、道見やすのり選挙対策本部総決起集会を開催させて頂きます。
当日は、高橋はるみ知事、鈴木直道北海道知事選挙候補予定者をはじめとして、多くの弁士と支援者の皆さまにお集まりいただき開催させて頂きます。
告示まで残すところ25日間、瞬時も立ち止まることなく戦い抜きます!
必ずや大願成就を果たし、再び北海道道政へと送り出していただき、皆さまとお約束させて頂いた
「北海道に元気を取り戻すため」に、
「北海道を強くするため」に、
「皆さんの暮らしに元気をお届けするため」に、
「あなたの暮らしに元気をお届けするため」に、北の元気玉は働く覚悟でございます。
万障お繰り合わせの上で、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
北の元気 道見やすのり 拝
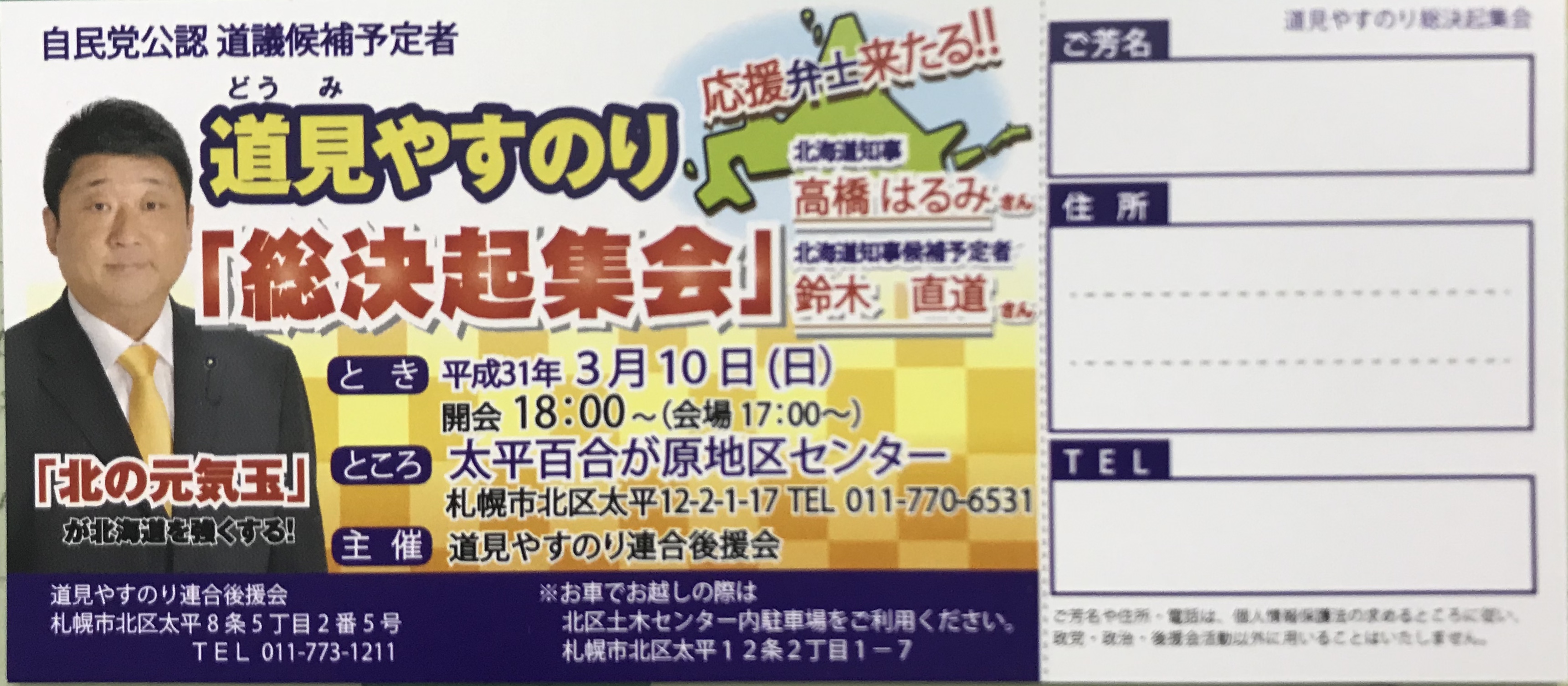
平成30年12月15日午前11時、道見やすのり連合後援会 選挙対策本部「事務所開き」を開催させて頂きました。
北海道の元気を取り戻すための、北海道を強くする為の戦いが、いよいよ始まります。
道見やすのり道議会議員が、皆さんにお約束している政策を実現させるためにも、この戦いは決して負けることは出来ません。

4年前の12月14日、重信先生がお使いになっていた縁起の良い同じ場所で「事務所開き」を開催させて頂いたことを思い返します。
「事務所開き」のご案内を差し上げたところ、多くの皆さまにお集まりいただくこととなり、道見やすのり道議会議員も身の引き締まる思いであったことと思います。

道見やすのり連合後援会女性部の皆さんの「熱い想い」と「元気」が詰まった「必勝千羽鶴」が道見やすのり道議と奥様に贈られました。

青柳史匡連合後援会会長からのご挨拶です。

加藤欽也青見会会長からのご挨拶です。

前回に引き続き、鶴見選挙対策本部長が陣頭指揮を執られます。



「事務所開き」の締めとして小田拓志事務局長によって、参加された皆様と必勝を期して「頑張ろうコール」を三唱させていただきました。

以前にもまして、皆様からの熱いご支援ご声援をお寄せいただきますようにお願い致します。
平成30年第4回定例会 一般質問
●新エネルギー導入の加速化について
新エネルギー導入の加速化については、会派や定例会、委員会を問わず、様々に議論されてきたところでありますが、今回は、私が民間と実際に取り組みながら、具体的に感じた課題や問題点などを引き合いに出しながら質問を展開します。

① エネルギー地産地消スタートアップ支援事業について
(1)支援事業の状況について
まず、「エネルギー地産地消スタートアップ支援事業」の状況について伺います。
道は、昨年度の「新エネルギー導入加速コーディネート事業」に続き、本年度「エネルギー地産地消スタートアップ支援事業」を行っています。
まず、本事業のこれまでの経過と、本年度事業の状況について伺うと共に、成果について伺います。
<答弁>
地域に対する支援事業についてでありますが
〇 道では、身近な地域で自立的に確保が可能なエネルギー資源を
効果的に活用する取組が、より一層、道内各地で進められるよう
エネルギーの地産地消に関するコーディネーターを
希望する市町村に派遣し、必要な助言や情報提供を行っているところであり、
昨年度は14市町村に対し、今年度は、これまでに10市町村への派遣を実施し、
引き続き、派遣要請を受け付けているところ。
〇 これまでの派遣により、調査資料の作成や地域の合意形成に向けた支援を行い、
八雲町では新エネルギー導入に向けた設計に着手するといった
市町村の取組が促進されているところ。
(2)市町村の実態について
次に、調査対象となっている市町村の実態について伺います。
市町村が具体的な取組みに至れない理由は、昨年度のコーディネート事業のアンケート結果からも判明しているように、資金不足と人材不足であることは明白です。
よって、道庁が自治体のみを相手に、いくら調査を続けて「つもり」を把握できたとしても、それが事業となって実現していくまでに至るには、遠回りな時間と労力が必要となってしまっているのではないでしょうか。見解を伺います。
<答弁>
市町村に対する取組についてでありますが
○ 道が行った、アンケート調査では、
9割以上の市町村が補助金など費用面での支援を望み、
4割以上が専門人材の派遣などを望んでいるところであり、
また、市町村からの聞き取りによると、
導入検討を行う際の相談相手が分からないといった、
専門人材の不足を挙げる例が多かったところ。
〇 道としては、こうした課題の解決に向け、
市町村に対し、先進事例など必要な情報の提供や
事業推進に向けた専門的な知見に基づく助言を行うなどして
事業の掘り起こしを図っているところであり
こうした支援を通じ、身近な地域で自立的に確保できる
エネルギーの効果的な活用に向け、市町村が企業と連携して
取り組んでいけるよう、努めてまいる。

(3)事業の対象について
次に、この事業の対象について伺います。
本事業は、自治体またはコンソーシアムが対象となっていますが、いま申し上げた通りに、自治体が新エネルギー事業に着手していくために必要な資金と人材は民間に在るのであって、この民間力をいかに活用できるのかが加速化のポイントになると考えます。
よって、本事業の役割は、自治体やコンソーシアムの意向調査に留まることなく、それらと新エネルギー事業を予定する民間事業者への意向調査を広く求め、それらをマッチングさせることによって、具体的な事業の実現を果たすことができるようになります。
知事は、本事業の対象者に民間企業を加えて、それらをマッチングさせることを事業の柱とすることで、より着手しやすい環境を生み出さなければなりません。
今回の提案についての見解を伺います。
<答弁>
新エネルギーの導入促進についてでありますが
〇 エネルギーの地産地消を推進するためには、
地域において自立的に確保が可能なエネルギー資源の
効果的な活用に向けて、民間企業の持つノウハウを活かすとともに、
地域が一体となって取り組むことが必要。
〇 このため、道では「地域新エネルギー導入コーディネーター」の
派遣により、市町村を中心に民間企業や団体を含む
コンソーシアムなどへの支援を行っているところであり、
本事業の実施にあたっては民間団体などを通じた周知を行い、
積極的な活用を促しているもの。
〇 道としては、本事業によるコーディネーターの助言を通じて、
民間企業を含めた、地域におけるエネルギー地産地消の取組の
掘り起こしなどに努めるほか、市町村に対し、民間企業の情報提供や
意見交換を行うなど、民間事業者の幅広い参入を促進しながら
新エネルギーの導入加速化を図ってまいる考え。
② エネルギー地産地消事業化モデル支援事業について
次に、「エネルギー地産地消事業化モデル支援事業」について伺います。
道は、平成28年度に新エネルギー導入加速化基金を創設して、その財源を基として、平成29年度から、エネルギー地産地消モデル事業に取組み、これまでに5カ所の事業を採択してきました。
まず、本事業のスキームについて伺います。この事業の補助は、事業期間5年以内で、総額5億円とされています。
この事業は、モデル事業であるからこそ、さまざまなトライ&エラーを繰り返すことのできるものであらなければならず、道が高い確実性を求めるならば、それは「モデル」である必要はありません。
例えば、特定目的会社などの事業体が、使い勝手の良いモデル事業の補助金として、市町村に拠出することを前提とするならば、特定目的会社が必要とする用地代金や後の固定資産税等の減免資金として使うことが出来るように設えて、支給金額も1億円程度に圧縮することで、採択件数を増やすことの方が、本事業の目的である「導入の加速化」に資することになると考えています。次年度以降に向けた、事業の見直しが必要です。知事の見解を伺います。
<答弁>
モデル事業についてでありますが
○ 地産地消を促進するためには、地域における需要に
見合った事業規模や効率的な設備設計などの検討をもとに
地域が一体となって取組を進めることが必要。
○ こうした事業化に至るまで時間を要する
エネルギーの地産地消の取組を促進するため、
道では、地域の特性に応じたエネルギー資源を効果的・効率的に利用し、
エネルギーの地産地消の事業化に向けたモデルとなる取組に対し、
複数年にわたり、継続的な支援を行っているところであり、
こうしたモデル事業の推進とともに、
設計や設備導入など取組の段階に応じた支援を行うなど
地域や企業の皆様と連携しながら、
エネルギーの地産地消の取組を全道に広げてまいる。
③ 自治体の現状について
次に、道内自治体の現状について伺います。
新エネルギー導入に向けて、地域が抱える課題は様々です。その地域資源を活用し、その地域の産業となり得る仕組みを構築しなければなりません。
政策メニューとしての「新エネルギー導入の加速化」については、国や道によって優先順位高い政策として取り上げられ、交付金や補助金が付き易く、自治体にとって手の出しやすい政策であると捉えられています。
一方で、過去にその地域で起きた環境問題や新エネルギー事業に対する失敗や破たん例などが、ブレーキを踏ませてしまっていることも強く感じたところです。
自治体は、地域をまとめることができません。いわゆる「よそ者」に対する反応は、必ずしも歓迎の雰囲気になるとは限らないからです。
先見の明がある首長自らが、先頭に立って政策をけん引する場合はまだしも、持ち込まれた施策として石橋を叩いても渡らない自治体をその気にさせていくことは、かなりハードルの高い作業となります。
道もそうであるように、自治体でも部局を渡る政策・施策に対する縦割りな行政体質が、更にハードルを高くしていることも事実です。
知事は、この現状をどのように捉えていて、自治体と一緒にどのように政策を更に推進させていく考えであるのか、また、必要とされる人材をどのように確保していく考えであるのか、見解を伺います。

<答弁>
新エネルギー導入に係る自治体の状況についてでありますが
○ 道内には、エネルギー資源に恵まれていながら
必要な専門人材の不足や、相談先が分からないなどの理由で
新エネルギー導入に向けた具体的な取組に至らない市町村もあり、
地域の取組を促進するためには、専門人材の関与が必要と認識。
〇 このため、道では、希望する市町村に対し、
「地域新エネルギー導入コーディネーター」を派遣し、
エネルギー地産地消にかかる事業計画の策定や
地域の連携体制の構築などの支援を行っており、
地域省エネ新エネ導入推進会議やセミナーなどを活用し、
地域の人材のノウハウ習得と交流促進に努めているところ。
〇 今後とも、こうした取組を通じて、
地域における専門人材が育まれるよう取り組んでまいる。
④ 民間力の活用について
次に、民間力の活用について伺います。
これまで述べたように、新エネルギー事業に対する膨大な知見や経験は、民間にあるのです。国内に限らず欧州を先進とした世界に、実に興味深い実例が存在しています。
国内における北海道の位置付けは、知事も「新エネルギー源の宝庫」として自負しているように、優位性が保たれているように、私も感じていましたが、視野を広げ、国内や世界の先進技術やビジネスモデルの視察等を通して学ぶと、むしろ道内における新エネルギー事業は、孤立した環境、いわゆる「ガラパゴス化」しているように思えてくるのです。
新エネルギー源に恵まれているからこそ、知恵や努力が足りなくなってしまっているのが、北海道の現実であることを思い知らされています。
国内や世界の新エネルギー事業に対する市場の投資欲は衰えていません。道内においても民間による多くの取組みや、旺盛な模索例をよく耳にします。
新エネルギー事業に必要な設備費は決して少ないものではなく、中小規模事業者が安易に取り組めるものではありません。
まして、系統接続の容量が極端に限られている道内事情にあっては、事業着手に欠かせない三種の神器と言われている用地と地域資源は用意できても、送配電線との接続がままならず、意欲はあっても断念せざるを得ない例を山ほど見聞きしてきました。
自治体の積極的な本政策への着手を果たしていく為には、道によって、いかに民間が参入しやすい環境を整えていくかが鍵となります。
これまで質問してきた内容も踏まえて、各事業の見直し、そして実質的な導入の加速化を実現させなければなりません。必要とされている視点を見定めた上で、事業の見直しが必要です。知事の見解を伺います。
<答弁>
新エネルギー導入に向けた取組についてでありますが
○ 本道に豊富に賦存するさまざまなエネルギーを活用し、
活力ある地域社会の実現に寄与していくことは重要であり、
新エネルギー導入加速化基金を活用し、
民間のノウハウも活かした事業の推進を図るため、
市町村のほか、市町村と団体、民間企業を含む
コンソーシアムに対して支援しているところ。
○ 道としては、自立的に確保できるエネルギー資源を、
熱や電気など多面的に利用する多様なモデルの創出を図るなど
本道における新エネルギーの効果的な活用に向け、
事業メニューの工夫なども行いながら、
地域や企業の皆様と連携した取組を進めてまいる考え。
⑤ 系統接続について
次に、系統接続について伺います。
北海道内の系統接続状況については、道央圏の一部に限って系統接続が可能となっているのみで、道内のほぼ全域に渡って系統接続が出来ない状況が続いています。
これらの接続可否については、基本的に、北海道電力のホームページ等で公開されている地域別の「系統接続空容量一覧表」を参考にしながら、その接続箇所を担当する北海道電力の支店等で確認することとなります。
しかし、その一覧表に表されている空容量は特別高圧連系のものであり、高圧連系については「事前相談」の申し込みによって初めて知らされるものであり、事業者が事業検討をするにあたって右往左往しなければならないことが課題となっています。
また、本年10月1日から系統空容量一覧表の書式が全国的に変更されていて、改善は認められるものの、未だに道内における新エネルギー導入の加速化にとって、大きな障害になっていることは明らかです。
そのような中で、本年10月の報道によると、経済産業省は、再生可能エネルギーの核となっている太陽光発電の「固定価格買取制度」を大幅に見直すことを発表しています。

(1)空き容量の情報公開について
まず、空容量の情報公開の方法について伺います。
先ほど述べた空容量の情報公開の方法や事業着手を諦めた業者が放棄した容量については、早い者勝ちの状態で引き渡されているのが現状です。
これでは、いつまで経っても道内における新エネルギー導入の加速化が、鈍化したままとなってしまいます。
道は、国と北海道電力と協議を進めながら、事業者にとって分かりやすい空容量情報の公開を目指すことが必要です。見解を伺います。
<答弁>
送電線の空容量の情報についてでありますが
○ 国では、電力系統を利用している発電設備設置者にとって、
系統に関する情報は極めて重要との考えに基づき
「系統情報の公表の考え方」を示しているところであり、
北電においても、この「考え方」に基づき、ホームページにおいて
系統接続検討における参考資料として、
「系統空容量マップ」と「系統空容量一覧表」を公開し
現在、道内の多くの地域において
系統接続に必要な空容量がないとしているところ。
○ 道としては、新エネルギーの導入に取り組もうとする
事業者に送電線の空容量に関する情報を
分かりやすく提供することは重要と考えており、今後とも北電に対し、
空容量の情報公開を的確に行うよう求めてまいる。
(2)空き容量の有効活用について
次に、空容量の有効活用について伺います。
空き容量情報について、なかなか適切な情報が掴めない事業者に、公正で公平な機会を提供する役割が道にあると考えています。
よって、系統別の空容量と今後の国の方針や、事業着手断念によって出てくる空容量について、北海道電力任せにするのではなく、国と道も加わって一括管理し、系統接続権を先ほど論じたスタートアップ支援事業等で、その地域の市町村と民間企業等をつなぐことにより、導入の加速化を実現していくことが出来ます。
例えば、私に言わせれば、その系統接続権を入札によって分配することができるのではないでしょうか。その落札金額については、北海道新エネルギー導入加速化基金に繰り入れて、道内における導入の拡大につなげることが出来ればよいと考えています。
入札については別の議論を待つことになりますが、少なくとも北海道電力だけに任せて、早い者勝ちにしておくことは好ましい状態とは言えません。見解を伺います。
<答弁>
新エネルギーの導入拡大についてでありますが
○ 本道では、メガソーラーに関する事業計画が急速に進む中、
多くの地域で、系統接続に必要な送電線の容量が不足しているところ。
○ このため、道では、系統容量の確保に向け、国に対し、
太陽光などFIT認定済み未稼働案件の見直しなどを求める、
地域資源を活用しながら取り組む出力変動の少ないバイオマス発電などの
優先接続に向けた制度の早急な整備を働きかけているところ。
○ 加えて、本道の豊富で多様なエネルギー資源が、
我が国全体のエネルギーミックスの実現にも貢献しうる
との観点から北本連系線をはじめとする送電インフラの整備などを
国に要請するとともに、北電に対し電力の安定供給と
系統接続などをはじめ、再エネへの積極的な取組を求め、引き続き
本道における新エネルギーの導入拡大に向けて取り組んでまいる。

⑥ 企業局による新エネルギー事業への取組みについて
次に、企業局による取組みについて伺います。
企業局では、水力発電による電気事業と工業用水道事業に取り組んでいることを承知しています。
私は、より積極的に事業展開を図るべきであると考えたところですし、その機会に恵まれていることを自覚しなければいけません。企業局は、自身でより稼ぎ出すことに注力することが必要です。企業局が抱える工業用水道事業における累積赤字は深刻さを増していて、将来的に発生することが避けられない管渠や管路、浄水場等の更新や改修といった資産的投資についても、膨大な費用が見込まれているところであって、それらの費用の工面に四苦八苦していることは自明です。
(1)積極的な事業展開について
まず、企業局による事業展開について伺います。
企業局が、自ら財源を確保する手段として事業の展開を図ることは、ひっ迫する道財政の負担軽減に直結することであり、なんら引き留められる理由が見当たらないのだと考えています。
あくまでも地方公営企業法の枠の中で、新エネルギー事業に取り組むこと、地域電源や地域資源の活用により、公的使命を果たすことが出来るように、固定価格買取制度を活用した電気事業や水道事業の展開を図ることが必要です。
その中でも、小水力やバイオマスなど比較的安定した、定格で稼働が可能な発電事業に取り組む考えはないのでしょうか。見解を伺います。
<答弁>
企業局による事業の展開についてでありますが
○ これまで、企業局では、
道内への電力の安定供給の一端を担うため電気事業を運営するとともに、
産業のインフラとして工業用水を安定的に供給するため
工業用水道事業の運営を行ってきたところ。
○ こうした中、電気事業については、固定価格買取制度いわゆるFITを活用し、
当面は安定的な収益を確保することが見込めるものの、工業用水道事業については、
需要の減少などにより厳しい経営状況となっているところ。
○ このため、企業局としては、将来に向け、
より安定した経営基盤を確立するため、
電気事業については、引き続きFITを有効に活用し、
FITの適用を見込むことができる新たな電源開発についても
検討するなどして安定経営に取り組んでまいるとともに、
工業用水道事業については、より一層の収益の確保に向け
電気、工水両事業の連携なども視野に入れながら、これまで取り組んでいなかった
新たな分野についても研究を進める必要があると考える。
(2)熱エネルギーの活用について
次に、熱エネルギーの活用について伺います。
もともと水道事業で水資源を取り扱うことに慣れている企業局だからこそ、着手しやすいものに熱エネルギーがあります。発電時に発生する膨大な熱エネルギーを、水で転換して売熱することが可能です。熱エネルギーは、さまざまな施設で使用されていて、現状では化石燃料によって生み出されているものと承知しています。それを転換していくことも環境保全の観点から推奨されるべきことだと考えています。工業用水道事業を行っている工業団地内には、さまざまな企業が立地されています。顧客は既に存在しています。
バイオマス発電などよって生み出した電力を固定価格買取制度で販売し、同時に生み出されている熱力で工業用水を媒介とした熱エネルギーを隣接する企業に販売することが可能です。
是非にも、取り組んでいただきたいビジネスモデルであると考えていますが、見解を伺います。
<答弁>
熱エネルギーの活用についてでありますが
○ 現在、道内においては、上士幌町での家畜糞尿を主体とした
バイオガスによる電気・熱供給や、南富良野町での、
木質バイオマスによるバイナリー発電と熱供給など
地域の再生可能エネルギーを利用した
熱の有効活用を図る取組が進められていると承知しているところ。
○ 企業局としては、今後とも持続的な経営を行いながら、
再生可能エネルギーの利用を推進していくためには、
これまで取り入れていなかった熱エネルギーの活用について、
検討することも重要であると考えており、
今後、事業への導入可能性について検討するため、
まずは、これらの取組をはじめ、様々な事例について、
情報収集に取り組んでまいりたい。
(3)企業局の新たな役割について
次に、企業局の新たな役割について伺います。
私は、賦存していても活用できていない木質資源の代用として、畜産糞尿や食品残渣から製造できる発熱電向けのバイオマス燃料の製造など、ガラパゴス化が進んでしまっている道内の新エネルギー向け技術に、新たな活路を見い出す役割も、企業局にあるものと考えています。
例えば、畜産バイオマス発熱電に必要なメタンガスは、運搬することが出来ないために、酪農家などの原料調達先から、そう遠くないところでの場所を選択するしか出来ませんでした。
一方で、道央を中心とした都市部でしか系統接続は実現できませんが、そうしたところでは環境や臭気の課題などが付きまとい、事業の実現になかなか到達できない例が、山ほどあったことを承知しています。
しかし、私が先日視察してきた最新の技術によると、畜産糞尿や食品残渣、道路脇の雑草や街路樹を剪定した枝葉、さらに木質バイオマス資源として不向きとされるバークでさえも、バイオマス発熱電原料として加工することが可能であることが判りました。その原料はほぼ無臭化することができて、運搬することも可能です。この技術は、はっきり言って驚きでした。
さらに、既に固定価格買取制度で事業着手されていて、間伐材や未利用材などの木質原料確保に苦慮し、一般材や廃材、化石燃料混合を原料としている事業者が、この原料を使用する手続きを済ませることで、電力の販売価格が1.6~2.2倍程度にまで改善させることができることを確認しています。言わばこれは道内における革命にも等しい技術であると捉えています。
いま紹介した新技術に留まることなく、工業試験場と連携することで、北海道に世界の技術を取り込み、稼ぎ出す役割が企業局にはあると考えています。見解を伺います。
<答弁>
企業局の役割についてでありますが
○ 企業局では、自らが、電力を安定的に供給することはもとより、
発電事業を通じて培った技術やノウハウを活用した
地域の再生可能エネルギーの普及促進に取り組んできたところ。
〇 そうした中、増大する自然災害や環境保全の要請など、
近年の社会情勢の変化にも適切に対応するためには、
再生可能エネルギーの普及促進のための
新たな技術や当局が取り入れていない既存技術などを
活用していくことも必要であると考えており、
企業局としては、今後、こうしたことについて、
専門的な知識を有する試験研究機関などとも連携しながら、
調査研究を行ってまいりたい。

(4)企業局が稼ぐ仕組みの必要性について
次に、企業局が稼がなければならない理由について伺っておきます。
これまで述べた中でも触れていますが、更新や改修に必要な費用や、赤字の総額は明確になっています。
しかし、その全てを税金で賄っていくほど道財政に余裕はありません。
まさしく、企業局が自ら稼ぎ出して、それらに投資していかなければならないのです。
よって、その全てではないにしても、しっかりとした計画や目標を持って、その必要額を稼ぎ出していくことを求めているのです。
企業局はその使命を果たすために、地方公営企業法の枠の中で、胸を張って事業展開を実現させることが必要です。公営企業管理者の見解を伺います。
<答弁>
今後の事業展開についてでありますが
○ 近年、企業局を取り巻く経営環境は、
電力システム改革や産業構造の変化などによる水需要の減少、
施設の老朽化や耐震化に伴う更新投資の増大など、一層厳しさを増しており、
安定した事業運営を行うためには、収益性の向上をはじめ、経営基盤の強化などを進め、
議員ご提案のとおり、まさに稼ぐことが重要であると考える。
○ 一方で、再生可能エネルギーの普及促進に向けては、
企業局自らが新たな事業に取り組むことも重要であると考えている。
○ このため、企業局としては、既存の水力発電事業や工業用水道事業を
安定的かつ効率的に運営していくことはもとより、
「経済性の発揮」と「公共の福祉の増進」という
地方公営企業法の経営の基本原則を踏まえた上で、
再生可能エネルギーを活用した新たな事業も含めた
様々な事業展開の可能性について、積極的に検討してまいりたい。
⑦ 道の役割と未来像について
次に、道の役割と未来像について伺います。
道が推進している「新エネルギー導入の加速化」には、いまだ多くの大きな課題が山積しています。
道が掲げる政策を、道の力でのみ推進することは出来ませんし、民間の力のみで加速化させていくにも規制や制約が多い現状では、加速化までには至っていないのが現状であると考えています。
道は、なにが障害となっているのか、なにが留まらせる原因となっているのかを民間事業者と一体となって検証し、そのハードルを乗り越えていく手段を編み出す役割があるのだと信じています。
新エネルギーの分野にあっては、道の、より積極的な姿勢が必要です。自ら取組み、民間と一緒になって新エネルギー大国の実現を果たさなければなりません。
民間がより参入しやすい市場づくりを実現させるための道の新エネルギー政策について、知事の新たな覚悟と決意を伺います。
<答弁>
新エネルギーの導入についてでありますが
○ 出力変動やコストなどの課題を有する
新エネルギーの一層の導入拡大を図るためには、
民間事業者等の幅広い参入を促進しながら
地域の特性に応じた事業性のあるモデルを創出していくことが重要。
○ 本道は、系統に制約がある一方、バイオマスをはじめ身近な地域で、
自立的に確保できるさまざまなエネルギー資源を有しており、
道としては、今後、本道の特性や再生可能エネルギーの
主力電源化を目指した国の動きを的確に捉えながら
北海道を次世代の新エネルギーの活用に向けて、
「多様な自立モデルの実証・実践の地」とするとの新たな考え方を加え
新エネルギー導入加速化基金を活用し、地域に賦存する
エネルギーを複合的に活用し熱や電気などの多面的な利用を
図る取組の普及を進め、地域や企業の皆様と連携した
エネルギー地産地消の取組を加速してまいる。
●事業継続計画等について
①道の事業継続計画について
次に、道の事業継続計画についてであります。
道は、地震をはじめとする大規模災害等により、道民生活に深刻な影響を与える事態が発生し、道自身が被災した場合にも、優先度の高い業務の継続などが可能となるよう「北海道庁業務継続計画」、いわゆる道庁版BCPを策定していますが、この計画で想定する災害は、札幌周辺の大規模地震や洪水となっており、道庁本庁舎が自然災害の直撃を受ける事態を想定したものとなっています。しかし、この度のような札幌から比較的離れた地域で発生した地震などをきっかけとする大規模停電も、道の業務継続に大きな影響を与えることが明らかとなりました。道では、現在進めている検証委員会の検証結果等を踏まえ、道の事業継続計画の見直しを行うものと考えますが、その際には、自然災害とは関係なく発生する可能性のある大規模停電も想定災害として位置付け、道の事業継続計画の実効性を高めるべきと考えます。道の見解を伺います。
<答弁>
道の業務継続計画についてでありますが
○ 道では、地震や洪水など大規模な自然災害を想定し、
災害発生時における職員の参集体制や優先して行う業務などについて、
北海道庁業務継続計画として定めているところ。
○ このたび発生した胆振東部地震では、
地震に加え、道内全域に及ぶ大規模停電により、職員の登庁に支障が生じるなど、
業務遂行にあたって、一定程度の影響が及んだところ。
〇 このため、道としては、今後、自然災害に加え、
新たに大規模停電の発生についても想定するほか、
来年度の早い時期にとりまとめられる災害対応の検証結果を踏まえ、
速やかに業務継続計画を見直すとともに、様々な事象を想定し、
訓練を繰り返し実施するなど、非常時において、
必要な業務が的確に遂行できるよう努めてまいる考え。
②市町村の事業継続計画について
次に、市町村の業務継続計画についてであります。
市町村においても、道と同様に事業継続計画の策定を行っていますが、計画内容が不十分であったり、この度の大規模停電では、非常用電源がないか、あっても十分な機能を果たせず、業務継続に支障が生じたケースが相当数に上ったと聞いています。
市町村は、自然災害等が発生した場合には、住民の避難や復旧・復興対策など災害対策全般の中心とならなければならない重要な機関であるにもかかわらず、非常時の備えが充分でないことは、憂慮すべき事態であるといわざるを得ません。職員数が限られる市町村では、BCPの策定まで手が回らないとの声も聞きますが、道は、こうした市町村の状況をどのように受け止め、今後どう対応していく考えか伺います。
<答弁>
市町村の業務継続計画についてでありますが
○ 市町村は、災害発生時には、災害対策本部を設置するとともに、
庁舎が、被災者支援の拠点ともなることから、予め計画を策定のうえ、
たとえ被災した場合でも、優先的に実施すべき業務の継続性などを
確保しておく必要があると認識。
○ しかしながら、道内では、全ての市町村において、計画は策定されているものの、
非常用発電機の確保や非常時優先業務の整理など国が特に重要な要素として示している
6項目全てを満たしているのは、21市町村にとどまっているところ。
○ このため、道としては、市町村を対象に
研修会を年度内に開催するとともに、国の支援制度の活用をはじめ、
それぞれの市町村の状況を踏まえ、様々な助言を行うなど
早期に、業務継続計画が適切に整備され、道内市町村における災害時の業務が
円滑に遂行できるよう努めてまいる。
最後に、今回質問させて頂いた各項目については、引き続き各委員会等で議論を深めて、確実な成果として参る決意と覚悟を申し添えて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
A,水道事業について
水道事業については、先の決算特別委員会において議論されたところではありますが、国では、来年度から水道事業統合に向けた取組を進める方針と聞いております。
歯止めがかからぬ人口減少によって水需要は減少し、市町村の水道事業は経営悪化が深刻化しています。そこで、水道法の改正案の中では、都道府県を調整役にして、全国で6580事業者の統合を進める方針であると報じられていました。
道内において人口が5000人以下の自治体は、平成29年度で76自治体であり、今後の人口減少を見込むと6000人以下の自治体は、同じく92自治体となり、実に51%、半数を超える自治体が、厳しい水道事業経営環境に置かれることが容易に想定できます。
そして、厳しい環境に置かれてしまう自治体は、なにも149もあるの過疎地域の指定を受けた自治体に限ったことではありません。それは、政令指定都市である札幌市でさえ収支的収支で黒字化させているものの、将来の資本的投資の抑制で財政収支を組み立てざるを得ない厳しい環境であることは明白です。
そこで、以下何点か伺います。
① 道内自治体の水道事業について
最初に、道内の水道事業の実態について伺います。
給水人口5001人以上の上水道事業者は全国に1355あり、そのうち3割ほどが赤字経営となっていて、給水人口5000人以下の簡易水道事業者は全国に5133あり、その経営環境はさらに厳しいものであることが判明しています。
では、道内における上水道水道事業者及び簡易水道事業者の内訳と、その経営状況について伺います。
<答弁>
道内における水道事業の状況についてでありますが
○ 平成28年度末現在における上水道事業は93、
簡易水道事業は239となっています。
○ 道内の水道事業の経営状況としては、
近年の人口減少による水道料金収入の減少、高度経済成長期に、
整備した施設の更新に多額の費用を要することなどに加え、
本道は積雪寒冷で人口密度が低く、
施設の設置や維持管理に要する費用が割高で、
全国的にみても、事業運営が厳しい状況にあるところ。
② 道内の水道事業の広域連携について
次に、道内の簡易水道事業者のうち、どれくらいの広域連携が進んでいるのでしょうか。また、経営ベースで統合に至るまで広域化が進んでいる事業者はどのようになっているのか伺います。
<答弁>
水道事業の広域連携についてでありますが
○ 簡易水道事業については、
平成18年度に示された国の方針により、事業の経営基盤強化等の観点から、
同一市町村内に多数あった簡易水道の事業統合が進められ、
平成19年度の327から、平成28年度には239となったところ。
○ しかしながら、市町村を越える事業統合には、至っていない状況にあります。
③ 道内の水道事業者の経営状況について
次に、道内の水道事業者のうち、どれくらいが収益的収支ベースで黒字経営となっていて、どれくらいが赤字経営となっているのでしょうか?
更に、当該自治体による一般会計からの補てんで黒字決算とされている水道事業者は、どの程度あるものでしょうか、伺います。
<答弁>
道内の水道事業者の経営状況についてでありますが、
○ 平成28年度決算における道内204の水道事業会計でみると、
収益的収支ベースで黒字の事業は、168事業、約82%であり、
赤字の事業は36事業、約18%となっているところ。
○ また、黒字の168事業のうち、一般会計からの補てんにより、
黒字となっているものは、28事業、約17%となっているところ。
④ 水道事業の実態について
次に、水道事業の実態について伺います。
例え、収益的収支ベースで黒字化できていたとしても、その実は、将来的に発生する膨大な管渠や管路、浄水場の更新・改修などの費用を正しく資本的収支ベースで見込むと、その状態は、途端にバランスが取れなくなることは既に議論されてきた通りです。
水道が、私たちの暮らしに不可欠なインフラである以上は、行政が責任をもって安心して使用できるように維持管理していかなければならないものです。
今まさに、それを担保できる経営環境を整えていくために、国は、水道法の改正や国庫補助金の拡充や地方交付税の増額による手厚い財政支援を施してでも、各水道事業者の自立を実現させようとしています。
そこで、数点伺います。
Ⅰ,道は、水道事業者や民間事業者による協議の場として「地域別会議」を設け、それぞ
れの意見や課題をとりまとめたとお聞きしております。
その会議でとりまとめている統合や広域化はもとより、体制の維持や管渠・管路、そ
して浄水場の更新や改修についての課題について、どのように認識し、今後どのよう
に対応していくことにしているのか見解を伺います。
<答弁>
水道事業の課題などについてでありますが
○ 道では、平成25年度に、水道事業が抱える課題の解決に向け、
意見交換や取組方策の検討を目的として設置した「地域別会議」を
6地域でこれまで延べ28回開催してきたところであり、
この中で、水道事業者からは
・技術系職員が不足し、保守管理等の技術継承が難しいこと
・水道料金収入が減少する中、施設更新に係る財源が不足していること
等の課題が示され、
また、民間事業者からは
・管理委託の共同化など、できることから進めて、事業の効率化を
図ることが大切との意見が出されたところ。
○ 道としては、これらの意見等を踏まえ、
今後も「地域別会議」の開催等を通じて、
関係者間の一層の意識共有を図りながら、
地域の実情にあった広域連携を促進し、
水道事業の基盤強化が図られるよう努めてまいる。
Ⅱ,道は、各水道事業者による更新計画の有無や今後の料金や予算の見込み、そして技術系職員の充足について承知しているのでしょうか。また、各計画の適正さの評価をしているのでしょうか、見解を伺います。
<答弁>
水道施設の更新等についてでありますが
○ 持続可能な水道事業とするためには、
中長期的な施設更新需要や、今後の予算の精査、
水道料金の検討などを的確に行うことが必要となることから、
計画的な施設の更新と必要な資金確保等について検討を行う、
いわゆる「アセットマネジメント」を実施し、
それに基づく水道施設の更新計画の策定が必要となります。
○ 道内の上水道事業及び水道用水供給事業では、
アセットマネジメントを約65%で実施、
管路に関する更新計画は約60%で既に策定されている状況であり、
道では、それぞれの事業が、更新計画に基づいて行われているか否かについて、
水道法に基づく立入検査で確認しているところであります。
○ しかしながら、更新計画を未だ策定していない事業者も多いことから、
道としては、引き続き、水道事業者に対し、アセットマネジメントの実施
と更新計画の策定について指導・助言を行ってまいる。
○ また、水道事業を担う自治体の技術系職員の充足状況については、
地域別会議等の機会を活用し、実態把握に努めており、
多くの自治体で、技術系職員の不足による技術の継承等の課題を抱えている状況。
<指摘>
いま答弁いただいた中で、アセットマネジメントや更新計画の策定率が60%程度とお
聞きしました。この度の改正案によると、「水道事業者等は、長期的な観点から、水道施設
の計画的な更新に努めなければならないものとする。」と資産管理について推進を示してい
ます。
道内の水道事業者による策定率が60%ということが、増加してきている過程なのかに
もよりますが、いつか策定すれば良いものなのではなく、その全ての水道事業者が策定を終える時期やそれまでの段階別に策定率を掲げながら、水道事業者に策定を強く求めていくことが必要です。
さまざまな事情があることは承知していますが、住民が安定して安全な水道を使い続けることが必要である以上は、市町村や水道事業者はその義務を負っていることを忘れてはいけません。これ以上の先延ばしは決して許されることではありません。
道は、この点を厳しく発信していく必要があります。くれぐれも傍観者として携わらぬように要請しておきます。
Ⅲ,道は、統合や広域化について検討を始めている水道事業者について把握しているのでしょうか。道が果たすべき役割は、計画策定の推進にとどまることはありません。道内の健全な水道事業の継続を実現させるために、どのような役割を果たしていく考えであるのかを伺います。
<答弁>
道の役割についてでありますが
○ 人口減少により料金収入が減るなど
水道事業を取り巻く環境が厳しさを増す中、
本道では、経営基盤の弱い中小規模の事業者が多く、
これらの水道事業を持続させていくためには、
事業統合や施設の共同利用、維持管理の共同委託などといった
広域連携により事業の効率化を
図っていかなければならないものと認識。
○ このため道では、これまで「地域別会議」等において
水道事業者間における意見交換を行うなどして
広域連携の推進に努めてきたところであるが、
今後はこの「地域別会議」等において、先進事例の紹介のほか、
地域の実情にあった連携手法を具体的に提案するなどして、
広域連携に向けた取組が具現化されるよう、
水道事業者の一層の意識の醸成を図り、
道内の水道事業の広域連携が進むよう、
道として、その役割を果たしていく考え。
Ⅳ,近年、全国各地で災害が多発する中で、本道でも9月6日に北海道胆振東部地震が発生し、水道にも大きな被害があったと承知しています。大規模な災害が発生した場合には、市町村単位での対応が難しくなることが想定できます。
今回の地震において、震源地近くで大きな被害があった厚真町や安平町は中小規模の水道事業者となりますが、どのような体制で断水の解消や通水を果たしたのか伺います。
<答弁>
胆振東部地震に対する対応についてでありますが、
○ 被災自治体においては、大きな災害が発生した場合の復旧等対応について、
全国の水道事業者などで組織する公益社団法人日本水道協会の
北海道地方支部と、災害時応援協定を締結しており、
今般の災害においても、この協定に基づいて、
札幌市を中心とした道内水道事業者等から、
応急給水や応急復旧のための職員の派遣や
資材の提供などの支援が行われ、漏水調査や補修工事等
断水の解消に係る措置がとられたところ。
○ また、道としては、発災翌日の9月7日から職員を現地に派遣し、
被災地の被害状況の把握や、被災した水道事業者に対し、
応急復旧への助言を行ってきたところ。
⑤ 北海道の水道水のPRについて
次に、北海道の水について伺います。
私は、北海道の水については高い評価を受けていると自負しています。それは、天然水に留まらず、水道水についても同様です。
私たちの暮らしに密着している水道事業の抱える課題ばかりではなく、その優位性を認識していただけるように道民の意識を醸成していくことや、日本国民や海外に広くアピールしていくことは、北海道を愛する道民の皆さんや水道事業に関わる全ての方々へのエールにも繋がることと考えます。
道は、6月1日から7日に催される水道週間で、これまで様々な取組みを展開してきていると承知していますが、新たに、道内の水道事業者から参加を募り、「美味しい水道水コンテスト」を開催することで、道内外、国外へとアピールすることができると思いますが、見解を伺います。
<答弁>
水道水の利用促進についてでありますが
○ 本道は総面積の約7割に当たる、554万ヘクタールが森林で覆われ、
山々から流れる数多くの河川は清涼で豊富な水道水源となっています。
○ 道内には、これらの水源から作った水道水を
安全で安心かつ「おいしい水」として
PRに努めている水道事業者もあることから、
道としては、道民はもとより広く道外の方々にも、
本道の水道水のすばらしさについて、HP等を活用して発信するほか、
水道週間の機会等を活用して、新たに、
道内の水道事業体が作ったボトルウォーターを
一斉に集めたイベントを開催するなど、
広く道内外に周知してまいります。
<指摘>
なかなか難儀な質問であったのかもしれません。
しかし、蛇口を捻れば当たり前に水が出てくる、水がタダであるという意識が根付いている日本では、水道事業者の危機意識を高めながら、同時に使用する住民の意識も併せて高めることで、今後到来する更新や改修などの避けることができない費用負担について理解を求めていくことが大切です。
私は、そんな事実を周知するだけではなかなか理解は得られないのだと考えています。
一方で、美味い不味いの品評が大切なのではなく、故郷の、北海道の水が美味しいことを、いかに誇りとしてアピールしていくのかは、地域の水道事業の維持継続にとって欠かせないポイントとなるのではないでしょうか。
よって、一斉に集めたイベント程度では、その効果は限定的です。
その効果の拡大や具体的な手段については、別の議論で深めることとしたいと思います。
⑥ 水道法改正案による協議会の設置について
今国会では、経営環境の改善を喫緊の課題とした水道法改正案が継続審議されていて、水道事業の基盤を強化することを目指しています。
これまで質問してきたような現状を早期のうちに改善していかなければ、急激な人口減少を避けられない北海道においては、安全で安定した水道水の供給がままならなくなることが現実になってしまうことが視野に入ってきているのです。
そこで、改正案では、広域化に向けて都道府県が関係市町村による協議会を設置できるようになると報じられています。
この協議会に期待されている役割は、統合と広域化へ向けて背中を押す役目であることははっきりしています。
一方で、「地域別会議」で意見や議論が取りまとめられているように、他府県と大きく異なる人口が分散化された北海道においては、一概に方向性を定めることができないことも確かなのです。
よって、改正案に基づいて「北海道水道事業経営統合広域化協議会」を早期に設置し、その協議会の下で「地域別会議」が機能するように設えることが必要です。
今回の取組みでは、各地域の諸事情を優先する余りに水道事業者の統合や広域化が進まないことは、未来の道民の不利益に直結してしまうことは明白です。
道は、この機会をどう捉えて考えているのか、どのように対応しようとしているのか、そして、この協議会をいつ設置する考えがあるのかを伺います。
<答弁>
協議会の設置についてでありますが
○ 人口減少に伴う水需要の減少、水道施設の老朽化、
技術系職員の不足等の様々な課題を抱える
水道を維持・継続していくためには、
水道事業者が、相互理解のもと、広域連携を進め、
事業の効率化を図ることが重要と認識。
○ このため、道では、「地域別会議」を設置し、
地域の水道が抱える課題の解決に向け、水道事業者間で
広域連携に向けた認識の共有を進めてきたところであり、
平成30年度には、木古内町と知内町との共同委託の動きも
現れてきたところ。
○ 現在、国では都道府県が広域連携の推進役となるよう
水道法改正の手続きを進めているところであり、道としては、
この法改正を広域連携推進のための重要な契機として捉え、
「地域別会議」等を通じて、より一層
各水道事業者における広域連携の意識の醸成を図るとともに、
その意向も十分確認しながら、
改正法に基づく「協議会」が早期に設置できるよう
取組を進めるとともに、各地域における「協議会」で、
水道事業者間の連携についての具体的な検討や取組が進むことで、
水道事業の基盤強化が図られるよう取り組んでまいる。
<指摘>
今回の議論の中で、「統合」と「広域連携」の意味合いの違いが気になっています。それは、その対象が隣接市町村である場合や同一市町村内の場合と、多岐に渡るケースがあって、水道料金や将来に渡って発生する維持管理の費用の多寡によって、地域別会議の場でも議論が深まっていないとお聞きしています。
改正案が示す意図を違うことなく、道として市町村に現実を強く知らしめていかなければ、これまで同様に問題や課題の先送りにしかならない、お茶を濁す程度の議論にしかならない可能性が容易に想定できます。
道は、強いリーダーシップを発揮して、本政策にあたっていただくように要請しておきます。
<指摘>
もう一つ指摘を加えます。
私は、これまでに上水道や下水道についての議会議論を行ってきましたが、その都度お伝えさせて頂いていることの中に、行政側からの視点のみでこの課題に望むのは現実的ではないと繰り返しお伝えしています。
行政側からの視点とは、耐用年数と更新・改修のための予算付けの都合で、いくら完璧な事業計画を組んだとしても、それは実現できないものでしかないということです。
更新や改修を進めるには、道内工事業者の皆さんの協力が欠かせません。
人口減少と共に、人手不足が進行し、更に建設土木業界におけるそれは顕著なものであることは明らかです。
同時に、業界における新技術や新工法の開発は、避けられない人件費や資材費の高騰の打開策として期待されるところでもあります。
また、民営化を含めた民間力の活用は、抜本的な課題の解決に大きく寄与することになるとも考えられています。
これらについて日常的体系的に情報共有と議論を深めていくことが重要であり、行政による情報の公開によって、想定される工事量と工事時期の的確な把握がなされます。
そして、関係業界の皆さんの計画的な人員配置と設備投資が実現します。
そこではじめて予算執行の的確化が実現するものと考えています。
だからこそ、今回の質問で主題としている協議会が果たす役割が非常に大きいものと判断しているのです。せっかくの機会ですから要望しておくと、この協議会には、業界団体の代表者と情報提供や交換が可能となる部会の設置も求めておきます。
道は、道内自治体に対して道が果たすべき役割を積極的に認識し、この好機を逃すことなく、広く道内で安全で安定した水道水の提供と維持を実現させるサポートを行うことができるように行動を積み重ねるよう強く要請して質問を終わります。ありがとうございました。
昨日、平成30年度の決算特別委員会が開会しました。
北の元気玉が三年半前に当選させて頂いて以来、初めての配属となりました。
第一分科会の委員長を拝命しております。その模様は別途ご報告させていただきます。
分科会の開会に先立ち、本委員会で企業局に質問をさせて頂く機会を得ましたので、
先輩諸氏のご指導を頂きながら「電気事業会計」と「工業用水事業会計」について質問せて頂きました。
特に、この工業用水道事業会計では、道が経営する「室蘭工水」「苫小牧工水」「石狩湾新港工水」の決算状況をチェックするとともに、それらが果たす役割を確認しました。
また、工業用水が単に産業を支える役割に留まることなく、新エネルギーの一翼を担うことのできる重要なインフラであることを指摘し、今後の議論につなげてまいることとしました。
是非、ご覧ください!
———————————————————————————————
二 工業用水道事業会計について
(一)平成29年度の決算について
次に平成29年度の工業用水道事業について伺います。まず、工業用水道事業の平成29年度の収支や未処理欠損金など、決算の状況がどのようになっているのか、この決算に対する認識も含め伺います。

<答弁>
平成29年度の決算についてでありますが
○ まず、収入については、契約水量の増加などがあった一方で、
平成18年度から借り入れた未稼動資産等整理債の償還が前年度に終了したことに伴い、
一般会計からの補助金が減少したことなどにより、経常収益は約20億8千万円となったところ。
○ また、支出については、減価償却費が増加した一方で、
未稼動資産等整理債の利息の減などにより、
経常費用が約18億8千万円となった結果、経常利益は約2億円となり、
さらに、今年度は特別利益が発生しなかったことから、
純利益も同額の約2億円となったところ。
○ この結果、7期連続で黒字決算となり、
今年度も一定の経営改善を図ることができたものと受け止めている。
○ しかしながら、ご指摘のあった未処理欠損金は、
平成29年度末で約86億4千万円と、
前年度と比べ約24億4千万円減少したものの、
依然として多額であり、厳しい経営状況にあるものと認識している。
(二)経営健全化計画の進捗状況について
未処理欠損金がなお多額に上るなど厳しい経営状況が続いていますが、企業局では、工業用水道事業の経営基盤の強化に向けて、平成27年度から31年度までの5年間を計画期間とした「北海道工業用水道事業経営健全化計画」に取り組んでいます。平成29年度はこの計画の中間年度にあたりますが、平成29年度までの進捗状況について伺います。
<答弁>
経営健全化計画の進捗状況についてでありますが
○ 現在、取り組んでいる「北海道工業用水道事業経営健全化計画」では、
平成27年度から31年度までの5年間の計画期間中、
全ての年度で純利益を計上することと、
未処理欠損金を可能な限り低減することを目標としているところ。
○ また、計画においては、契約水量、契約率、純利益、
経常収支比率、未処理欠損金の5項目について、年度毎の目安を設定しているところ。
○ 平成29年度決算においては、工業用水道事業全体で、
契約水量については、目安の25万6,594トンに対し、
実績は25万6,052トンと542トン及ばず、
このため、契約率は目安の78.5パーセントを0.2ポイント下回る
78.3パーセントとなっている。
○ 一方、純利益については、8千万円に対し約2億円、
経常収支比率は、104パーセントに対し110.6パーセント、
未処理欠損金は、約91億4千万円に対し約86億4千万円と、
それぞれ目安を上回る結果となっており、
目標については、計画初年度の平成27年度から3期連続で、
概ね達成できたものと考えている。

(三)経営改善に向けた取組とその成果について
経営健全化計画においては、工業用水の供給能力に対する料金収入の基礎となる契約水量が占める割合、すなわち契約率がなかなか伸びない状況を踏まえ、新規需要の開拓や支出抑制の取組を進めていくとしていますが、平成29年度までにどのような取組を行い、どのような成果が挙げられたのか伺います。
<答弁>
経営改善に向けた取組などについてでありますが
○ まず、需要開拓の取組として、知事部局や関係機関と連携して、
企業立地イベントへの出展や企業への個別の営業活動を行っており、
平成29年度は新たに
「北洋銀行ものづくりテクノフェア」への出展を行ったほか、
今年度は金融機関との情報交換会や、
近年、工業用水の問い合わせが増えているバイオマス発電の
事業者に対し、幹部によるトップセールスを行ったところであり、
こうした取組などを通じ、計画開始からこれまでに
9,880トンの使用申込があったところ。
○ 次に、支出抑制の取組として、運転管理業務について
単年度委託から4年間の包括委託への見直しを進めてきたほか、
企業債の借入について、利息の低減が図られる借入方法に
改めるなどの取組により、これまで約684万円を削減したところ。
○ 企業局としては、引き続き、需要拡大の取組を積極的に行うとともに、
可能な限りの経費節減に努めながら、経営健全化を着実に推進していく考え。
(四)契約率の動向について
工業用水道事業は多額の設備投資が必要となるため、契約率が一定水準を確保することが重要であり、経営基盤強化に向けた重要な指標と考えます。そこで、室蘭地区、苫小牧地区及び石狩湾新港地域における工業用水の契約率は、近年どのように推移しているのか伺います。
<答弁>
契約率の推移についてでありますが
○ 道営工業用水道事業が国の制度に基づき
平成18年度から取り組んだ、
「経営健全化計画」の最終年度である平成26年度と、
企業局が独自に策定し、取り組んでいる
現在の「経営健全化計画」の中間年度に当たる
平成29年度を比較すると、工業用水全体では、給水能力32万7千トンに対し、
契約率は77パーセントから78.3パーセントへと、1.3ポイント上昇した。
○ 同様の比較を工水別に行うと、
室蘭工水では、給水能力11万5千トンに対し、
契約率は93.7パーセントで横ばいとなっているものの、
苫小牧工水では、給水能力20万トンに対し、
契約率は2.1ポイント上昇の72.7パーセント、
石狩工水では、給水能力1万2千トンに対し、
契約率は0.6ポイント上昇の24.6パーセントと、
両工水では上昇で推移している状況。
(五)石狩工水の契約率について
室蘭工水では9割、苫小牧工水では7割を超える契約率を維持しているものの、石狩工水については、契約率が3割を切るなど依然として厳しい経営状況にあるとのことです。石狩工水の契約率について、今後どのように見通しているのか伺います。
<答弁>
石狩工水の今後の見通しについてでありますが
○ 石狩湾新港地域は、物流拠点としての産業集積が進み、
これまで工業用水を多く使用する企業の立地が伸びなかったことなどから、
給水能力1万2千トンに対し、平成29年度末の契約水量は2,952トン、
契約率は24.6パーセントにとどまり、抜本的な経営改善に向けては、
需要の拡大が最も重要な課題と考えているところ。
○ そうした中、北海道電力が、平成27年度から
同地域で液化天然ガスによる発電所の建設を進めており、
現在の契約水量600トンは今後段階的に増え、
平成42年度までに1,600トンとなる予定であるほか、
事業環境の変化などから使用開始時期は、ずれ込む可能性があるが、
他のエネルギー関連企業からも、平成33年3月から3,480トンの
使用申込を受けており、これらを考慮すると、
契約率は約64パーセントとなる見込である。
(六)室蘭工水について
室蘭工水の大口ユーザーであるJXTGエネルギー株式会社が、室蘭製造所における石油製品等の製造を停止する方針が報道されて以来約1年が経過しました。JXTGエネルギーの契約水量は室蘭工水の4分の1を超え、仮に契約水量の全量が契約解除となった場合、工業用水道事業の経営に大きな影響が生じると考えます。企業局は、JXTGエネルギーによるこの度の経営方針についてどのような説明を受けており、工業用水道事業経営にどのように影響すると考えているのか、また、今後どう対応する考えか合わせて伺います。

<答弁>
室蘭工水についてでありますが
○ 室蘭工水は、鉄鋼関連企業など7社に対し、
日量10万7,710トンの工業用水を供給しており、
給水能力11万5千トンに対し、93.7パーセントと高い契約率となっている。
〇 こうした中、JXTGエネルギー株式会社から、
昨年9月、室蘭地区でこれまで行ってきた石油製品の製造を停止し、
平成31年4月以降は、北海道を中心とした
石油製品の物流拠点として事業を再編すると発表があったところ。
〇 その後企業局では、同社から、事業再編は
競争力強化を図るための全国的な生産・供給体制見直しの結果
必要な措置であるとの説明を受けるとともに、
本年3月には、改めて同社から、今後の水使用についての相談があり、
現在、事業再編後の工業用水の使用目的や水量などについて、
確認を行っているところ。
〇 同社は室蘭工水の契約水量の26.5パーセントを占める
大口ユーザーであり、その動向は、室蘭工水の経営に
大きな影響を及ぼすことも考えられることから、
将来の収支見通しなど様々な検討を進めているところ。
(七)需要拡大の取組について
経営基盤の強化に向けては、契約水量の増加を図ることがなによりも重要です。経営健全化計画の達成に向けて、新規需要の開拓や契約水量の増加に、今後どのように取り組んでいくのか伺います。
<答弁>
需要拡大の取組についてでありますが
〇 需要拡大に向けては、企業の皆様に
工業用水の利点を理解していただくことが重要であるため、
昨年度から「北洋銀行ものづくりテクノフェア」への出展を行っているほか、
今年度から新たに「ビジネスEXPO(エキスポ)」に出展し、来場者に対し、
良好な水質や上水道に比べ安価な料金をPRするとともに、
最新の企業情報の収集を図ることとしているところ。
○ また、近年は、食品関連のほか、新エネルギーによる発電や熱供給においても、
工業用水利用の動きがあることから、今後は、これらの分野にも重きを置いて
新規需要開拓を行っていく必要があると考えているところ。
○ このため、企業局としては、
庁内関係部と企業誘致や水需要に関する情報の共有を図るとともに、
道内金融機関とも連携して進出企業の情報を収集するほか、
外部有識者による経営懇談会において、
専門的な視点からのアドバイスを受けながら
工業用水の新規・増量ニーズをいち早く掴み、
需要開拓に活かしていく考え。

(八)北海道胆振東部地震への対応について
苫小牧工水では、北海道胆振東部地震で大きな被害を受けた苫東厚真発電所などのユーザーに対して工業用水を供給していますが、苫小牧を含め、今回の地震による送水への影響など各地区の状況はどうだったのか伺います。
<答弁>
地震への対応についてでありますが
○ 企業局においては、9月6日未明の地震発生後、
各管理事務所において、ただちにダムや取水施設、配水管など
全ての施設について点検を実施したところ。
○ その結果、苫小牧地区では、浄水場の被害は無かったものの
配水管の2カ所で漏水を確認したため、
送水を継続しながら配水管の補修を行い、
9月21日には、補修を完了したところ。
○ また、室蘭地区は、貯水ダム本体及びゲートなどの関連施設、
配水管路への被害は無く、
石狩湾新港地域も、浄水場、配水管ともに被害は無かったことから、
3工水ともに、地震に伴う送水への直接的な影響は無かったところ。
○ しかしながら、その後も余震が続いていることから、
企業局では施設の設置場所で、震度3以上の地震があった場合には、
点検を行っており、引き続き送水に万全を期してまいる考え。
(九)配水管路の耐震化計画について
今回の地震では配水管路からの漏水が発生しているとのことですが、昭和40年代から50年代にかけて整備された企業局の工業用水道施設では、老朽化及び耐震化対策が大きな課題であると考えます。災害に強い施設としていくため、配水管路の耐震化をどのように進めていく考えか伺います。
<答弁>
配水管路の耐震化についてでありますが
○ 配水管路の老朽化が進む中、地震等の自然災害に備えるためには、
配水管路の老朽更新、耐震化は重要な課題と認識しており、
これまでも順次、耐震性の高い配水管への更新を行ってきたところ。
○ こうした中、室蘭工水では、平成31年度までの
第三期改修事業の完了により、耐震性が低く老朽化も進み
早急に対応しなければならない区間の改修については、
概ね完了する予定となっているところ。
○ また、苫小牧工水では、今後行う第二期改修事業で、
耐震性の低いコンクリート管の更新を行う予定であり、
これにより過去の地震において漏水が発生した区間の耐震化が図られる見通し。
○ 一方、平成11年度から給水を開始している石狩工水については、
他の事業者から譲渡を受けた区間を除き、耐震基準を満たしている。
○ 企業局としては、工業用水の安定的な供給に向け
今後とも耐震化率の向上に計画的に取り組んでまいる考え。
(十)施設の耐震化に向けた取組について
配水管路以外のダムや浄水場などの設備については、昨年度の決算特別委員会においても、耐震診断を行いその結果を踏まえて計画的に耐震化を進めるということでしたが、この度の地震も踏まえて、今後の耐震化をどのように進めていく考えなのか伺います。
<答弁>
施設の耐震化についてでありますが
○ 工水の安定供給を図るためには、配水管の耐震化のみならず、
施設設置後40年以上が経過し、老朽化が進んでいる
貯水ダムや取水施設、浄水場などの耐震化も重要であり、
平成28年度に着手した耐震診断について、
これまで平成34年度としていた完了予定を平成31年度に前倒しするなど、
耐震化に向けた取組を加速させているところ。
○ 耐震診断の結果、室蘭工水の幌別ダムでは、
将来にわたる最も大規模な地震動の際、
貯水ダム本体の貯水機能は維持できるものの、
ゲートの操作に課題があるとされ、
現在、可能な限り早期の耐震化に向け、鋭意検討を進めているところ。
○ また、苫小牧及び石狩工水は、
来年度までに浄水場などの耐震診断を完了し、
その結果を受け、速やかに耐震化に向けた検討を進めることとしている。

(十一)今後の施設整備のあり方について
工業用水の供給を将来にわたり安定的に継続していくためには、ライフサイクルコストの最適化が図られるよう中長期的な見通しに立って整備計画を策定することが求められます。さらに、人口減少社会にあっては企業の経済活動に伴う工業用水の需要も今後大幅な増加は見込めないものと考えます。こうした状況を踏まえた将来予測に基づいて工業用水道施設の整備を行う必要があります。また、着実、適切に工事を発注していく事も重要です。今後の施設整備にあたっての企業局の考え方を伺います。
<答弁>
今後の施設整備についてでありますが
○ 工業用水道は、本道の産業振興にとって不可欠なインフラであり、
厳しい経営環境の中においても、安定供給を維持するためには、
施設の計画的な維持管理や整備が必要不可欠である。
○ このため、設備の更新の際は、管路については腐食度合いの調査、
機械類については定期的な点検結果に基づき
ライフサイクルコストの最適化を目的とした更新計画を策定するなどして、
長寿命化を図ってきたところ。
〇 また、今後の施設整備に当たっては、
将来の水需要を見通し、減少が見込まれる場合には
例えば管路の更新時には、管径を縮小するスペックダウンや、
非常用電源設備の更新時には、装置の発電能力を下げる
ダウンサイジングなどの検討を行うことも必要であると考えており、
企業局としては、こうした取組を通じて、経営の健全化にも
十分留意しながら、適切な施設整備に努めてまいる。
○ なお、工事等の発注にあたっては、
可能な限り事業量の平準化に努めるとともに、
道内建設業界の動向にも留意しながら、計画的な発注に努めてまいる。
<指摘>
重ねてお話しすることになりますが、とても重要なことですので、あえて指
摘を加えておきます。
さきほど「可能な限り事業量の平準化に努めるとともに、道内建設業界の動
向にも留意しながら、計画的に発注してまいる」と答弁していただきました。
企業局が有する排水管路や各施設は、特に1972年の札幌オリンピックを
契機として進んだ道内の開発から約50年という耐用年数を一気に迎えるこ
とになります。そこには膨大な工事量があるのです。
それに対して、それらの更新や耐震化は、少しずつでしか進められていない
のが現実の姿なのです。
企業局は、今後発生する必要工事量を把握し、それが前倒しになろうとも、
長寿命化策を施しながら後ろ倒しになろうとも、全体工事量の平準化を図ら
なければなりません。
平準化と言っても、ただ均せばいいものではありません。
道内の工事会社で施工可能な範囲での平準化が欠かせません。
昨今の人手不足の解消や、関係業界の皆さんによる工法や低コストのための
技術開発も欠かすことは出来ません。
平準化と道内業界との情報の共有とは、その実態を正確に把握し、行政と民
間が課題を共有し、いまから有効な策を打ち出していくことが必要です。
また、その予算は膨大なものとなることは明確です。
国や道から落ちてくる分をアテにするだけではなく、自ら稼ぎ出すことで、
自主性を以って財源確保に努めるくらいの覚悟で、事にあたっていただきた
いと強く要請しておきます。

(十二)大規模停電の影響について
今回の地震では、全道の電力が失われるブラックアウトが発生しました。企業局は、ブラックアウトの引き金となった道内最大量の発電を行っている苫東厚真発電所に工業用水を供給していますが、仮に火力発電所への工業用水の供給が停止すると運転に支障を来し、設備の安全性も損なわれる恐れがあります。今回の大規模停電により苫東厚真発電所への給水にはどのような影響があったのか、また、苫東厚真発電所を抱える苫小牧地区のほか、室蘭地区及び石狩湾新港地域における火力発電所への給水状況と大規模停電の影響についても併せて伺います。
<答弁>
大規模停電の影響についてでありますが
○ 北海道電力苫東厚真発電所に用水を供給している
苫小牧工水では、停電と同時に送水に不可欠な加圧ポンプの電源を
非常用電源に切り替え運転を行ったものの、停電が長時間にわたったため、
非常用電源の燃料が不足する懸念があったところ。
○ このため、企業局では、苫東厚真発電所への給水を
維持する重要性から、北海道電力などの協力を得て、
最優先で燃料を確保し、給水を継続したことから、
苫東厚真発電所などの火力発電所をはじめ
地区内への給水には影響が無かったところ。
○ 一方、室蘭工水では、停電により送水のための加圧ポンプが停止したが、
幌別ダムからの自然流下による水圧で送水を一定量、維持することができ、
地区内の火力発電設備を含めた受水企業には影響が無かったところ。
○ さらに、石狩工水でも、苫小牧工水と同様に
加圧ポンプの電源を非常用電源に切り替えて運転を行ったが、
停電当日の昼頃には、その後の燃料調達が困難になると判断し、
全ユーザーの了解を得た上で、16時過ぎから23時間にわたり
給水を停止したものの、
停電の影響で地区内の多くの企業が操業停止していたことから、
断水による大きな影響は無かったところ。
(十三)大規模停電時における工業用水の安定供給について
道民生活、道内経済のライフラインである電力供給を工業用水が支えている実態があり、仮にこの度の大規模停電のような状況が再び発生したとしても、速やかに復旧するためには、停電時にも安定して工業用水を供給することが不可欠であると考えます。企業局としては、電力供給に必要な工業用水道の供給に今後どのように取り組んで行く考えか伺います。
<答弁>
安定供給に向けた対策についてでありますが
○ 今回の停電では非常用電源の燃料が不足し、
石狩工水では、受水企業には影響が無かったものの、
工水の供給を一時停止する事態も生じたところであり、
今後、長時間の停電にも対応できる非常用電源の確保が、
課題として認識されたところ。
○ このため、企業局としては、非常用電源の確保に当たっては、
電源設備の更新に合わせて、
長時間運転できる効率的な発電装置を導入するとともに、
燃料確保が困難になったことを踏まえ、
燃料タンクの容量の増加についても検討を行ってまいる考え。
(十四)強靭化に向けた取組について
工業用水道は重要な産業インフラであり、施設の老朽更新を進め地震等の自然災害に備えるなどして、将来にわたり安定供給を維持することが事業者としての重要な責務です。特に、道内における電力供給に大きな役割を果たす火力発電所の運転に必要な水を供給する企業局の工業用水道事業は、間接的ではありますが道民生活を支える重要なインフラでもあり、厳しい経営状況にあるとはいえ、道民の安心・安全を守るため必要な施設更新・改修は行わなければなりません。施設の強靱化に向けて今後どのように取り組んでいくのか伺います。
<答弁>
施設の強靭化についてでありますが
○ 委員ご指摘のとおり、工業用水道は重要な産業インフラであり、
将来にわたり安定的な供給を維持することは、
工業用水道事業者として最も重要な責務であると認識しているところ。
○ とりわけ、今回の地震を踏まえ、
災害時における道民の皆様の安心・安全を確保する観点から、
火力発電所に対する給水の安定性の確保には、
最優先で取り組む必要があると考えるところ。
○ このため、苫東厚真発電所へ給水する苫小牧工水においては、
耐震性の低いコンクリート管の更新を加速化するため、
第二期改修事業の前倒しについて検討を進めることとしたところ。
○ また、平成28年度から行っている耐震診断の結果を受け、
現在進めている貯水ダムのゲートや浄水場の耐震化についても、
可能な限り早期に立案・実行できるよう検討を進めていくほか、
停電対策についても、非常用電源設備の更新などの検討を
急ぐこととしているところ。
○ これらの対策には、多額な費用を要することから、
工水事業の厳しい経営状況や受水企業の経営負担に鑑み、
計画的な整備を図るとともに、
国に対し補助制度の拡充などを強く働きかけるなど、
必要な財源の確保に努めてまいる。
(十五)工業用水道事業の持続可能な経営について
契約率の低迷、災害対策、老朽更新などの課題を抱え、工業用水道事業の経営は今後も厳しい状況が続くと考えますが、そのような中にあっても、道内経済・道民生活そのものを支えるインフラとして、将来にわたり持続可能な事業の構築が求められます。工業用水道事業が抱える様々な課題を踏まえ、今後、どのように経営に取り組んで行く考えか伺います。
<答弁>
工業用水道事業の経営についてでありますが
○ 工業用水道を巡る状況は経済のグローバル化に伴う産業の空洞化や
水のリサイクル技術向上などによる需要の減少など、
事業開始時に比べ大きく変化しており、
道営工業用水道事業においても厳しい経営状況が続いているところ。
○ このような中にあっても、エネルギー、食関連産業など
新たな分野での利用も始まってきていることから、
こうした様々な企業ニーズに的確に応えていくことが、
受水企業の裾野を広げ、需要の開拓に繋がるものと考えており、
今後とも、知事部局や関係機関と連動した機動的な営業活動に
力を入れてまいる。
○ また、このたびの北海道胆振東部地震においては、
大規模停電時においても火力発電施設などへの
給水を維持することができ、
工水の安定供給の重要性について、改めて思いを強くしたところ。
○ 私としては、地域経済を支えるインフラとしての役割はもとより、
道民生活や道内経済の活性化に欠かせない電力供給を支えている
工水の重要な役割をしっかりと果たすため、
施設の早急かつ計画的な老朽更新や耐震化を最重要課題として
取り組んでまいる考え。
○ また、中長期的な経営を見据えて、
最も効率的な施設整備のあり方を検討するとともに、
費用の平準化や財源の確保などにも努め、
工水の安定供給と経営基盤の強化に最善を尽くしてまいる考え。
<指摘>
さきほど質問した電気事業についても同じことが言えると思うのですが、道
や企業局が自ら「稼ぐ」ことを強く意識しないことには、これから迎える人
口減少危機をはじめとする難局に立ち向かうことは出来ません。
北海道が北海道らしく、北海道に住む皆さんが幸せで元気な大地を創り出し、
後世に希望をつないでいく責務がある私たちは、この「稼ぐ」ことから逃れ
ることは出来ないのだと信じています。
特に、新エネルギー導入の加速化を推し進める私たちには、北海道という優
位性を活かした多くの手段が存在していることを自覚し、積極的に民間の活
力を取り込んだ推進力を手に入れなければなりません。
知事をはじめとする道庁職員の皆さんと、公営企業管理者をはじめとする企
業局の皆さん、そして多くの民間事業者の皆さん、それぞれがこれまでの概
念を打ち破ってでも踏み込んでいかなければならない時が、すぐそこまでや
ってきているのだと考えています。
私自身も積極的に情報収集にあたりながら、決して議論するのみを善しとせ
ず、実行動を以って北海道の元気を皆さんと力を合わせて創り出していきた
いと考えています。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
昨日、平成30年度の決算特別委員会が開会しました。
北の元気玉が三年半前に当選させて頂いて以来、初めての配属となりました。
第一分科会の委員長を拝命しております。その模様は別途ご報告させていただきます。
分科会の開会に先立ち、本委員会で企業局に質問をさせて頂く機会を得ましたので、
先輩諸氏のご指導を頂きながら「電気事業会計」と「工業用水事業会計」について質問せて頂きました。
特に、この電気事業会計では、道が取り組む水力発電を中心とした「新エネルギー事業」の在り様を明らかにし、会計的にも検証することで、未来に北海道が「新エネルギー大国」として元気であることを議論しています。
是非、ご覧ください!
一 電気事業会計について
(一)平成29年度の収支について
まず、平成29年度企業会計決算のうち電気事業について伺います。電気事業の収支などの状況はどのようになっているのか伺います。
<答弁>
平成29年度決算についてでありますが
○ まず、収入については、発電量が平年に比べ3割程度伸びたことから、
経常収益が約46億8千万円となったものの、
記録的な大雨により過去最高の発電量となった前年度に比べ
約4億円の減少となっているところ。
○ 一方、支出である経常費用などについては、
前年度に比べ、修繕費などで約4億4千万円増加し、
約26億1千万円となったことから、純利益については約20億7千万円と、
前年度に比べ約8億4千万円の減少となったところ。

(二)純利益について
平成29年度は約20億7千万円の純利益が生じているものの、昨年度の純利益約29億1千万円と比較すると、約8億4千万円の減少となっています。率にすると約30%の減少であり決して小さくない額ですが、なぜこうした純利益の減少となったのか伺います。
<答弁>
純利益についてでありますが
○ 平成29年度は順調に発電を行うことができたものの、
清水沢発電所が改修工事のため平成28年12月から運転を停止したことや、
前年度と比較すると7月、8月の降雨量が少なかったことにより、
販売電力量が前年度対比約88%となり、
経常収益が約4億円の減少となったところ。
○ また、川端発電所においてオーバーホールにより約3億円を要したことや、
夕張市に対する市町村交付金に
シューパロ発電所分が新たに約9千万円加わったことなどから、
経常費用などが約4億4千万円の増加となり、この結果、平成29年度の純利益は、
前年度と比べ約8億4千万円の減少となったところ。

(三)経営状況について
電気事業を安定的に経営していくためには、しっかりとした経営基盤を確立する必要がありますが、電気事業の経営状況をどのように分析しているのか、固定価格買取制度、いわゆるFITによる収益なども含め伺います。
<答弁>
道営電気事業の経営状況についてでありますが
○ 平成27年4月に運転を開始した企業局最大規模のシューパロ及び
28年10月に運転開始した滝の上両発電所が、
FITの適用を受けたことにより、
平成29年度の両発電所の電力料収入は約27億2千万円と、
全電力料収入約44億8千万円の約6割を占めるなど、
安定した収入を確保していることから費用に対する収入の割合を示す
経常収支比率が180パーセントとなり、総務省が直近で公表している
平成28年度の全国平均を40ポイント以上上回るなど
FIT適用前と比べ大幅に向上している。
○ 一方、経営リスクの面ではこれまで建設費用や改修費用を
概ね企業債の借入で賄ってきたことから、料金収入に対する企業債残高の比率が、
154パーセントと、全国平均の83パーセントを大きく上回り、
依然として高い比率となっているものの、
企業債残高については、計画的な償還と今後の借入抑制により
改善を見込んでいるところ。
○ こうした指標を踏まえると、道営電気事業は、
全国と比較しても経営上支障となる問題は見当たらず、
現在のところ経営状態は安定していると考えているところ。
<指摘>
いま頂いた答弁に「全国と比較しても」という表現がありました。
確かに、他の都府県で類する先からデータを引用すること自体には違和感がありません。
しかし、一方で、新エネルギー源の宝庫と自負する私たちが、平均並みの実績を残していることに満足することは、「その先の道」を模索する北海道にとって低めの目標設定であることは否めません。
是非、企業局の皆さんには、より積極的な目標設定と役割を果たしていただけるようにお願いをしておきます。

(四)電力システム改革について
国では平成25年度から、電力の安定供給の確保と電力料金の最大限の抑制等を目的に電力システム改革を進めています。この改革に伴い、電力市場は、水力発電や太陽光など再生可能エネルギーを対象とした新たな取引市場の創設など様々な検討が進められています。こうした一連の改革は、今後、企業局の電気事業にどのような影響を及ぼすと受け止めているのか伺います。
<答弁>
電力システム改革についてでありますが
○ 平成28年4月から始まった電力の小売り全面自由化により、
電力は自由な価格で取引されることとなったところ。
○ 道営電気事業についても、FITが適用されていない
発電所の電力の売却については、平成32年度以降、原則、一般競争入札となり、
売電価格が電力市場の動向などの影響を受けることから、
これまで以上に、収入の変動を見通すことが困難となることが懸念される。
○ また、現在、国が検討している再生可能エネルギーの
環境価値を取引する非化石価値取引市場などの新たな市場の創設は、
収入の増加に結びつくことが期待されるものの、
新たに送配電関連設備の維持・運営費用を発電事業者にも負担させる
議論が進められているなど、改革の内容によっては、
経営にさらなる影響を与えることも予想されるため、
企業局としては、引き続き、電力システム改革の動向に注視してまいりたい。
<指摘>
いま「電力システム改革の動向に注視してまいりたい」と答弁を頂きました。
しかし、買取価格の下落や送配電関連設備の取り扱い、さらに系統接続の空
き容量の見直し等と、それらの方向性は既に見通すことが可能です。
よって、待ちや受けの立場ではなく、攻めの姿勢で先行しておくことが必要
です。新エネルギーについての技術は、まさに日進月歩、特に欧州において
日に日に先進技術が開発されているのが現状です。
積極的な情報収集にあたりながら、北海道を新エネルギー大国に相応しい大
地と成長させることができるように、北海道庁並びに企業局の皆さんには、
日々汗していただけるように要請しておきます。
(五)FITの見直しについて
平成24年度から始まったFITについては、現在国において太陽光発電における買取価格の引き下げや、大規模な事業用発電について入札制度を導入するなど、国民負担の低減に向けた取組が進められているところです。
このようなFITの見直しは、太陽光や風力発電に限らず、今後は水力発電についても同様な検討が進められる可能性があると考えますが、現在どのような状況になっているのか伺います。
<答弁>
FITの見直しについてでありますが
○ FITについては、平成24年7月に施行された
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する
特別措置法」の附則において、平成33年3月までの間に状況を勘案し、
抜本的見直しを行うこととされている。
〇 また、同法の規定に基づき国において、
毎年度、買取価格の見直しが行われ、国民負担の抑制に向け、
太陽光や風力発電などについては、順次、引下げが行われており、
水力についても平成29年4月から出力1千キロワット以上
5千キロワット未満については引き上げ、同年10月から
出力5千キロワット以上3万キロワット未満については
引き下げとなったところ。
○ こうした中、水力発電は開発期間が長期にわたることや
初期投資が巨額なこと、さらには、ダムなどでは減価償却期間が
50年以上と長いにもかかわらず、買取期間が他の電源と同様に
20年間と定められていることから、
期間終了後には大幅な減収が見込まれるなどの課題があると
考えているところ。

(六)地震による被害状況などについて
去る9月6日に北海道における観測史上過去最大の震度7を記録する北海道胆振東部地震が発生し、家屋を巻き込んだ大規模な山腹崩壊等により多くの尊い命が失われたばかりでなく、公共施設などにも甚大な被害が生じたと報じられています。今回の地震による道営発電施設にはどのような被害が生じ、道は、その後どう対応したのか伺います。
<答弁>
地震による被害状況などについてでありますが
○ 当時、企業局では、改修工事中の清水沢を除く7カ所で発電を行っており、
地震直後は発電を停止したものの、地震により水路に土砂等が流入し
運転を停止した滝の上を除く6カ所の発電所では、
北海道電力からの要請に応じて、地震発生当日のうちに順次運転を開始し、
地域への電力供給に寄与したところ。
○ 運転を停止した滝の上発電所については、
土砂撤去などの応急工事に直ちに着手し、
2週間で運転を再開したところであり、
今後、本格復旧に向け今年度中に調査設計を実施し、
早期に対策工事を行うことができるよう努めてまいる。
(七)今冬の発電の見通しについて
道営発電施設においては、速やかに運転を再開したとのことですが、今回の地震に伴い発電停止した北海道電力の苫東厚真発電所については、先月10日に復旧したものの、道内ではこれから電力需要が高まる冬を迎え、不測のトラブルで電力需給がひっ迫する事態も想定せざるを得ません。こうした状況を踏まえると、企業局の電気事業は安定的な電力供給の担い手として一定の役割を果たすことが期待されますが、道営発電施設における今後の発電の見通しは、どのようになっているのか伺います。
<答弁>
今後の発電の見通しについてでありますが
○ 道営発電所においては、発電量がピークとなるかんがい期間の終了後である
秋口から冬までの間に、保安規程に基づく定期点検などのため発電を停止するほか、
冬期間には河川の水量が少なくなることから、発電量が低下するところ。
○ このため、当局としては、定期点検の実施にあたって、
北海道電力と十分な協議を行いながら、電力供給に支障を来さないよう
適切な時期や期間で行うとともに、冬期間においても、高い水位で運転するなど
ダムの貯留水を有効活用した効率の良い運転を行い、
発電量の確保に努めてまいる考え。

(八)発電施設の老朽化対策などについて
地震などの災害が発生した場合でも、安定的に電力を供給していくためには、発電施設の強靱化を図っていくことも大変重要であると考えます。
企業局では、道内に8カ所の水力発電所を保有していますが、建設後50年以上経過した発電所も複数あり、老朽化した発電所では耐震性に課題を抱えているところも少なくないと考えます。
発電用ダムや発電所建屋などの主要な発電施設が損壊した場合、周辺にも甚大な被害をもたらすばかりでなく、長期間にわたり発電を停止せざるを得なくなる事態も想定されます。
道営発電施設の老朽更新や耐震性の強化に今後どのように取り組んでいく考えか伺います。
<答弁>
発電施設の老朽化対策などについてでありますが
○ 改修工事中の清水沢を除いた7カ所の発電所のうち
鷹泊、川端、岩尾内の3発電所については、
運転開始以降、概ね50年以上経過し、
老朽化が進んでいるところ。
○ このため、これらの発電所については、
機器の故障などによる発電停止リスクや、耐用年数も勘案し、
計画的に改修を進めることとしているところ。
○ 一方、耐震化対策としては、2カ所ある道営の発電専用ダムのうち、
清水沢ダムについては、耐震診断により、安全性を確認したところであり、
ポンテシオダムについては、現在調査を行っているところ。
○ また、発電所建屋のうち、
現在の基準に照らして耐震性が低い鷹泊については、耐震補強設計を、
耐震性が明らかでない岩尾内、川端、ポンテシオについては、
耐震診断を、それぞれできるだけ早期に行うことができるよう努めてまいる。
(九)地すべり対策について
今回の地震では、震源地付近において広範囲にわたり山腹崩壊が発生したのは記憶に新しいところです。また、平成28年の熊本地震では、地すべりにより水力発電施設の一部が損壊し、大量の発電用水が流出する事故が発生しました。こうしたことを踏まえ、道営発電施設についても、施設の耐震性のみならず、地震に伴う地すべり発生の危険性について考慮すべきと考えますが、見解を伺います。
<答弁>
地すべり対策についてでありますが
○ 平成28年に発生した熊本地震では、地すべりにより山の斜面に設置されていた
発電用の貯水タンクが損壊し、タンクと水路内に貯まっていた
約1万立方メートルに及ぶ大量の水が土砂とともに下流域の集落に流出するという
被害が発生したところ。
○ 熊本地震での斜面崩壊や胆振東部地震で
大規模な山腹崩壊が多数発生したことを踏まえると、
地すべり等のリスクを適切に評価し、
対策を講じておくことが必要であると考えているところ。
○ このため、企業局としては今後、全発電所を対象とした調査を実施し、
必要な対策を検討してまいる考え。
(十)水力発電について
今回の地震では、地震発生直後、道内全域で電力供給が停止する、いわゆる「ブラックアウト」が発生しました。ブラックアウトからの復旧にあたっては、外部からの電源がなくても起動できる水力発電所がいち早く発電を再開し、単独で再起動できない火力発電所に電力を供給し、復電に寄与したと承知しています。
水力発電は、二酸化炭素の排出がほとんどなく地球温暖化防止対策に貢献するなど環境にやさしいエネルギーとしても導入の促進が期待されており、今回の地震で水力発電の重要性が改めて認識されたところです。
そこで、まず、道内の水力発電の現状と、企業局の水力発電所の規模や全道のシェアについて伺います。
<答弁>
水力発電の状況についてでありますが
○ 道内では、企業局の他に北海道電力や電源開発などの
民間事業者が水力発電を行っており、その発電電力量は
平成29年度で約49億キロワットアワーで、
道内の火力や水力などを合わせた全発電電力量
約360億キロワットアワーの約14パーセントを占めているところ。
○ このうち、改修工事中の清水沢を除き、
現在、企業局が運営する7カ所の水力発電所における
発電電力量は、約3億キロワットアワーで道内の全発電電力量の約1パーセント、
水力発電による電力量の約6パーセントのシェアとなっているところ。

(十一)発電量の増加に向けた取組について
水力発電の分野では企業局の水力発電が一定の規模を有しているとのことですが、クリーンエネルギーの拡大やエネルギーの地産地消の観点から、企業局が率先して水力発電の発電量を増やすべきと考えます。
シューパロ発電所は、平成27年4月に夕張シューパロダムの完成に伴い廃止した二股発電所の代替え施設として運転を開始していますが、企業局において、新たな地点での大規模な電源開発は、平成4年4月に運転を開始した夕張市の滝下発電所以降、行なっていません。発電量の増加のためには、新たな電源開発を行うことも必要と考えますが、見解を伺います。
<答弁>
発電量の増加に向けた取組についてでありますが
○ 企業局では発電施設の老朽化に対応するため、
計画的に施設の改修を進めているところであり、その改修にあたっては、
既存設備の最大限の有効活用を図るため、発電所の設備更新に併せて
発電効率の高い機器への更新を行う、いわゆる「リパワリング」を進め
発電量の増加に取り組んでいるところ。
○ 一方で、水力での新たな電源開発は、開発可能性のある地点が奥地であることや、
十分な発電量が見込めないなど立地条件の厳しいところが多く、
高額な初期投資に対し、採算面での見通しがたたないことなどから、
滝下発電所以降、新たな開発は行って来なかったところ。
○ こうした中、企業局としては、今回の地震において、
外部電源なしに自力で発電を開始できる水力発電の優位性を再認識したことや、
東日本大震災を踏まえたFITの創設など社会情勢の変化も踏まえ、
これまでに、調査検討を行ってきた地点について、
改めて開発の可能性を検討するとともに、
未開発地点の情報収集にも努めてまいる考え。
<指摘>
この質問では水力発電について伺っていますので、分野を限っての質問になっていますが、新エネルギーには太陽光をはじめとする様々な種類があるのです。企業局として、北海道における新エネルギーという分野について広く可能性を切り拓き、且つ公的役割を果たしながら、同時に、それらに必要なコストを自身で積極的に稼き出さなければならないことを自覚していただきたいと考えています。
新たな電源開発はこれからの北海道の新エネルギー導入に向けた重要なテーマとなりますので、改めて関係部局とも議論してまいりたいと考えます。
(十二)財源の確保について
平成32年度以降は、電力市場の自由化の一環として競争入札で道営電気事業の売電単価が決定されるため、価格面での厳しい競争環境となります。
こうした中、発電施設の老朽化や耐震化対策などの取組を着実に進めていくため、財源の確保にどう取り組んでいく考えなのか伺います。
<答弁>
財源の確保についてでありますが
○ 平成27年4月から運転を開始している企業局最大規模のシューパロ発電所が、
FITの適用を受けていることから、当面の間、一定の収入は確保され、
安定した経営が維持できると考えているところ。
○ しかしながら、電力システム改革の影響に伴い
平成32年度以降、原則、一般競争入札が導入され
収入の動向を見通すことが困難となることや、
FIT期間の終了後には大幅な減収が見込まれ、
経営に大きな影響が生じる懸念があるところ。
○ こうしたことから、FIT終了後を見据え、安定した経営を行っていくため、
現在の利益を有効に活用して企業債の借入を抑制し、
償還元金や金利の負担を軽減するなど収支構造の見直しに取り組むとともに、
効率的な維持管理などによる支出のさらなる見直しや
経営リスクに備えた内部留保資金の確保にも取り組んでいく考え。
(十三)地域貢献について
企業局では、地域貢献の一環として、地域新エネルギー導入アドバイザー制度を設けるなど、市町村などの取組を支援してきたと承知していますが、これまでどのような取組を行ってきたか伺います。
<答弁>
地域貢献についてでありますが
○ 企業局では、エネルギーの地産地消の取組を支援するため、
一般会計が設置した「新エネルギー導入加速化基金」に
昨年度から5年間で60億円を繰り出すほか、
平成17年度に「地域新エネルギー導入アドバイザー制度」を設け、
市町村等を対象とした発電に関する説明会や勉強会の開催、
現地調査や技術の提供など、
地域における再生可能エネルギーの導入の取組を
支援してきており、本年は弟子屈町における
公園の維持管理に活用する小水力発電の導入が図られたところ。
○ また、市町村が行う小水力発電の導入モデルとして、
昨年度、夕張川の沼の沢取水堰発電所の建設に着手し、
本年度中に運転を行うこととしており、これにより得られた知見を活かしながら、
今後とも、地域が行うエネルギーの地産地消の取組を
積極的に支援してまいる考え。
(十四)市町村への支援について
今回の地震を踏まえ、市町村においては、防災拠点となる公共施設などへの再生可能エネルギー導入の動きが加速する可能性もあると考えますが、市町村には電気に関する専門的な知識や経験を有する技術者が不足しているのが現状です。今回の地震を契機として、企業局には、発電事業に関する経営、技術、ノウハウを活かして、市町村が取り組む防災拠点などへの再生可能エネルギー導入を支援していく必要があると考えますが、企業局はどのように対応していく考えか伺います。
<答弁>
市町村への支援についてでありますが
○ 今回の地震を契機として、災害時の防災拠点における
電源確保の重要性が改めて認識されたところであり、
市町村自らが地域の特性に応じた
多様な再生可能エネルギーの導入を進めることは、
大変重要な取組であると考えているところ。
○ このため、企業局では、今後、市町村に対して、
小水力発電など地産地消が可能なエネルギーに関し、
当局が有する知識やノウハウを積極的に提供していくとともに
新たに、自家消費を目的とした太陽光発電などの
再生可能エネルギーと蓄電設備との組合せによる
電力供給について調査研究を進めることとしているところ。
○ 企業局としては、これらの取組を通じ
再生可能エネルギーが防災拠点などでも有効に活用できるよう
幅広く検討を行い、その成果を市町村に提供してまいる考え。
<指摘>
この点については、企業局のみならず知事部局全てに言えることであります
が、私は、道が市町村への支援についての政策を組み立てる際に、もっと民
間力を活用することを当たり前にしていかなければならないのだと考えてい
ます。
そもそも市町村自身については、新エネルギー分野への興味はあっても、自
らが着手する為の地域資源の活用や膨大な設備費投資、そして事業を主導す
る人材の不足などを理由として、そのハードルが決して低くはないものと承
知しています。
そこに必要となるものは、民間活力でしか補うことはできないのではないで
しょうか。
むしろ、私は、多くの市町村と意見交換を重ねた経験から、道は、市町村と
優秀な技術と経験を有する民間企業とを結びつける役割を果たしていくべき
なのだと確信しています。
国の支援策の延長にあるメニューから組み立てるのではなく、道内に潜在す
るニーズと私たち自身さえも気付いていない北海道の優位性を十分に活かす
ことのできる政策とその実行を期待したいと思います。
(十五)今後の電気事業の運営について
これまで発電施設の改修、耐震化や再生可能エネルギーの導入促進などについて伺ってまいりましたが、こうした取組を進めるに当たっては、道としては、今後、どのように電気事業運営に取り組んでいく考えか、見解を伺います。
<答弁>
今後の電気事業の運営についてでありますが
○ 道営電気事業は「経済性」と「公共性」という
公営企業の基本原則のもと、クリーンで安全な水力発電所を建設、運営することで、
道内の再生可能エネルギーの拡大の一翼を担ってきたが、
今回の北海道胆振東部地震を受け、
電気は道民生活に欠かせないライフラインであり、
災害が発生した場合であっても、安定的な電力の供給に最大限努めるという
電気事業の重要な役割について改めて思いを強くしたところ。
○ 一方、今後、道営電気事業は電力システム改革により、
電力市場の動向に直接影響を受ける厳しい経営環境の中に置かれますが、
災害時においても外部電源なしに発電を開始できる
水力発電の優位性を最大限に発揮する事業運営や、
地域の防災拠点における再生可能エネルギー導入に対する貢献といった
道営電気事業が果たすべき役割はさらに広がってきているものと考えている。
○ このようなことから、私といたしましては、様々な情勢変化を的確に見極め、
安定した持続的な事業運営を行っていくため、
企業債への依存体質の脱却やさらなる効率的な運営により、
老朽発電所の計画的な改修や耐震化はもとより、
地域における再生可能エネルギー普及への貢献、
さらには、企業局自らが、新たな電源開発を検討するなどして、
道営電気事業に求められる役割を職員と一丸となって果たしてまいる考え。
<指摘>
公営企業管理者から、今後の運営について積極的な答弁をいただけたと捉え
たところです。
大いに期待するものですし、そのために必要な情報の収集や、議会議論を通
して、私もより確実な事業の実施へ向けた一翼を担っていきたいと考えてい
ます。
全ては北海道の元気の為に、お互いに責任を果たして参りましょう。
この質問は、地元を廻らせて頂いている中で、地域の方からご要望を頂き、担当部局と打合せしながら質問にまとめたものです。
災害時の避難については、私たち自身は基より、動物の避難が課題となってきています。
東日本大震災や西日本豪雨等の大災害時には、実際に様々な課題が露呈しているとお聞きしました。
避難所における衛生的な問題ばかりではなく、ペットを自宅に置いて避難された被災者が、ペットのお世話をしに自宅へ戻った際に、二次被災されてしまうなど、想定されるケースは様々です。
正しく防災訓練で、その地域の実情に合わせた想定を展開し、人とペットが共生できる環境を整えておかなければなりません。
———————————————————————————————————-
A,動物愛護対策について
動物愛護週間は、昭和48年に制定された「動物の保護及び管理に関する法律」、更に平成11年に改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」等によって、毎年、9月20日から26日の一週間と規定されています。
同法第4条第3項で、「国及び地方公共団体は、その趣旨にふさわしい行事」を実施するように努めることになっています。
昨今では、動物愛護週間に合わせて、国や地方自治体、関係団体が協力して、動物の愛護と管理に関する普及啓発の為の各種行事が実施されているとお聞きしています。
そこで数点に渡り、質問させていただきます。
① 北海道が取り組む根拠について
最初に、北海道が動物愛護対策に取り組む根拠と、どのような体制で取組んできたのか、伺います。
<答弁>
動物愛護対策の根拠と体制についてでありますが
○ 「動物の愛護及び管理に関する法律」では、
国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関する
普及啓発に努めなければならないことや、
都道府県は、国の基本指針に即した、
動物愛護管理推進計画を定めることなどが規定されているところ。
○ また、道は、平成13年に
「動物の愛護及び管理に関する条例」を制定し、
動物の愛護及び管理に関する総合的かつ
計画的な施策を実施しており、これらの法律及び条例に基づき、
動物愛護に関する取組を進めているところ。
○ 道の体制については、本庁及び振興局において、
ペットの適正飼育に係る指導や普及啓発などの事務を
実施しているところであるが、
特にペット販売店などへの立入検査や動物に起因する
苦情対応などについては、専門的知識を有する職員を配置し、
獣医師職員がその業務に対応しているところ。
② 犬猫の殺処分数について
次に、犬猫の殺処分数について伺います。
飼育放棄され道内の保健所などで引き取られた犬や猫に、できるだけ生存の機会を与える為に新たな飼い主へ譲渡するように努めていると認識していますが、やむを得ず殺処分される犬や猫が存在していることを承知しています。
道内では、どれだけの犬や猫が殺処分されているのか、また、過去10年間の推移はどのようになっているのか、伺います。
<答弁>
犬や猫の殺処分数についてでありますが
○ 動物愛護管理法では、
飼うことのできなくなった犬や猫などの引取りが、
道のほか、指定都市の札幌市、中核市の旭川市及び函館市に
義務づけられているところ。
○ これらの機関における犬や猫の殺処分数は、
10年前の平成19年度では、8,515頭、
5年前の平成24年度では、4,329頭
直近の平成29年度では、708頭となっており、
近年、大きく減少しているところ。
<指摘>
いま答弁頂いた通りに、その数を大きく減らすことが出来ているとのことですから、本法の精神の下で、皆さんの取り組んできた効果が出ていることは明白です。一方で、その大半が民間団体の熱心な活動によって支えられていることも忘れてはなりません。引き続き、民間団体支援を含めた道内隅々に行き渡る政策の展開を期待して、次の質問に移ります。
③ 道内の動物愛護週間行事について
次に、道内における取組みについて伺います。道内各地で動物愛護に関わるイベントが開催され、住民の皆さんに向けて様々な普及啓発が行われている承知しています。どのような方々が、どのような取組みを実施されてきたのでしょうか。近年の傾向や諸課題についても併せて伺います。
<答弁>
動物愛護週間行事についてでありますが
○ 道では、本庁及び14振興局が、
獣医師会、市町村、動物愛護団体などと連携し、
昨年9月2日から10月1日の間、札幌駅前地下歩行空間をはじめ、
道内各地の公共施設、振興局庁舎、大型量販店などで、
動物のふれあい体験、犬の躾教室や健康相談のほか
動物愛護パネル展、保健所に収容された犬や猫の譲渡会、
さらには、ペットの災害対応に関するスライド上映など、
広く道民に動物愛護に関する意識を普及・啓発するための取組を、
実施してきたところ。
○ 近年、道内での犬や猫の殺処分数が大きく減少するなど、
これらの普及・啓発の効果は徐々に道民に浸透しつつあるが、
いまだ行政に犬や猫の引取りを求める飼い主が存在しており、
動物を最後まで適切に飼うことへの普及啓発や、
多頭飼育に起因する周辺環境の悪化などが課題となっているところ。
<指摘>
時に社会問題化している無責任無秩序な多頭飼育がもたらす悲惨な実態は、私たちは報道などで知ることができます。飼い主のモラルが問われることとなっていますが、一方で、行政側にもそれを避けることが出来る手段が残っていることも確かだと考えています。
例えば、多頭飼育の権利と並行して求める義務や責任の明確化など、取り組む余地が残されています。道が積極的に取り組んでよい政策であると考えますので、この際に求めておきたいと思います。
④ 道の災害時対応について
次に、道の災害時対応について伺います。
平成25年5月に環境省から出ている通達によると、同法第6条の動物愛護管理推進計画に定める事項の追加として、災害発生時の動物の取り扱いが必ずしも十分でなかったことを踏まえて、災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項を定めて、計画段階で災害時対応を定めるべきことが明確にされています。
避難所では、人への支援が最優先されることではありますが、避難者の中にはペットと一緒に避難したい方も一定数いることは明らかです。避難所におけるペットのスペースは、家族同然のペットと避難する方々にとって、とても大切なことと考えられます。
道では、広く道民や避難所を運営する市町村に対して、ペットの飼育スペースの確保や、その環境についてどんな役割やどのような働きかけを行ってきたのでしょうか、伺います。
<答弁>
避難所におけるペットの対応についてでありますが
○ 道では、過去の災害時の教訓を踏まえ、
「動物の愛護及び管理に関する条例」では、飼い主の遵守事項として、
ペットと一緒に避難する「同行避難」を求めるとともに、
「北海道地域防災計画」では、
避難所等におけるペットのためのスペースの確保に
努めるよう求め、市町村に対し周知を図っているところ。
○ また、道が平成28年7月に市町村向けに作成した
「北海道版避難所マニュアル」では、ペットを滞在させるスペースは、
臭いの問題等があることから、
人の居住スペースと十分な距離をとることや、
ペットを連れた避難者の受入に当たっては、
アレルギー体質の方への配慮の観点から、
指定された場所以外での飼育を禁止することなどを示し、
避難所運営が円滑に行われるよう周知に努めているところ。
⑤ 道内自治体の災害時対応の取組みについて
次に、道内自治体の災害時対応の取組みについて伺います。
道内にも、動物を家族と位置付けて、家族同然に暮らす方々が多く、特に災害時の避難対応については、東日本大震災や九州豪雨、先日の西日本豪雨などを通して、この動物愛護の考え方から諸課題が明らかになってきているところとお聞きしています。
同法第6条や同推進計画や北海道地域防災計画などでは、災害発生時における動物の避難について定めていて、飼い主が避難する際に動物を同行させる等、飼い主自らの責任によって行うこととしています。これは、避難所に「同行避難」させることを前提していて、伴って、市町村が設置する避難所には、家庭動物のためのスペースの確保に努めるものとしています。
この点に関しては、必ずしも確保を求めていることではないことと、避難者の中に衛生上の問題や動物アレルギー保持者などへの配慮から、道民ヘの理解は、いまだ整備半ばといったところであると推察されます。
現時点での、道の認識を伺うとともに、市町村との連携や災害時対応を中心に伺います。
<答弁>
災害時対応への認識などについてでありますが
○ 避難所でのペットのためのスペースの確保については、
避難所の規模や、想定される避難者の人数などのほか、
ペットの臭いや鳴き声、アレルギー体質を持つ方への配慮も
必要であることから、地域の実情に合わせて
避難所を運営管理する市町村がスペース確保の是非や、
具体的な場所等を判断していくこととなるが、
現段階では必ずしも十分な状況ではないと認識。
○ 道としては、今後とも受入体制の整備が
進んでいない市町村に対して、速やかに、
避難所でのペットのスペースについて適切な配慮がなされるよう
求めていくとともに、避難所でのペットの受入について、
広報誌やホームページを活用するなどして、
広く地域住民に周知されるよう、働きかけてまいりたい。
<指摘>
避難所におけるペットの受入体制については、道内自治体の取組みが十分とは言えないとお聞きしましたし、その実態は大部分で検討されていないものと承知しています。まさに道の役割がそこにあると考えていますので、部として力を入れて速やかに働きかけるように要望しておきます。
⑥ フレンドリードックテストについて
次に、フレンドリードックテストについて伺います。
道内では、全日本犬訓練士連合協会の北海道地区担当となる北海道訓練士会が、「フレンドリードックテスト」の普及に尽力されていて、既に、道や各振興局、市町村と連携しながら活動に従事されていると承知しています。
これは、犬の福祉に貢献し、人との共生社会に適応した指導および教育を行うことを目的として行われているプロジェクトとなっており、飼い主の自覚や犬の躾が出来ているかを確認する試験と聞いています。
私は、災害時対応をスムースに行うためにも、これらの趣旨を飼い主に求められていることは基より、広く道民に周知させておくことこそが、災害発生時の避難所設置に伴う無用な軋轢を避けることに直結するものと確信しているところです。民間によるこれらの活動をより積極的に取り込んで、目的を達成していく必要があると考えますが、道の見解を伺います。
<答弁>
民間による活動についてでありますが
○ 道が動物愛護週間などで実施している、
「ペットの躾教室」、「健康相談」、「動物とのふれあい体験」、
「犬猫の譲渡会」などの行事では、専門知識を有する獣医師会や、
動物愛護団体、犬の訓練士の方々など
民間団体との連携が不可欠となっているところ。
○ また、ペットの災害対策においては、
飼い主による平常時からの適正な飼育が大変重要であることから、
「躾教室」や「フレンドリードッグテスト」など
躾に関する普及啓発の取組は、
災害時の飼い主との同行避難を想定した備えとして
有効なものと考えているところ。
○ 道としては、今後とも、先ほど申し上げた民間団体などに
道が実施する動物愛護週間行事への参加を呼びかけるとともに、
団体が実施する譲渡会などの会場の確保や
広報等の協力・支援を行うなどして連携を密にし、
動物の適正飼育やペットの災害対策について、
広く道民に普及啓発を図ってまいりたい。
<指摘>
こういった民間団体の活動を積極的に支援していくことは、行政が果たし切れないことや、痒い所に手が届く施策として欠かせないものであることに違いありません。むしろ現場で携わっていただいている皆さんの知見を活かしきることができるように、今以上に踏み込んだ協働を実現させていかなければなりません。各団体との情報交換やより効果の高い取組みの発掘や開発を推進するように要請しておきたいと思います。
⑦ 今後の道の取組について
最後に、今後の道の取組について伺います。
これまで質問してきたように、動物愛護週間は、私たちの日常生活に深く関与している動物の適切な飼養や管理について、責任ある飼い主になってもらうことや、私たちへのルールを啓発させるために大切な機会となっています。特に、災害発生時においては、いまだ備えが不十分であることが、これまでの大災害を通して、関係者によって提起されてきているところです。
災害は、いつどこで起きるのか分かりません。平時から道民への呼び掛けは基より、避難所の適切な運営、被災動物の救護活動、災害時を想定した訓練など万全の体制を整えておくことが重要と考えています。
最後に、道は、今後、災害時のペット対策をどのように位置づけて、市町村と連携しながら、道民に広く知らしめることが出来るように取り組んでいくのか、伺います。
<答弁>
今後の道の取組についてでありますが
○ 道では、動物愛護管理法の改正や
国の基本指針などの社会情勢の変化を踏まえ、
「動物愛護推進計画」を改正して、本年3月に
第2次計画を策定したところであり、
この中で、防災訓練やペットの受入体制の整備など、
災害への対策は、動物の適正な飼育や普及啓発と同様に、
主要な施策と位置付けているところ。
○ 道としては、今後、飼い主に対し、動物愛護週間等のイベントや
道のホームページなどの広報媒体を通じて、
災害対策のさらなる普及啓発を行うとともに、
10月には、獣医師会や市町村、動物愛護団体などへ呼びかけ、
災害時に関係機関が広域的に協力、連携して
ペットの災害対策が行われるよう、同行避難を想定した図上訓練を
環境省との共催により道内で初めて実施するなど、
災害時におけるペット対策の強化を図ることとしており、引き続き、
人と動物が共生できる社会の実現に向け、取り組んでまいる。
<指摘>
道では、北海道防災総合訓練等を実施していますが、災害時における同行避難が明示されている現在では、その防災訓練のメニューの一つとして取り入れられるべきものであると考えています。関係各部と連携をとりながら、災害時のペット対策を想定した訓練を行うことによって、各自治体に留まることなく、住民の皆さんにも、私たちの暮らしに寄り添うペットの愛護と管理について考えて頂く機会を、道が積極的に提供していただけるように強く要望して、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。